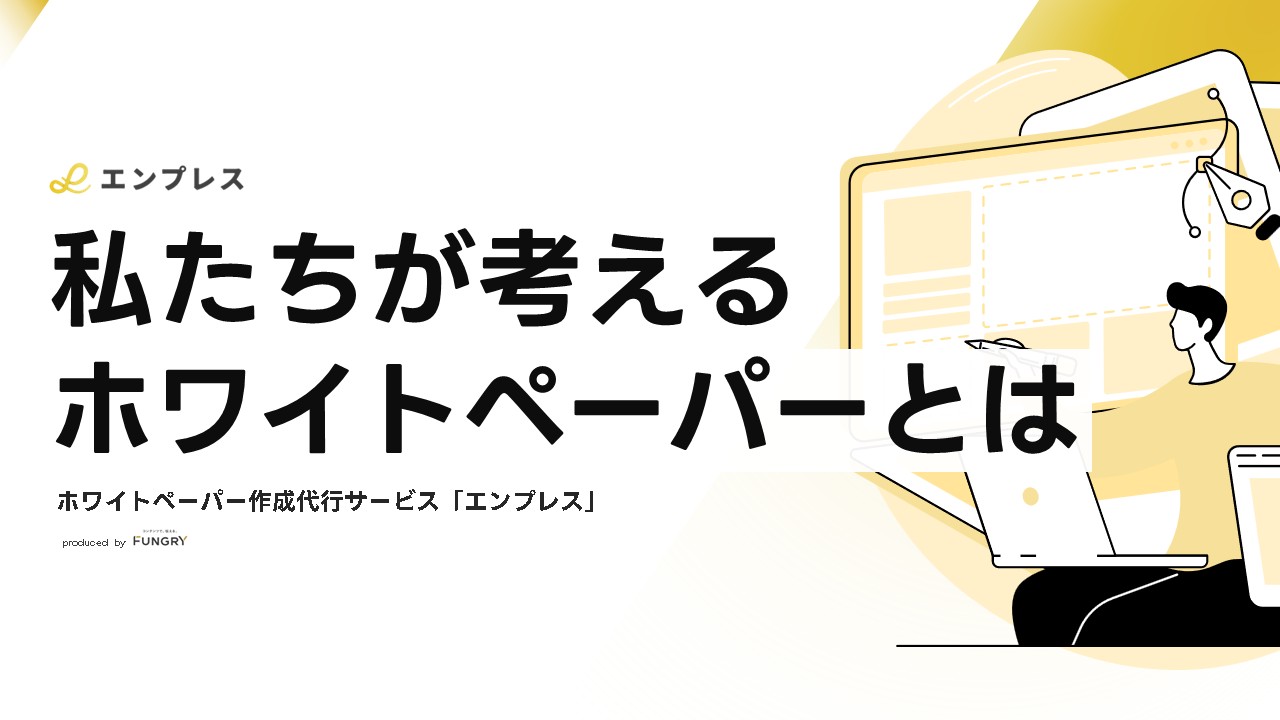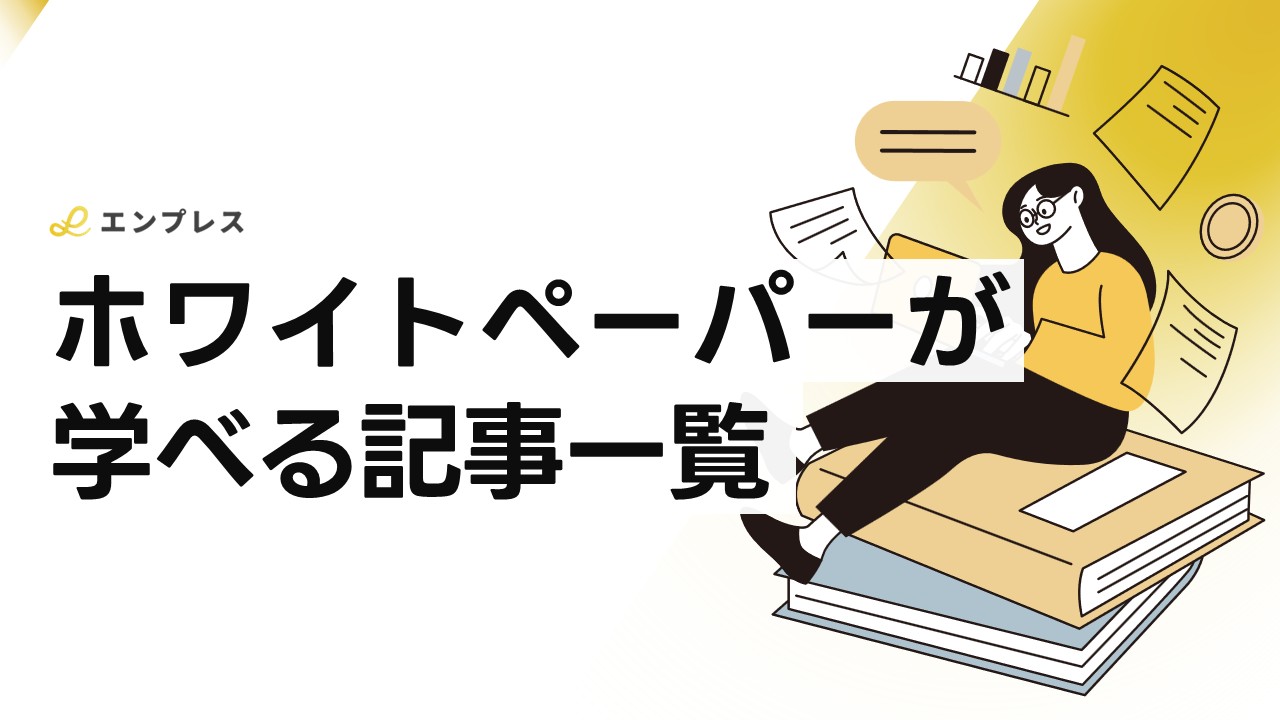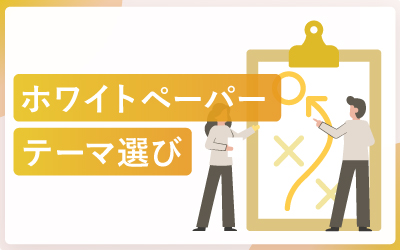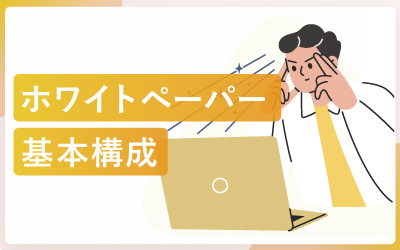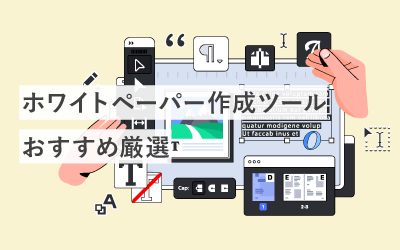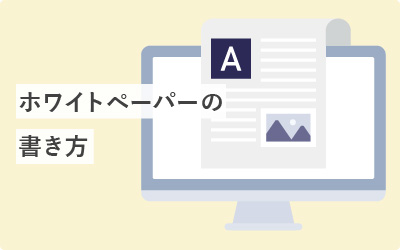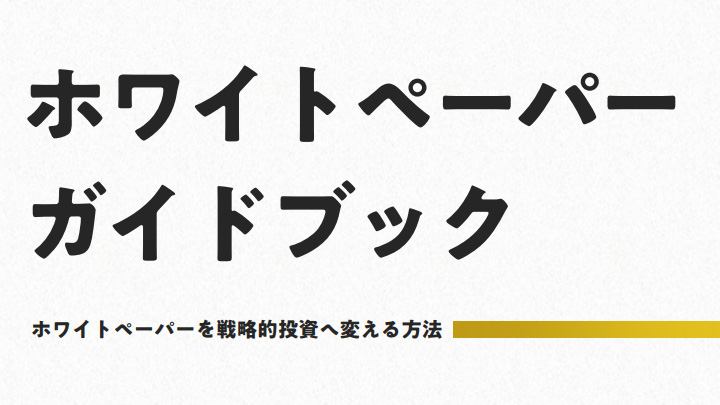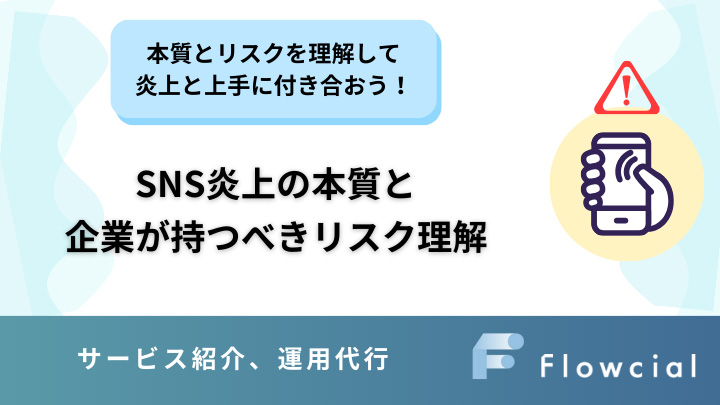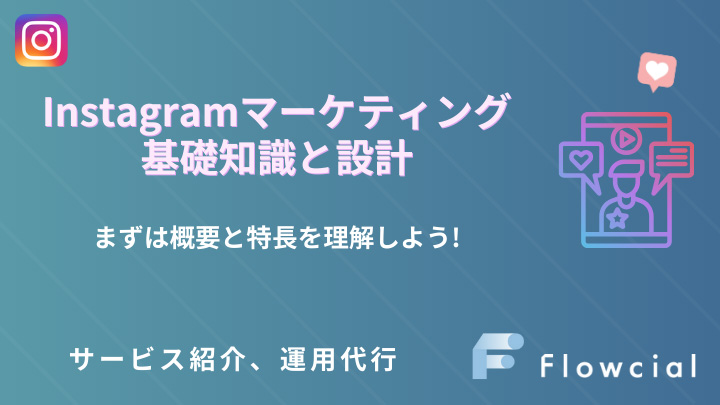いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーは作るには、細かい工程があるため、すべての流れを確認頂くのがおすすめです。
ホワイトペーパーは、企業のマーケティング戦略において非常に有効なツールです。
その制作プロセスを適切に進めることで、高い成果へと繋げることはできますが、そもそも作り慣れていないと流れを掴めていない場合も。
時間やコストをかけて制作するのですから、より成果が出せるホワイトペーパーが作れるように、具体的な制作フローを1~10まで解説していきます。
- 目次
- 1. 現状を深く掘り下げ、課題を特定する
- 2. 優先すべき課題を見極め、解決の糸口を探る
- 3. ホワイトペーパー制作の明確な目的を設定する
- 4. 誰に届けるか?ターゲットを詳細に設定する
- 5. ターゲットの具体化:ペルソナを設定する
- 6. プロジェクト全体の目標を具体的に設定する
- 7. プロジェクトの進行を管理するスケジュールを策定する
- 8. 専門性を有するプロジェクトチームを結成する
- 9. ターゲットに響くテーマとジャンルを決定する
- 10. 質の高い情報収集を行う
- 11. 構成(台割)を練り上げる
- 12. 視覚的に魅力的なデザイン見本を探す
- 13. 制作全体のルール(レギュレーション)を定める
- 14. 最適な制作ツールを選定する
- 15. 読者の心を掴む原稿を執筆する
- 16. 情報を「デザイン」として視覚化する
- 17. 公開前の最終チェックを徹底する
1. 現状を深く掘り下げ、課題を特定する
ホワイトペーパーの制作へ取り掛かる前に、まずは自社が抱える具体的な課題を明確にすることが肝心です。
「売上が伸び悩んでいる」
「リード獲得が不足している」
「ブランド認知度が低い」
このような漠然とした課題ではなく、その背景にある真の原因を探っていく。
初期段階で行う深い現状把握は、ホワイトペーパーが単なる情報提供で終わらず、実際に自社の課題解決に貢献できるかを判断する上で不可欠な工程です。
もし、ホワイトペーパーが最適解でないと判断されれば、別の施策にリソースを投入する判断も必要になります。
このステップを疎かにすると、後の工程で方向性を見失い、期待する効果が得られない可能性が高まるため、自分たちの課題把握から始めていきましょう。(すぐデザインから入ろうとしてはダメ!)
2. 優先すべき課題を見極め、解決の糸口を探る
現状の把握が完了したら、次に重要なのは、洗い出した課題の中から最も優先度の高いものを見極めることです。
表面的な問題に囚われず、「なぜその課題が発生しているのか」「根本的な原因は何か」といった問いを繰り返しながら深掘りしていく必要があります。
たとえば、リード獲得が不足している課題の裏には、ターゲット設定のズレやコンテンツの魅力不足が隠れているかもしれません。
この優先順位付けが、ホワイトペーパー制作の方向性を決定づける羅針盤となります。
最も解決すべき課題に焦点を当てることで、より効果的で具体的な解決策を提示できるホワイトペーパーが生まれるのです。
3. ホワイトペーパー制作の明確な目的を設定する
優先すべき課題が定まったら、「なぜ、このホワイトペーパーを作るのか」目的を具体的に設定しましょう。
この目的が曖昧なままだと、制作過程でメンバー間の認識のずれが生じたり、途中でモチベーションが低下したりするリスクがあります。
例えば、「新規リードを月間100件獲得する」「特定製品の無料トライアル申込数を20%向上させる」「顧客ロイヤリティを高めるための教育コンテンツとして活用する」など、具体的な数値目標や期待する行動まで落とし込むことが理想です。
関わるすべてのメンバーがこの目的を共有し、一丸となって取り組むことで、制作の質が高まり、最終的な成果に直結します。
4. 誰に届けるか?ターゲットを詳細に設定する
目的が明確になったら、次は「誰にこのホワイトペーパーを届けたいのか」ターゲットを明確に設定します。
ターゲットが漠然としていると、ホワイトペーパーの内容が誰にも響かず、本来の目的から外れたものになりかねません。
例えば、「中小企業のIT担当者」だけでなく、「企業のDX推進に課題を感じており、具体的なソリューションを探しているIT担当者」のように、より深く不安や悩みを理解した設定が求められます。
ホワイトペーパーの成功は、この「誰に伝えるか」を正確に見極めることに大きく左右されます。
ターゲット見極めの重要性:顧客の「心」を理解する
商品や価値観の多様性
お客様は一様ではありません。ある人は費用対効果を重視し、また別の人は品質やブランド価値に重きを置きます。ターゲットの価値観を理解することで、ホワイトペーパーで伝えるべきメッセージも変わってきます。
言語と文化の壁
どんなに素晴らしい情報も、相手が理解できる「言語」でなければ伝わりません。ここでいう「言語」とは、顧客の業界特有の専門用語や、お客様が抱える課題に対する共通認識を指します。多くの企業が自社目線で情報を発信しがちですが、これではターゲットにとって「伝わらない日本語を話している」状態と同じです。
顧客の購買フェーズ
顧客は常に購買意欲が高いわけではありません。いますぐ商品を探している「顕在層」は少数であり、競合も多いため競争が激化します。一方、まだ購買意欲が明確ではない「潜在層」は、ライバルが少なく、関係性を築きやすい層です。顧客がどのフェーズにいるのかを理解し、そのフェーズに合わせた情報提供をすることで、押し付けがましくない、自然なコミュニケーションが生まれます。
「種まき」と長期的な関係構築
潜在層へのアプローチは、未来に向けた「種まき」に似ています。初期段階で価値を提供し、信頼関係を築くことで、将来的にお客様が課題に直面した際、自社が「第一想起」される可能性が高まります。これは、長期的なビジネスチャンスを育む上で非常に重要な視点です。
5. ターゲットの具体化:ペルソナを設定する
ターゲット設定をさらに深掘りし、「ペルソナ」として具体的な人物像を創造します。
ペルソナとは、ターゲット層を代表する架空の人物像のことです。
「どのような企業に勤めているのか」「役職は何か」「どんな課題を抱えているのか」「どんな情報源から情報を得ているのか」「どのような性格で、どんなことに興味があるのか」など、多角的に掘り下げていきます。
可能であれば、1~3人程度のペルソナを設定し、それぞれの課題やニーズ、情報収集方法などを具体的に記述しましょう。
ペルソナの解像度を高めることで、ホワイトペーパーの内容が、まさにその人物に語りかけるような、パーソナライズされたものになります。
これにより、ダウンロード時のコンバージョン率や、その後のエンゲージメント率の向上なども期待できます。
6. プロジェクト全体の目標を具体的に設定する
ホワイトペーパーのターゲットが明確になったら、具体的な目標を設定します。
この目標は、ホワイトペーパーの制作に携わるすべての部署(マーケティング、営業、制作など)が共有し、連携をスムーズにするための羅針盤となります。
たとえば、「ホワイトペーパー公開後3ヶ月で、ダウンロード数500件、そのうち商談化率10%」といった具体的な数値目標を設定することで、各部署の役割が明確になり、責任の所在もはっきりします。
共通の目標を持つことで、部署間の連携不足や責任の押し付け合いを防ぎ、ホワイトペーパーの効果を最大限に引き出すことが可能になります。
7. プロジェクトの進行を管理するスケジュールを策定する
ホワイトペーパー制作には、企画、原稿作成、デザイン、公開ページの準備など、多岐にわたる工程が存在します。
そのため、設定目標から逆算し、具体的なスケジュールを策定することが不可欠です。
「いつまでに原稿を完成させるか」「デザインの締め切りはいつか」「校正期間はどのくらい取るか」タイムラインを明確にし、プロジェクト開始時にすべてのメンバーと共有しましょう。
大まかなスケジュールでも構わないので、早い段階で計画を立てることで、各メンバーが自身の役割と納期を認識し、プロジェクト全体の進捗を滞りなく管理できます。
スケジュールがないまま進めると、各々が独自のペースで動き、結果的に納期遅延や手戻りが発生するリスクが高まります。
8. 専門性を有するプロジェクトチームを結成する
スケジュールに沿って高品質なホワイトペーパーを制作するためには、適切なスキルとノウハウを持つメンバーでプロジェクトチームを編成することが重要です。
一人で全てを完結できるケースは稀であり、通常は戦略立案、企画、原稿執筆、デザイン、Webページ構築など、様々な専門性が必要とされます。
各タスクに最適なメンバーを選定し、それぞれの役割を明確にしましょう。
もし社内リソースが不足している場合や、特定のスキルが足りない場合は、制作代行会社や外部の専門家との連携も積極的に検討したいところ。
適切なチーム体制を構築することで、効率的に質の高いホワイトペーパーを制作できる基盤が整います。
外部専門家との協業における留意点
外部コンサルタントや制作会社を選定する際には、現場の状況を深く理解し、具体的な解決策を提案できるかを見極めることが肝心です。
表面的なアドバイスに終始する「口だけ」の存在では、現場メンバーとの間に不協和音が生じ、プロジェクトが円滑に進まない可能性があります。
9. ターゲットに響くテーマとジャンルを決定する
ホワイトペーパーの制作において、テーマやジャンルの決定は非常に重要であり、ターゲットのニーズや抱える課題によって、求められる情報の種類は大きく異なります。
たとえば、幅広いリードを獲得したい場合は、基礎知識やノウハウ系のテーマが適しています。
一方、質の高いリードや具体的な商談に繋げたい場合は、成功事例や導入事例、具体的な課題解決策を提示するテーマが効果的です。
最初に設定したターゲットと目的に立ち返り、最大限の成果をもたらすテーマを慎重に選びましょう。
この段階でのテーマ選定が曖昧だと、制作後の効果が限定的になる可能性があります。
ホワイトペーパーのテーマ選定プロセス:自社状況と利用シーンの融合
ホワイトペーパーのテーマ選定は、自社の集客状況とホワイトペーパーの利用シーンという二つの視点を組み合わせることで、戦略的な選択が可能になります。
これらの視点を総合的に考慮することで、集客からダウンロード、そしてその後の顧客育成までをシームレスに繋ぐ、効果的なホワイトペーパーのテーマ選定が可能になります。
自社状況(集客状況)の視点
現在、どのトピックがWebサイトで高いアクセス数を得ているか、どのキーワードで検索流入が多いかなどを分析し、既存の人気記事を補完するテーマを選ぶと効果的です。
既に高い関心があるトピックであれば、そこからのダウンロード導線もスムーズになり、リード獲得に繋がりやすくなります。
逆に、全く集客できていないトピックを選んでも、成果が出にくい傾向にあります。
利用シーン(ホワイトペーパーを使う場所)の視点
ホワイトペーパーをどのように活用するのかを明確にしましょう。
例えば、特定イベントのフォローアップ用、営業資料として活用するため、Webサイトからのダウンロードコンテンツとしてなど、利用シーンによって最適なテーマや内容が変わります。
10. 質の高い情報収集を行う
テーマとジャンルが決定したら、ホワイトペーパーに盛り込む情報の収集を徹底的に行います。
この段階で十分な情報を集めることは、後々の手戻りを防ぎ、制作プロセス全体の効率を高める上で極めて重要です。
情報が不足していると、後から追加や修正が発生し、構成やデザインにも影響を及ぼし、時間と労力が大幅に増加します。
関連情報を網羅的に揃えることで、制作がスムーズに進み、完成度の高いホワイトペーパーを効率的に仕上げることができます。
このステップを疎かにすると、最終的に質の低いホワイトペーパーになりかねないため、十分な時間を確保し、多角的な情報収集を心がけましょう。
11. 構成(台割)を練り上げる
収集した情報をもとに、読者にとって分かりやすく、引き込まれるような構成(台割)を作成します。
これは、ホワイトペーパー全体の「設計図」にあたるものであり、大まかな流れを決め、各ページにどのような情報を配置するかを割り振っていきます。
一般的なホワイトペーパーは1ページあたり300~500文字程度で、合計11~20ページ程度(3,000~6,000文字相当)が目安となります。
構成の段階で、盛り込むべき情報とその配置が明確になっていないと、後続のライターやデザイナーが迷い、制作時間が大幅に増えてしまう。
効率的かつ質の高いホワイトペーパーを制作するためにも、この構成作りは極めて重要な工程です。
12. 視覚的に魅力的なデザイン見本を探す
構成が固まったら、ホワイトペーパーの「見た目」を決定づけるために、デザイン見本を探しましょう。
デザイン見本を参考にすることで、視覚的にどのような印象を与えたいか、ターゲットにとって使いやすいレイアウトは何か、といったアイデアを得ることができます。
実際に公開されている他社のホワイトペーパーを参考にしたり、競合他社のデザインをチェックしたりするのはもちろん有効です。
さらに、デザイン見本が多数掲載されているWebサイトを活用し、異業種の事例も参照することで、新しい視点やクリエイティブな発想を得られることがあります。
これらの参考をもとに、最適なレイアウト、配色、フォントなどを検討し、ホワイトペーパーの品質向上に繋げましょう。
13. 制作全体のルール(レギュレーション)を定める
ホワイトペーパーを制作する際、最初の1冊だけでなく、将来的な更新や複数種類の制作を視野に入れ、制作ルール(レギュレーション)を定めておくことが重要です。
使用するフォントの種類やサイズ、カラーパレット、図表の形式、レイアウトの基本原則など、統一感を持たせるための明確なルールを設定します。
これにより、複数のホワイトペーパーを制作する際の手戻りが減り、新しいメンバーでもスムーズに作業を進められるようになります。
また、内容の更新や修正が必要になった場合も、明確な基準があることで迅速かつ一貫した対応が可能となり、制作効率の向上とコスト削減に貢献します。
14. 最適な制作ツールを選定する
ホワイトペーパーは通常、PDF形式で顧客に提供されるため、PDF化できるツールであればどのようなものでも構いません。
しかし、制作ツールの選定は非常に重要なポイントです。特定のツールを扱える人が限られている場合、その後の更新作業が属人化し、情報が古くなるリスクが高まります。
制作ツールは、関わるメンバー全員が「扱いやすい」と感じるものが理想的です。
一般的なデザインツールから、オンラインで共同編集が可能なツールまで、チームのスキルレベルや予算、今後の運用体制などを考慮し、最適なツールを選びましょう。
15. 読者の心を掴む原稿を執筆する
作成した構成(台割)に基づき、各ページに入れる原稿を執筆していきますが、文章作成に不慣れな場合は、専門のライターをチームに加えることを検討しましょう。
ホワイトペーパーには、通常3,000~6,000文字程度の原稿が必要とされ、最低でも2,000~4,000文字は必要となるため、専門的な文章スキルが求められます。
ただし、原稿段階で内容が固まっていないと、後のデザインやレイアウト調整に支障をきたすため、早い段階でアウトラインや大枠を固めておくことが重要です。
また、ターゲットの関心を引くために、難しい専門用語や業界特有の言葉を使う場合は、わかりやすい解説を加え、読み手がスムーズに内容を理解できるよう配慮しましょう。
読み手の視点に立ち、簡単な言葉で、かつ説得力のある文章を心がけることが成功への鍵となります。
16. 情報を「デザイン」として視覚化する
原稿が完成したら、いよいよ情報のデザインに取り掛かります。
原稿がない状態でデザインを先行させると、後からテキストを入れ込む際にレイアウトが崩れたり、情報の整合性が失われたりするリスクが高まります。
特に社内デザイナーに依頼する場合は、構成、台割、原稿をすべて提供した上で、その内容に基づいてデザインを進めてもらいましょう。
デザインは単に見た目を美しくするだけでなく、情報を整理し、読み手にとって理解しやすい形で視覚化する重要な役割を担っています。
情報が不足したままデザインが先行してしまうと、ホワイトペーパーの目的、目標、ターゲットといった重要な要素が曖昧になり、結果として「情報」が正しく伝わらない、見た目だけのデザインになりがちです。
デザイン先行で進めることは、かえってデザインが失敗する原因となることがあるため、情報の整理と原稿作成を優先し、その上で効果的なデザインを施すことが肝要です。
17. 公開前の最終チェックを徹底する
最終的に完成したホワイトペーパーは、制作担当者以外のメンバーに依頼し、徹底的なチェックを行いましょう。
ダウンロードされたホワイトペーパーは回収が難しく、内容に間違いがあったとしても公開後に修正することは困難です。
そのため、公開前の段階で細部まで完璧に整えておく必要があります。
特に以下の3つのチェックポイントに注目して確認を進めましょう。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 視認性 | レイアウトやフォントサイズ、配色など、全体的に「見やすいか」を客観的に評価します。 |
| 可読性 | 文章の長さ、専門用語の使用、句読点の使い方など、文章が「読みやすいか」を確認します。 |
| 判読性 | 内容の論理的な流れ、情報の一貫性、誤字脱字など、全体として「内容が理解しやすいか」を判断します。 |
具体的なチェック表はこちら。
| ポイント | 〇 / △ / × | チェック内容 |
|---|---|---|
| 視認性 | テキストと背景のコントラストが適切で見やすい配色か? | |
| 全体のフォントサイズが適切で読者にストレスを与えていないか? | ||
| 余白が適切に保たれており要素が詰め込まれ過ぎていないか? | ||
| 見出しと本文が明確に区別されており視線誘導はスムーズか? | ||
| 挿入した図表や画像がぼやけておらず視覚的にわかりやすいか? | ||
| ページ番号が適切に配置されているか? | ||
| 可読性 | 誤字脱字や文法の誤りはないか? | |
| 1文が長すぎず適切な改行がされているか? | ||
| 必要以上に難しい専門用語は入っていないか? | ||
| 情報が箇条書き・リストなど活用されて整理されているか? | ||
| ターゲット層に合わせたトーンや口調になっているか? | ||
| 日本語の表現が助長ではなく明確であるか? | ||
| 判読性 | 情報の流れが論理的であるか? | |
| 主張がはっきり示されているか? | ||
| 具体的な根拠は記されているか? | ||
| 内容が読者のニーズや課題に直結しているか? | ||
| 抽象的な説明ではなく具体例やケーススタディが含まれているか? | ||
| 読者にとって不要な情報や曖昧な表現が省かれているか? |
チェックする際は、評価者自身の好みや主観が入り込まないよう、事前にチェックリストを作成し、具体的な評価基準を設けることがお勧めです。
これにより、客観的かつ効果的な最終チェックが可能となり、高品質なホワイトペーパーの公開に繋がります。
ホワイトペーパー制作は多岐にわたる工程を経て完成しますが、それぞれのステップを丁寧に進めることで、マーケティング戦略に貢献する強力なツールになっていくため、本記事がお役に立てますと幸いです。