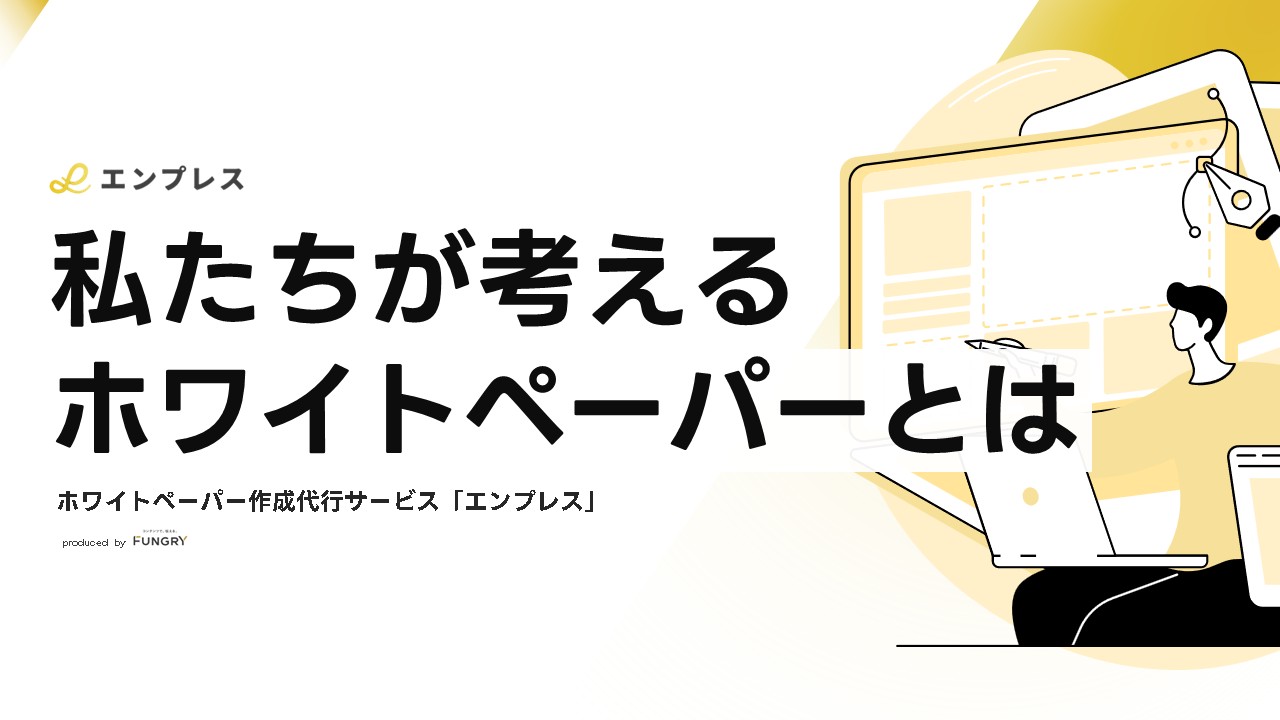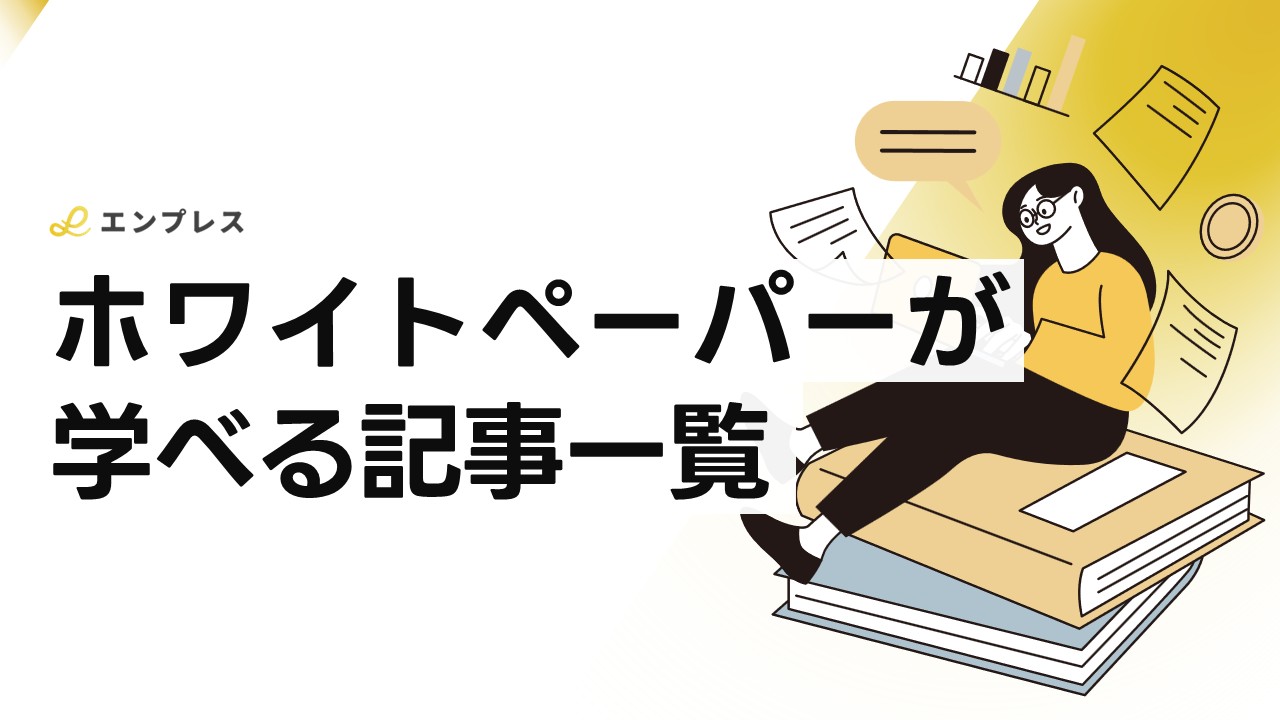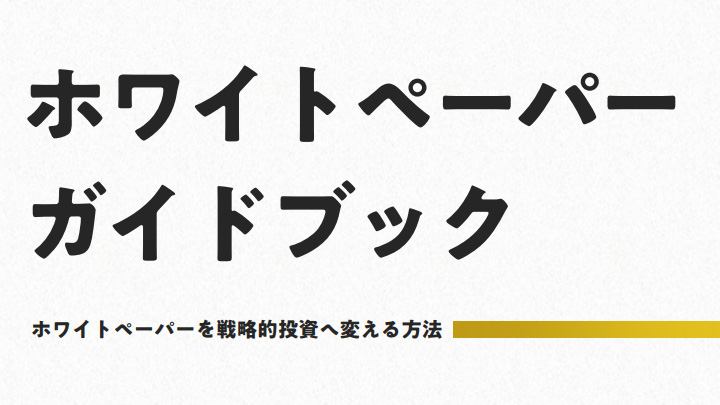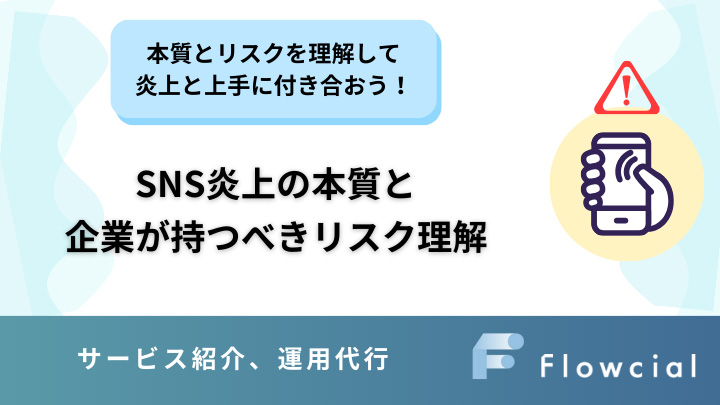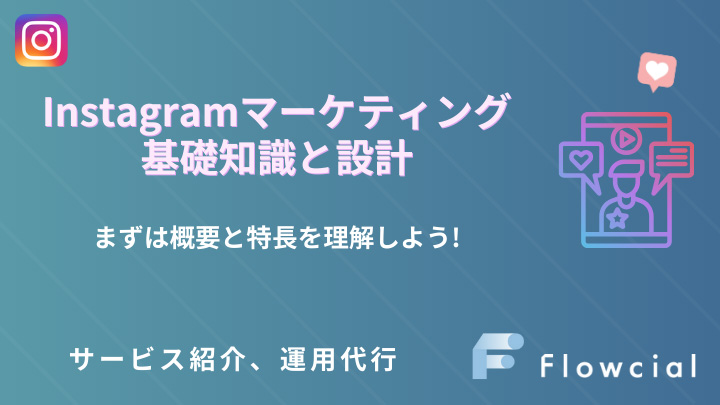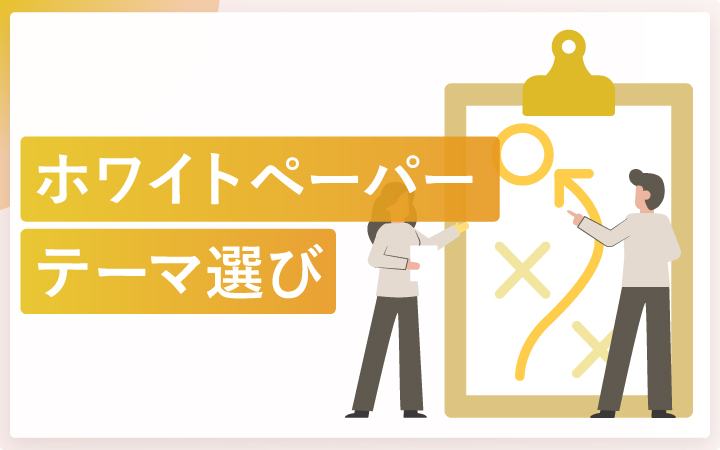
いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーを作る時に、何を軸にすればいいのか、テーマについて解説!
「ホワイトペーパー」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
もしかしたら、「会社案内」や「商品パンフレット」のような、ただの資料だと感じているかもしれませんね。
確かに、形の上ではPDFファイルなどの資料です。
しかし、BtoB(企業間の取引)の世界で使われるホワイトペーパーは、普段あなたが手渡しする資料とは全く違う役割を持たされています。
ホワイトペーパーはウェブサイトを通じて、会ったことのないたくさんの人にダウンロードしてもらうことを目的とした、ビジネスを成長させるための重要なマーケティングツールです。
そして成果を出すためには「テーマ(企画)」選びが何よりも重要であり、魅力的でお客様の心に響くものであればあるほど、たくさんのダウンロードにつながり、最終的なビジネスの成果にも良い影響を与えてくれる。
この記事では、どんな状況でも、あなたの状況にぴったりなホワイトペーパーのテーマが選べるように、その考え方と具体的なステップを分かりやすく解説していきます。
- 目次
- ホワイトペーパーは「ただの資料」ではない
- ダウンロード数だけを追いかける落とし穴:なぜ「目的」と「状況」が大切なの?
- セオリー通りに進めないテーマ選びの重要度
- 目的達成に導くホワイトペーパーのテーマ選定3ステップ
- 最後に
ホワイトペーパーは「ただの資料」ではない
あなたが普段、特定の商談相手に手渡す資料、または社内向け資料は、その場で説明を加えたり、質問に答えたりしながら渡しますよね。
相手はどんな情報が欲しいのか、何に困っているのかが分かっているから、内容も調整しやすいはずですが、ホワイトペーパーの場合は状況がそもそも違います。
ウェブサイトに置いて、あなたがその場にいなくても、不特定多数の見込み顧客にダウンロードしてもらうものなので、どんな気持ちで、何のためにダウンロードしたのかを、細かく知ることはできません。
だからこそ、ホワイトペーパーのテーマ(企画・内容)を選ぶことは、ただ「面白そうなネタを探す」のとは訳が違います。
これは、会社全体のマーケティング戦略、具体的な目的、そして「どんな人に届けたいか」ターゲットのすべてに深く関わる、とても大切な「戦略的な意思決定」でもあります。
テーマが曖昧だと、制作に関わる人たちの間で認識のズレが生まれ、せっかく時間やお金をかけて作ったのに、期待した成果が出ない…なんてことにもなりかねません。
このような理由からホワイトペーパーを作る前は、テーマ選びに十分な時間と検討をかけることが、本当に大切なのです。
テーマ選定は単なるネタ探しではない
ホワイトペーパーのテーマは、面白そうなネタを見つける、単純な行為ではありません。
企業全体のマーケティング戦略、具体的な目的・目標、そして設定したターゲットに対して、どんなメッセージを届け、どのような成果を得たいのか、その全てに深く関わる戦略的な意思決定にテーマが関わります。
企画の良し悪しは、その後のライティング、デザインなどの制作プロセスはもちろん、最終的なダウンロード数やそこから獲得できるリードの見込み度にも直接的に影響します。

このように、テーマは目的達成と具体的なアウトプットを結びつける「要」となり、逆に言えば、この要が揺らいでしまうと、後続の全てが成り立たなくなります。
そしてホワイトペーパーの制作から活用に至るプロセスには、複数の担当者が関わることが一般的。
もしテーマ性や伝えたいメッセージが曖昧だと、各担当者が独自の解釈で作業を進めてしまい、結果として完成したホワイトペーパーが当初の目的や理想から大きく乖離してしまうリスクが高まります。
結果として小さなコミュニケーションロスや認識のズレが積み重なることで、最終的な成果に大きな悪影響を及ぼし、ホワイトペーパーへの投資効果が正しく評価されない事態を招きかねないため、しっかりと決めていく必要があります。
ダウンロード数だけを追いかける落とし穴:なぜ「目的」と「状況」が大切なの?
「ホワイトペーパーはたくさんダウンロードされた方がいいんでしょ?」
そう思っている方もいるかもしれませんね。
もちろん、ダウンロード数は多いに越したことはありませんが、実はそれだけが正解ではありません。
ホワイトペーパー制作の目的は、単に数を増やすことではなく、「会社の目標に合った見込み顧客(将来のお客様候補)とつながり、その後の行動へとつなげる準備をすること」にあるからです。
では、なぜダウンロード数だけを追いかけると問題が起きるのでしょうか?
もしテーマを広げすぎて、誰にでも当てはまるような内容にしてしまうと、確かにダウンロード数は増えるかもしれませんが、中にはあなたの会社のサービスや商品にはあまり関心がない人、あるいは現状では全く必要としていない人も含まれている可能性が高くなります。
そういった方々へいくらアプローチをしても、門前払いがいいところ…。
ターゲット外にダウンロードされると困ること
目的の見込み顧客以外のダウンロードが増えてしまうと、気持ちも低く、行動を起こさない方が多ければ、その後にビジネスへ繋げることが難しくなります。
話もなかなか進まず、時間ばかりかかってしまう…。
他にも、
- ナーチャリングに労力がかかる(マーケティング資源をムダにしてしまう)
- 期待がずれてしまう(期待を裏切られたと感じてマイナスの印象が残ってしまう)
ただダウンロード数を増やすことだけを考えると、かえって効率が悪くなり、最終的なビジネスの成果には結びつきにくくなる可能性があるのです。
ホワイトペーパーのテーマを選ぶ時には、「何のためにこのホワイトペーパーを作るのか(目的)」と「今の会社や事業、マーケティング活動がどんな状況にあるのか(状況)」を深く考えることが、とても重要に。
たとえば「今すぐサービス導入を検討している、やる気のあるお客様候補と出会いたい」状況であれば、初心者向けの基本的なノウハウの資料ではなく、具体的な導入事例や、商品の機能が詳しくわかる資料の方が、目的に合ったお客様候補を引き寄せられます。
「ホワイトペーパーのテーマの質が、最終的な成果を左右する」と言われるのは、まさにこのような理由があるからであり、目指すべき成果を明確にし、それに合ったテーマを選ぶことで、質の高い見込み顧客との出会いを増やし、ビジネスを成功に導くことができるのです。
ホワイトペーパーの質が成果を左右する
では、なぜホワイトペーパーのテーマ選びが、ダウンロード数やそこから繋がる成果にここまで決定的な影響を与えるのでしょうか。
その根幹には、企業のマーケティング戦略や、そのホワイトペーパーを作成する具体的な目的が深く関わっています。
例えば、「リードを増やしたい」「見込み顧客を育成したい(ナーチャリング)」「既存顧客の満足度を向上させたい」「カスタマーサポートへの問い合わせ工数を削減したい」など、ホワイトペーパーの目的は多岐にわたります。
それぞれの目的によって、最も響くメッセージや必要な情報も変わってくる。
しかし、目先の効率性だけを追い求めたり、多くの人に届けようと考えすぎたりすると、テーマ設定が広くなり曖昧になりがちです。
具体例としてリード獲得を目指すマーケター向けホワイトペーパーを企画する際、
避けるべきテーマ例: 「リード獲得マニュアル」
効果的なテーマ例 : 「リードの獲得数を増やす10のコツ」
この二つは一見似ていますが、受け手に与える印象は大きく異なります。
「10のコツ」をテーマした方は、単に「リード獲得方法」を網羅的に解説するだけでなく、「数を増やす」具体的なメリットを提示し、「10のコツ」と絞り込むことで情報の整理と実行可能なイメージを与え、言葉の表現として「コツ」を取り入れお客様の関心を引きつけます。
このようにテーマを絞り込むことで、特定のターゲット層に深く刺さる、より魅力的で具体的な表現を生み出しやすくなります。
テーマ性の明確さは、コンテンツのライティングはもちろん、デザインや構成といったアウトプットの質と方向性を決定づけ、結果としてそれが直接的なダウンロード数に繋がり、マーケティング目標の達成度合いにも影響を与えるのです。
テーマ選びこそが、ホワイトペーパーの成否を分ける最初の、そして最も重要なステップと言えます。
セオリー通りに進めないテーマ選びの重要度
BtoBマーケティングの世界では「契約に近い、見込み度の高いお客様候補を狙う施策から優先すべき」、このような考え方が一般的です。
そのため「事例」や「製品・サービス資料」のような、具体的な検討フェーズのお客様に響くホワイトペーパーを作るのがセオリーだ、と言われることも少なくありません。
もちろん、これは正しい考え方です。
しかし、それが常にすべての会社にとっての「最適解」かといえば、そうではない場合もあります。
特に、これまでホワイトペーパーを使ったマーケティング経験がほとんどない、または社内にそのノウハウやスキルがまだ十分ではない状況では、話が変わってきます。
いきなり見込み度の高いお客様候補だけを狙って、非常に専門的なホワイトペーパーを作った場合、ダウンロードしてくれる人数がとても少なくなる可能性があり、ダウンロード数が少ないと以下のような問題も出てきます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| データがたまらず改善しにくい | ダウンロード数が少なすぎると、「どんな人がダウンロードしたのか」「どの部分に興味を持ったのか」データがなかなか集まりません。データがなければ、何が悪くて何が良いのか、どう改善すればもっと効果が出るのか(PDCAサイクルを回すと言います)が分かりにくくなってしまいます。 |
| 社内からの評価が得にくい | せっかく時間や費用をかけてホワイトペーパーを作ったのに、ダウンロード数がずっと少ないままだと、「成果が出ていないじゃないか」と社内から見なされてしまうかもしれません。そうなると、次にホワイトペーパーを作るための予算が下りなくなってしまう、なんてことにもなりかねません。 |
このような状況を考えると、一見遠回りに思えるような戦略が、実は非効率ではなく効率的な成果獲得へつながることがあります。
もしホワイトペーパーマーケティングの経験がまだ少ないのであれば、まずは「幅広い層の読者にとって役立つ、基礎的なノウハウ系のテーマ(潜在層向けのテーマ)」から始めてみるのがおすすめです。
セオリー通りに進めないメリット
BtoBマーケティングのセオリーである、見込みの高いお客様を狙っていく戦略ではなく、その逆をすることのメリットはいくつかあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| たくさんのデータを集められる | ノウハウ系のホワイトペーパーは、比較的多くの人にダウンロードしてもらいやすい傾向があります。これにより、まずはお客様候補の興味や関心に関する「生きたデータ」をたくさん集めることができます。どんな情報が人気なのか、どんな言葉に響くのか、具体的な肌感覚として掴めるようになります。 |
| 改善の経験を積める | ある程度のダウンロード数が見込めるので、例えば「タイトルを変えてみる」「ダウンロードページのデザインを変えてみる」色々な試みをしやすいです。これらの試行錯誤を通じて、「どうすればもっとダウンロードしてもらえるか」「どうすればもっと読んでもらえるか」、ホワイトペーパー運用の実践的なノウハウやスキルを、着実にチーム内へ蓄積していくことができます。 |
| 社内での理解と協力が得やすい | 目に見えるダウンロード数(成果)を出すことで、「ホワイトペーパーって効果があるんだね」と社内の他の部署の人たちにも理解してもらいやすくなります。 |
これが、今後の予算獲得や、より高度なマーケティング施策への挑戦を後押ししてくれるので、会社の「経験値」や「今の状況」をしっかりと見極めて、それに合わせたテーマを選ぶことが、実は成功への近道になるのです。
最終的に目指す場所は同じでも、そこへたどり着くまでのルートは「会社によって柔軟に変えるべきだ」と覚えて頂くのがおすすめです。
目的達成に導くホワイトペーパーのテーマ選定3ステップ
実際にホワイトペーパーのテーマを選ぶ具体的な3つのステップを見ていきましょう。
このステップを踏めば、テーマ選びで迷うことはグッと減るはずです。
STEP1:徹底的な「状況把握」
ホワイトペーパーのテーマを考える前に、まずは自社の状況をよーく見てみることが大切です。
ここでの「状況把握」とは、目的に合ったホワイトペーパーを作るための「土台」となり、土台がしっかりしていないと、どんなに良いアイデアも、残念ながら空回りしてしまう可能性があります。
具体的に、次のようなことをじっくり考えてみましょう。
今の会社や事業はどんな段階にいますか?
- 会社の名前や事業は世の中にどのくらい知られていますか?(認知度)
- 市場の中であなたの会社はどんな立ち位置にいますか?(競争力)
- 会社や事業として解決したい課題は何ですか?(例:新規・既存どちらを増やす?)
マーケティング活動の現状はどうですか?
- 制作に使える予算や時間や担当できる人はどのくらいいますか?(リソース)
- どのような方法でリードを集めていますか?(リード獲得の成果や現状)
- 社内で制作したり運用したりする経験はどのくらいありますか?(経験値)
- もし経験が少ないならデータを分析したり改善策を考えたりするスキルは十分ですか?
最終的に達成したいビジネスの目的は何ですか?
- このホワイトペーパーを通じて最終的に売上をどれくらい増やしたいですか?
- 特定の商品の導入数をどれくらい増やしたいですか?
- 商談につながるお客様候補を何人獲得したいですか?
どんなお客様候補の方へ届けたいですか?
- その人はどんな仕事をして何の役職の人ですか?(具体的なターゲット像)
- どんな業界の人ですか?
- どんなことに困っていて何の課題を解決したいと思っていますか?
- 情報を集める時、どんな風に調べていますか?(情報収集の行動)
STEP2:目的に合わせた「テーマの種類」を選ぼう
STEP1で会社の状況や目的、ターゲットをしっかり把握できたら、次はいよいよ「どんな種類のテーマにするか」を具体的に考えていきます。
ホワイトペーパーにはいくつかの「型(タイプ)」があり、お客様が情報を集めている段階によって、響くテーマの型が変わってくるんです。
また、テーマの種類を見る前に、頭の柔軟性を高めると、さらにアイデアが出てくるようになるので、その方法も含めて見ていきましょう。
テーマを選ぶ前の準備
ホワイトペーパーのテーマには、ある程度の「型(種類)」が存在し、インターネット検索や生成AIによって情報が溢れる現代では、一般的で無難なテーマは既に多くの場所で探せます。(自然と目にも入ってくる)
こうしたテーマは、どうしてもお客様の興味を引きにくく、伝えたいメッセージも埋もれてしまいがちです。
既存のファン層にとっては信頼性からダウンロードされる可能性もありますが、新しい層へ響かせるためには、より専門性や独自性を際立たせることが効果的です。
そのため、テーマ選定においては、可能な限り既成概念にとらわれず、まずは自由な発想で可能性を探求する機会を持つことが、とても重要になります。
STEP1:自由な発想でアイデアを広げる
最初のステップは、あらゆる制約を取り払い、可能な限り多くのアイデアを自由にリストアップすることです。
普段の業務の延長線上で考えたり、事前の情報収集が不十分なまま考え始めたりすると、発想が限定され、どうしても無難なテーマに落ち着きやすくなります。
もちろん、十分に検討した結果として普遍的なテーマを選ぶのは問題ありません。
しかし、最初から可能性を狭めてしまうと、もっと効果的なテーマを見落とす可能性があります。
斬新すぎる必要はありませんが、まずは「こんな情報があったら面白いかもしれない」「こんな課題解決に役立つかもしれない」など、幅広い可能性を含んだアイデアを出すことから始めましょう。
アイデア出しの具体的な方法としては、以下のようなアプローチが有効です。
| アイデア出し | 説明 |
|---|---|
| 自社の強みを深掘りする | 競合にはない独自の知見や経験、技術は何か? |
| 社内へのヒアリング | 営業、開発、サポートなど、各部門が顧客からよく聞く課題や質問、成功事例は何か? |
| 個人の経験や知識の棚卸し | 担当者が過去に経験した成功・失敗談、学んだノウハウなどをマインドマップなどで整理する。 |
| 複数人でのブレインストーミング | 異なる視点を持つメンバーで自由に意見を出し合う。 |
| 他社の成功事例の分析 | 競合や他業界のホワイトペーパーから、なぜそれがダウンロードされているのか、成功要素を抽出する。 |
| コンテンツマトリクスを活用 | 顧客の購買フェーズと関心軸から、提供すべきコンテンツのタイプを構造的に考える。 |
他社で既にダウンロードされているホワイトペーパーのテーマを参考にするのも一つの手段ですが、それはあくまで最終的な調整段階に留め、まずは自社ならではのユニークな価値を見出すことに注力しましょう。
この段階で最も重要な注意点は、「アイデアを否定しない」こと。
実現可能性や難易度、ターゲットへの適合性は次のステップで判断します。
まずは質より量を重視し、アイデア出しの妨げになる要因を取り除くことが肝心です。
STEP2:目的と顧客視点でアイデアを絞り込む
様々な角度からアイデアを出し終えたら、次にそれらを今回制作するホワイトペーパーの目的に照らし合わせながら絞り込んでいきます。
この絞り込みの過程で、最も強く念頭に置くべきことがあります。
それは、ホワイトペーパーが「誰のための」ものであるか。
ホワイトペーパーは企業のマーケティング活動の一環として作成されるため、「会社のため」に作る意識が先行しがちです。
しかし、もし最終的な目的が「売上創出」にあるならば、その達成のためにはまず「お客様のため」になるホワイトペーパーである認識を持つことが不可欠です。
なぜなら、お客様の課題解決や満足度の先にこそ、自社の目的達成があるからです。
中間目標が「リード獲得」であっても、最終目標が「売上創出」である以上、お客様の期待に応えられないホワイトペーパーでは、一時的にダウンロードされてもその後の商談や契約には繋がりません。
(避けるべきシナリオ)興味 → ダウンロード → 期待外れ…
(目指すべきシナリオ)興味 → ダウンロード → 信頼獲得 → 商談 → 契約
お客様がダウンロードした資料を見て、どのように感じ、どのような行動を取るのか、これが全てを決定します。
したがって、絞り込みの段階では、自社の強みや専門性を最大限に活かしつつ、最もお客様の満足度を高め、信頼獲得に繋がる可能性のあるテーマを、アイデアリストの中から抽出することを意識します。
この「お客様のため」思考で考えれば、選定されるアイデアは大きく変わってくるはず。
この視点を常に忘れずに、絞り込みを進めましょう。
STEP3:選定したテーマを具体的に落とし込む
いくつかの有望なアイデアに絞り込めたら、いよいよそれらを具体的なホワイトペーパーの「テーマ」として形にするステップです。
何の課題や情報に焦点を当て、どのような切り口でコンテンツを構成していくか、制作全体の指針を明確にしていきます。
具体化の際に重要なポイントは3つ。
① 誰に向けて情報を届けたいのか(具体的なターゲット像)
ターゲットの役職、業界、抱える課題などをさらに明確にします。
② 自社の強みや専門性をどのように含めるか
そのテーマにおいて、自社が提供できる独自の価値や知見は何かを明確にします。
③ そのテーマで目的達成にどのように近づけるか
このテーマが、リード獲得やナーチャリングやマーケティング目標にどう貢献するのかを具体的に考えます。
テーマを具体化し、関係者間で共通認識を持つためには、テーマを構造的に捉えるのが有効です。
そして、以下の三層構造で考えると、ブレなくメッセージを伝えることができます。
| テーマ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 大テーマ | ホワイトペーパーが扱う情報の大まかな方向性や分野。 | マーケティング |
| 中テーマ | 大テーマの中で、特に焦点を当てる課題やターゲット。 | 中小企業のマーケティング戦略 |
| 小テーマ | 中テーマをさらに具体化し、ホワイトペーパーの核心となる価値や切り口。 | BtoBビジネスにおけるリード獲得のためのマーケティング戦略 |
この三層構造と、そこから導き出される「最も伝えたいメッセージ」(例: ホワイトペーパーはBtoBのリード獲得に有効な手段である)を明確に可視化しておくことで、制作過程でのブレを防ぎ、出来上がったホワイトペーパーがお客様のニーズとズレることなく、一貫性のあるメッセージを届けられるようになります。
テーマの種類と選び方
ポイントはSTEP1で把握した「自社の状況」と「達成したい目的」、そして「お客様候補が今どんな情報を求めているか」を考えながら、最も効果的なテーマの種類を選ぶこと。
特に、ホワイトペーパーの運用経験がまだ少ない場合は、まずは「ノウハウ型」のような、比較的ダウンロードされやすいテーマから始めて、少しずつ経験を積んでいくこともおすすめで、これが最終的な目的達成への効率的な遠回りになることもあります。
ノウハウ型(潜在層向け)
ノウハウ型とは、あなたの会社が長年培ってきた経験や独自の知識、技術に基づいた、お客様のビジネス上の課題解決に役立つ情報を提供するタイプです。(例:「〇〇を効率化する10のコツ」や「失敗しないためのチェックリスト」のような内容)
特定の業界や業務における実践的な基礎知識から、現場での試行錯誤から生まれた独自のテクニックまで、その内容は多岐にわたります。
まだ自分の課題をはっきりと認識していない人や、課題はあるけど、どうすればいいか分からないという人に、問題提起をしたり、新しい知識を与えたりすることで、興味を持ってもらい、ダウンロードにつながりやすいのが特徴で、比較的幅広い層にアプローチできます。
こんな目的に合うテーマがノウハウ型
- 会社の認知度を高めたい。
- 幅広いお客様候補を集めたい。
- ホワイトペーパーの運用経験がまだ少ないので、まずはたくさんのダウンロードデータを集め、ノウハウを蓄積したい。
- お客様に「この会社は詳しいな」「役に立つ情報を提供してくれるな」と思ってもらい、信頼関係の第一歩を築きたい。
| 主な種類例 | 説明 |
|---|---|
| ノウハウ(簡易) | 特定の課題に対する基本的な解決策や、短時間で学べる実践知識。(例:10~20ページほど) |
| ノウハウ(詳細) | 特定テーマに関する深い専門知識や、具体的な実践ステップ、応用方法など。(例:20ページ以上~) |
| 基礎知識 | 特定の業界、技術、手法などに関する入門レベルの解説。 |
| マニュアル | 特定のツール、製品、プロセスなどの具体的な利用手順や操作方法。 |
| ガイドブック | 特定の目的達成に向けた、体系的で包括的な手引き。 |
| チェックリスト | 特定の作業や状況において、確認すべき項目をまとめたリスト。 |
| 手順 | 特定のタスクやプロセスを完了させるためのステップ説明。 |
| テンプレート | 業務で使用できる企画書、レポート、計算シートなどのひな形。 |
| 技術紹介 | 自社が持つ独自の技術や、専門分野の技術要素に関する詳細解説。 |
| 比較 | 複数の製品、サービス、手法などを特定の観点から比較検討したもの。 |
調査レポート型
あなたの会社が独自に集めて分析したデータや、業界全体の最新の動き、市場のトレンドなどをまとめたタイプです。
客観的なデータに基づいて話すので、情報の信頼性や説得力が非常に高まります。
特に、他の会社では手に入らないような独自の顧客データやアンケート調査の結果など、非常に価値が高く、お客様に「この会社は専門家だ」と強く印象付けることができます。
こんな目的に合うテーマが調査レポート型
- 市場における会社の専門家としての地位を確立したい。
- お客様に新しい市場の動きや課題を認識させたい。
- 他社との差別化を図りたい。
| 主な種類例 | 説明 |
|---|---|
| 業界トレンド | 特定業界の最新動向、市場規模、将来予測などの分析レポート。 |
| アンケート調査 | 特定のターゲット層へのアンケート結果とその分析・考察。 |
| ランキング | 特定の基準に基づいた製品、サービス、企業の順位付け情報。 |
| 口コミ(レビュー) | 顧客からの評価や感想を収集・分析し、傾向などをまとめたもの。 |
| 研究 | 特定の技術や分野に関する独自の学術的な調査・実験結果。 |
製品・サービス型(顕在層向け)
あなたの会社の製品やサービスについて、具体的な情報を詳しく紹介するタイプです。
この資料をダウンロードするお客様は、すでに何らかの課題を抱えていて、その解決策としてあなたの会社の製品やサービスにかなり興味を持っている可能性が高いです。
そのため、適切な情報を提供できれば、すぐに次の検討ステップ(例えば、営業担当者との商談など)へと進みやすいお客様候補になります。
こんな目的に合うテーマが製品・サービス型
- 製品やサービスの具体的な検討を促したい。
- 商談につながるお客様候補を直接獲得したい。
- 導入を検討しているお客様の疑問を解消したい。
| 主な種類例 | 説明 |
|---|---|
| 製品・サービス資料 | 自社の製品やサービスの概要、特徴、導入メリットなどを紹介。 |
| カタログ | 製品ラインナップ、モデル、仕様などを一覧でまとめたもの。 |
| スペック | 製品やサービスの詳細な技術仕様、性能、動作環境データなど。 |
| 価格表 | 製品やサービスの料金プラン、オプション、費用体系など。 |
事例型(顕在層向け)
あなたの会社の製品やサービスを実際に導入・利用したお客様の、具体的な成功事例や活用方法を紹介するタイプです。
実際のお客様の声や、導入後にどれくらいの成果が出たか具体的なデータが入るので、製品・サービスの信頼性や有効性を非常に説得力高く伝えられます。
制作には時間と手間がかかりますが、「事実」に基づいているため、独自性が非常に高く、ダウンロードされやすいテーマの一つです。
こんな目的に合うテーマが事例型
- 製品・サービスの信頼性を高め、導入への不安を解消したい。
- 成約に近い、具体的な検討段階のお客様候補を獲得したい。
- 特定の業界や課題を持つお客様に、自分ごととして考えてもらいたい。
| 主な種類例 | 説明 |
|---|---|
| 導入事例 | 製品やサービスを導入した顧客の背景、導入プロセス、得られた成果。 |
| 成功事例 | 特定の課題解決や目標達成に成功した顧客の取り組み詳細。 |
| 失敗事例 | 失敗から学んだ教訓や改善策、リスク回避策などを共有。 |
| 活用事例 | 製品やサービスの多様な利用方法や、特定の機能の活用例。 |
| シミュレーション | 製品やサービスの導入効果などを数値で試算し提示するもの。 |
その他
これまでの型には当てはまらないけれど、お客様の興味を引きつけ、ダウンロードにつながるユニークなテーマもあります。
例えば、会社の内部で行われている独自の取り組みを紹介したり、普段は外部に出さないような情報を見せたりすると、お客様の関心を強く引きつけやすい傾向があります。
| 主な種類例 | 説明 |
|---|---|
| クイズ | 特定分野の知識を楽しみながら学べるインタラクティブなコンテンツ。 |
| 企業の裏側 | 普段公開されない開発プロセス、組織文化、プロジェクト舞台裏など。 |
STEP3:選んだテーマを具体的に掘り下げよう
いくつかの有望なテーマの種類を選んだら、いよいよそれを具体的なホワイトペーパーの「テーマ」として形にする最終ステップです。
ここで、どんな課題や情報に焦点を当て、どのような切り口でコンテンツを構成していくのか、制作全体の方向性をはっきりと決めていきます。
具体的に考えるべきポイントは3つあります。
誰に向けて情報を届けたいのか(具体的なターゲット像をもう一度確認)
選んだテーマは、どんな役職の、どんな業界の人に、どんな課題を抱える人に一番響くでしょうか? その人の顔を思い浮かべながら、より具体的な言葉でターゲット像を明確にしましょう。
貴社の強みや専門性をどう組み込みますか?
そのテーマにおいて、あなたの会社だけが提供できる独自の価値や深い知識は何でしょうか? 他の会社にはない、あなただけの視点や解決策を明確にすることで、ホワイトペーパーの価値がぐっと高まります。
そのテーマで、どんな目的を達成しますか?
このホワイトペーパーがダウンロードされることで、リード獲得やお客様を育てる(ナーチャリング)やマーケティング目標にどう貢献するのかを、具体的にイメージしてみましょう。ダウンロードされた後、お客様にどんな行動を促したいのかまで考えることが重要です。
最後に
ホワイトペーパーは、単に一度作って終わり、という「資料」ではありません。
お客様との関係を築き、会社のビジネスを成長させていくための、非常に重要な「資産」です。
この資産を最大限に活かすため、今回お伝えしたように、単なる「ネタ探し」ではなく、「何のために作るのか(目的)」「今の会社の状況はどうか」「どんなお客様に届けたいのか」、そして「これまでの経験値」という本質的な要素を深く、じっくり考えてテーマを選ぶことが不可欠です。
適切なステップを踏んでテーマを決めれば、もう「何を作ればいいか分からない」と迷うことはなくなるはず。
そして、その一つ一つのホワイトペーパーが、あなたのビジネスに確かな成果をもたらす力強い味方になってくれます。