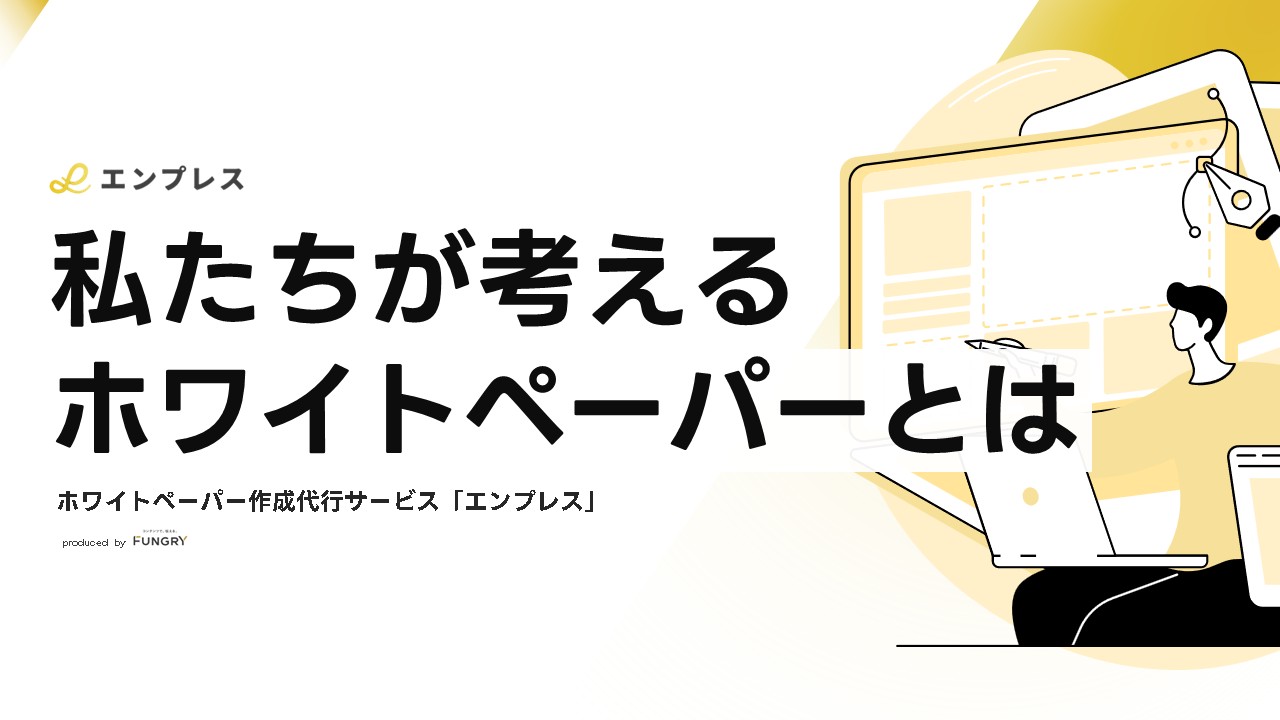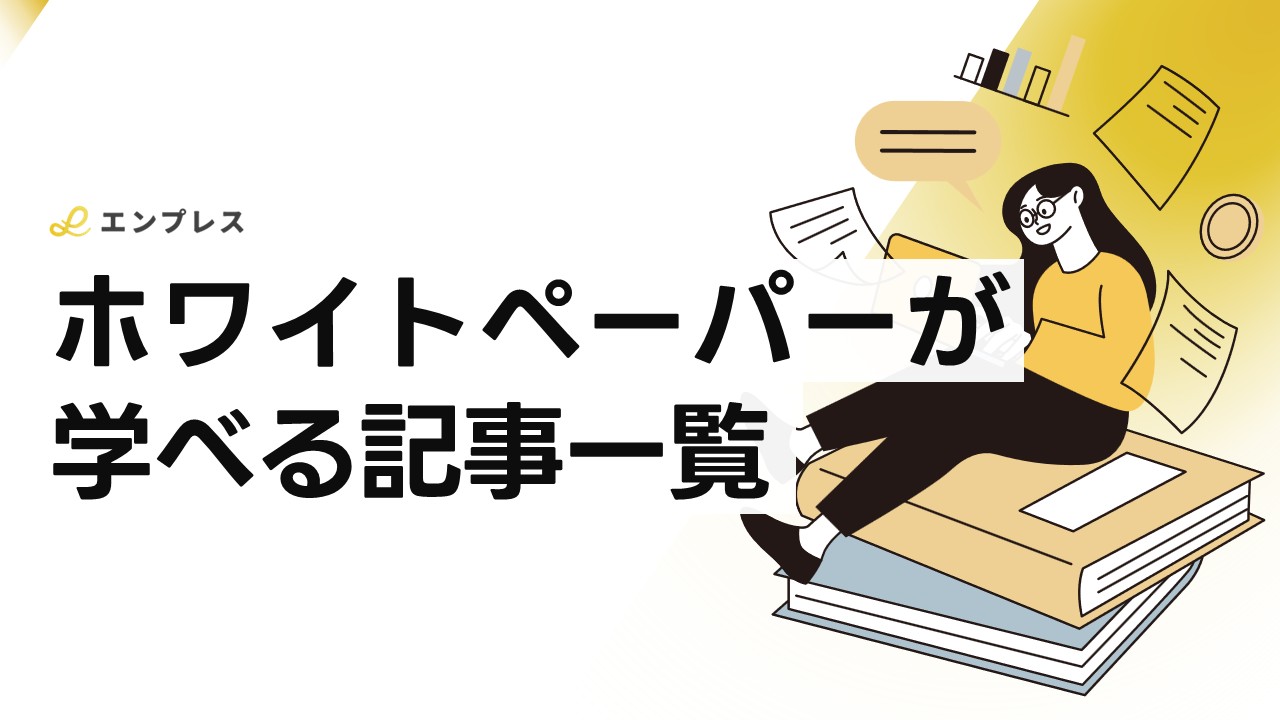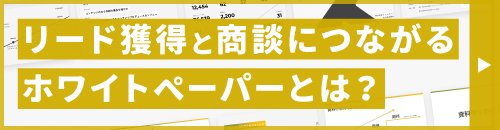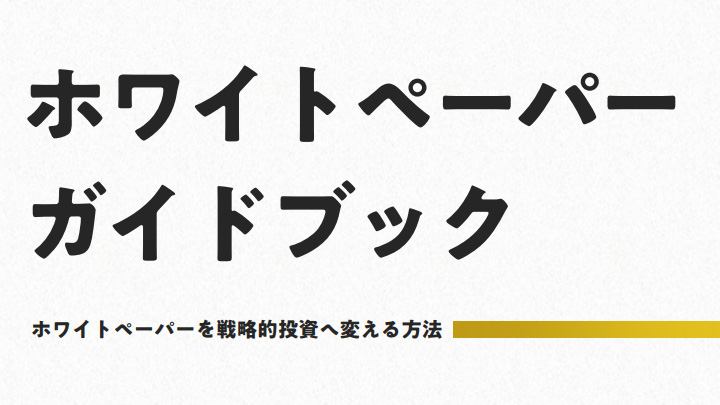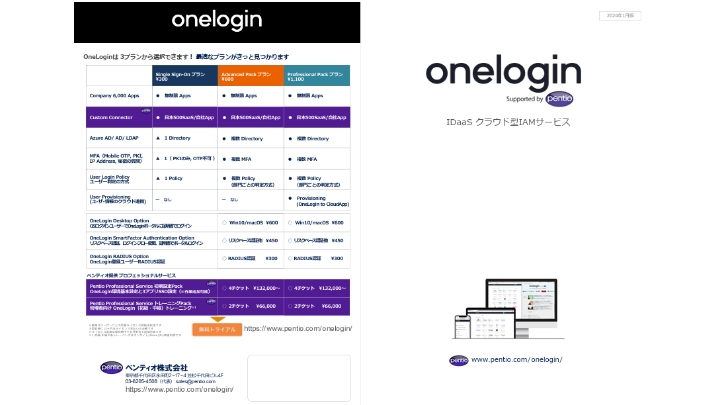いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。失敗を取り戻すのと、最初から予防して発生させないようにするのでは、かかる時間に大きな差があります。
ホワイトペーパーの作成は、単一の要因で失敗するのではなく、複数の問題が複雑に絡み合っている場合が少なくありません。
そのため「〇〇をすれば良い」「△△をやっておけば大丈夫」など表面的な対策だけでは不十分。
ホワイトペーパーの企画・制作から活用に至る一連のプロセス全体を通して、各段階に潜む課題を深く理解する必要があるため、この記事ではホワイトペーパー作成における代表的な5つの問題を抽出し、それぞれの詳細な解説と具体的な改善策も解説していきます。
これらの問題を事前に認識し対策を講じることで、せっかく時間と労力をかけたホワイトペーパーが無駄に終わるリスクを減らし、より効果的な成果へと繋げることができます。
- 目次
- ① 社内の足並みが揃わない問題
- ② オウンドメディアのポテンシャルを活かせない問題
- ③ ホワイトペーパー自体の魅力不足
- ④ 獲得したいリード像とのミスマッチ
- ⑤ ホワイトペーパーの効果的な活用戦略の欠如
- 最後に
① 社内の足並みが揃わない問題
ホワイトペーパーの成否は、制作段階以前の社内状況に大きく左右されます。
この点を軽視すると、的外れな原因究明に時間を費やしたり、本質的ではない表面的な修正にばかり注力してしまう可能性も。
根深い社内問題を事前に洗い出し、対策を講じることが重要です。
問題1 社内理解と協力体制の欠如
ホワイトペーパーはマーケティング活動の重要な一環であり、最終的には売上にも大きく貢献する可能性があります。
しかし、その効果が顕在化するまでには時間を要することが多く、「資料」というイメージから経営層にはその価値が理解されにくいことがあります。「簡単に作れるだろう」といった認識を持たれ、十分な予算や協力を得られないケースも少なくありません。
このような状況下では、現場担当者が孤立し、十分なリソースがない中で制作を進めざるを得なくなり、結果として質の低いホワイトペーパーしか作成できず、さらなる社内からの期待低下を招くという悪循環に陥ることがあります。
改善策
目的と効果の明確化
ホワイトペーパーの目的(リード獲得数、商談数、顧客育成など)と、それが会社の売上にどのように貢献するのかを具体的なデータや事例を用いて経営層に説明し、共通認識を持つことが不可欠です。
関係部署との連携強化
マーケティング部門だけでなく、営業部門や広報部門など、関連部署との連携を密にし、それぞれの視点やニーズを反映させることで、より実用的なホワイトペーパーを作成できます。
成功事例の共有
過去の成功事例や、他社のホワイトペーパー活用事例などを共有することで、社内全体の理解とモチベーションを高めることができます。
問題2 顧客理解の深度不足
質の高いホワイトペーパーを作成するためには、ターゲット顧客の深い理解が不可欠です。「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを明確にする必要があります。
しかし、自社の製品やサービスを熟知しているが故に、顧客像を固定的に捉えてしまいがちです。
市場環境、競合の動向、顧客ニーズは常に変化しているため、過去の成功体験や思い込みに基づいて「これが求められているだろう」と制作したホワイトペーパーは、顧客のニーズと乖離し、結果として誰にも読まれない可能性があります。
改善策
徹底的な顧客分析
顧客データ(アンケート、インタビュー、購買履歴、行動ログなど)を多角的に分析し、顧客の属性、課題、ニーズ、購買プロセスなどを詳細に把握します。
ペルソナ設定
顧客分析に基づき、具体的な顧客像(ペルソナ)を設定し、チーム全体で共有することで、ターゲット顧客への共感を深め、より顧客視点に立ったコンテンツ作成が可能になります。
カスタマージャーニーマップの作成
顧客が製品やサービスを認知し、購入に至るまでのプロセスを可視化し、各タッチポイントにおける顧客の心理や行動を理解することで、最適なコンテンツを提供できます。
問題3 兼業による制作チームのパフォーマンス低下
ホワイトペーパーの制作を内製する場合、既存の社員が兼務で担当することが一般的です。
社内メンバーで構成されたチームは、コミュニケーションが取りやすいというメリットがある一方、各メンバーが本業の合間に制作を行うため、十分な時間を確保できなかったり、本業の繁忙によってスケジュールが遅延したり、最悪の場合、担当者がフェードアウトしてしまうこともあります。
兼業によるリソース不足は、ホワイトペーパーの品質低下を招き、結果として期待される効果が得られないという悪循環に繋がる可能性があります。
改善策
専任チームの組成
可能であれば、ホワイトペーパー制作に専念できるチームを組成することが理想的です。
明確な役割分担と責任者の配置
制作に関わる各メンバーの役割と責任を明確にし、進捗管理を行う責任者を配置することで、プロジェクトの遅延を防ぎます。
外部リソースの活用
ライティング、デザイン、ディレクションなど、専門スキルが必要な部分については、外部の専門家や制作会社に委託することも有効な手段です。
問題4 内製におけるスキル不足
ホワイトペーパーを内製する場合、一般的に「ディレクション」「ライティング」「デザイン」の3つの基本的なスキルが求められます。
これらのスキルを一人で全て持ち合わせている人材は稀であり、複数の担当者で役割分担を行うことが一般的です。
しかし、ホワイトペーパー制作の経験が少ない担当者が集まった場合、基本的な知識やノウハウが不足していたり、制作することに注力するあまり、その後の活用方法まで意識が向かないことも。
専門的なスキル不足は、ホワイトペーパーの品質を低下させ、最終的な失敗に繋がる可能性があります。
改善策
研修やセミナーの実施
社内担当者向けに、ホワイトペーパー制作に関する研修やセミナーを実施し、必要な知識やスキルを習得する機会を提供します。
外部専門家からのアドバイス
ホワイトペーパー制作の経験豊富な外部コンサルタントや制作会社からアドバイスや指導を受けることで、制作の質を高めることができます。
テンプレートやツールの活用
ホワイトペーパーの構成やデザインに関するテンプレートやツールを活用することで、効率的に高品質なホワイトペーパーを作成できます。
問題5 外注先の選定とコントロールの失敗
内製が難しい場合や、専門的なスキルを外部に求める場合は、制作代行を検討することになります。
しかし、資料制作代行会社は多数存在するため、自社の目的や予算に合った最適な外注先を選定することは容易ではありません。
また、選定に時間をかけたとしても、実際に期待通りのホワイトペーパーが納品されるとは限りません。
制作中は代行業者主導で進むことが多く、自社の細かな要望が伝わりにくかったり、完成したものが一般的な資料と変わらないクオリティである可能性も。
外注先の選定を誤ったり、その後のコントロールが不十分な場合、期待した効果を得られないことがあります。
改善策
明確な選定基準の設定
外注先の選定にあたっては、実績、専門性、コミュニケーション能力、費用などを明確な基準に基づいて比較検討します。
複数社からの見積もりと提案の比較
複数の制作会社から見積もりを取り、提案内容を詳細に比較検討することで、自社のニーズに最も適したパートナーを見つけることができます。
密なコミュニケーションと進捗管理
制作期間中は、定期的な打ち合わせや進捗報告を求め、密なコミュニケーションを図ることで、認識のずれを防ぎ、品質を確保します。
契約内容の明確化
成果物の定義、修正範囲、納期、費用などを明確に記載した契約書を作成し、双方の認識を一致させておくことが重要です。
② オウンドメディアのポテンシャルを活かせない問題
ホワイトペーパーは、通常、自社が保有するウェブサイト(オウンドメディア)を通じて提供されます。
資料ダウンロード用の入力フォームを設置し、顧客に情報を提供するという形式が一般的。
そのため、オウンドメディアの運用状況が、ホワイトペーパーの成果に大きな影響を与えるため、事前にその問題点を把握しておく必要があります。
問題1:集客力の低さ
どんなに魅力的で質の高いホワイトペーパーを作成しても、それをダウンロードしてくれるユーザーがいなければ意味がありません。
ホワイトペーパーがダウンロードされない原因は、その内容自体ではなく、ホワイトペーパーにたどり着く前の段階、つまりオウンドメディアへの集客力が不足しているケースが非常に多いです。
SEO対策が不十分で検索エンジンのランキングが低迷していたり、ブログ記事などのコンテンツマーケティングが機能しておらず、ウェブサイトへのアクセス数が伸び悩んでいる場合、ホワイトペーパーの存在は潜在顧客に認知されません。
広告運用は即効性がありますが、予算に左右されるため、持続的な集客には繋がらない。
オウンドメディアへの集客力強化は、ホワイトペーパーで成果を出すための重要な前提条件です。
改善策
SEO対策の強化
ターゲットキーワードに基づいたコンテンツ作成、内部リンクの最適化、被リンク獲得など、SEO対策を徹底的に行うことで、検索エンジンからの自然流入を増やします。
コンテンツマーケティングの推進
顧客の課題やニーズに合わせた質の高いブログ記事、事例紹介、動画コンテンツなどを継続的に発信し、ウェブサイトへのエンゲージメントを高めます。
SNSの活用
ターゲット顧客層に合ったSNSプラットフォームを活用し、コンテンツの拡散やコミュニケーションを図ることで、ウェブサイトへの誘導を促進します。
問題2 ホワイトペーパーへの導線の不備
オウンドメディアにアクセスしたユーザーが、必ずしも最初からホワイトペーパーを探しているとは限りません。
多くの場合、特定の情報を求めてウェブサイトを訪れており、ホワイトペーパーの存在自体を知らない可能性があります。
ウェブサイト内にホワイトペーパーへの導線が適切に設計されていない場合、せっかくアクセスしたユーザーも、目的の情報だけを見てすぐに離脱してしまい、ホワイトペーパーのダウンロードに繋がりません。
ホワイトペーパーの存在を認知させ、興味を持ってもらうための導線設計が重要です。
改善策
目立つ場所への導線設置
ウェブサイトのトップページ、サイドバー、記事コンテンツ内など、ユーザーの目に触れやすい場所にホワイトペーパーへの導線を設置します。バナー、CTAボタン、テキストリンクなどを効果的に活用します。
関連コンテンツからの誘導
ブログ記事や事例紹介など、関連性の高いコンテンツからホワイトペーパーへのリンクを設置することで、興味を持ったユーザーをスムーズに誘導できます。
ポップアップやスライドインCTAの活用
ユーザーの行動に合わせて、ポップアップやスライドイン形式でホワイトペーパーを紹介するCTAを表示することで、注意を引きつけ、ダウンロードを促します。
問題3 入手前の情報との不整合
ユーザーがどのような経路でホワイトペーパーにたどり着いたのかを把握し、その情報とホワイトペーパーの内容に一貫性を持たせることは、期待感を維持し、ダウンロード率を高めるために非常に重要です。
例えば、クリックしたバナーに「資料作成が楽になる」と書かれていたにも関わらず、ホワイトペーパーの表紙が「資料デザインのアイデア100選」だった場合、ユーザーは期待していた情報と異なると感じ、離脱してしまう可能性が高まります。
一方、表紙が「資料作成が楽になるテンプレート配布」であれば、バナーからホワイトペーパーへの流れに一貫性があり、ダウンロード意欲を維持できます。
改善策
流入経路の分析
どのチャネルからユーザーがウェブサイトに流入し、どのコンテンツを経由してホワイトペーパーにたどり着いたのかを分析します。
メッセージの一貫性
各流入経路で訴求するメッセージと、ホワイトペーパーのタイトルや概要、表紙のデザインなどを一致させることで、ユーザーの期待感を損なわないようにします。
ランディングページの最適化
ホワイトペーパーのダウンロードページ(ランディングページ)では、ホワイトペーパーの内容、得られるメリット、ターゲット読者などを明確に伝え、コンバージョン率を高めます。
③ ホワイトペーパー自体の魅力不足
ホワイトペーパーの失敗原因として最も多いのは、その制作過程における問題です。
作成中は気づきにくいものの、完成後に効果が出ないことで問題が顕在化することも。
チェックリストやノウハウを活用して制作すれば別ですが、慣れていないと作成作業に追われ、細かい部分の確認や配慮が不足しがちです。
問題1 表紙の訴求力不足
資料ダウンロードという形式の場合、最初にユーザーの目に触れる表紙の魅力が、ダウンロードされるかどうかを大きく左右します。
ユーザーにとって魅力的な表紙とは、「自分ごと」として捉えられ、「さらに詳しく知りたい」と思わせるものです。つまり、期待感を持たせられるかどうかが重要になります。
オウンドメディア内にホワイトペーパーのサムネイルだけを設置した場合、一瞬見ただけで自分に関係がないと思われてしまえば、クリックすらされず、ダウンロードには繋がりません。
ホワイトペーパーの表紙の情報とデザインの質を高めることが、成果を大きく左右します。
改善策
ターゲット顧客への明確な訴求
表紙には、ターゲット顧客が抱える課題やニーズを明確に示し、「これは自分のための情報だ」と感じてもらえるように工夫します。
具体的なメリットの提示
ホワイトペーパーを読むことで得られる具体的なメリットを簡潔に伝え、ダウンロードする動機付けを行います。
魅力的なデザイン
ターゲット顧客層に合ったデザインを採用し、視覚的に訴求力の高い表紙を作成します。専門デザイナーに依頼することも有効な手段です。
目を引くタイトルの設計
タイトルは、内容を的確に表しつつ、ユーザーの興味を引くように工夫します。具体的な数字やキーワードを入れる、疑問形にするなどのテクニックも有効です。
参考:【最優先】ホワイトペーパーはタイトルの付け方で決まる
参考:パワポの表紙デザイン100パターン(ファイルDL可)
問題2 顧客が求める価値との乖離
ホワイトペーパーの作成には労力がかかり、情報量が多いほど提供できる価値も高まると考えがちです。
しかし、顧客は必ずしも多くの情報を求めているわけではありません。むしろ、短時間で要点を把握できる、分かりやすく整理された情報を求めている場合があります。
企業側が提供したい価値と、顧客が実際に求めている価値にズレがあると、情報の詰め込みすぎによって表現が無難になり、顧客にとって「自分ごと」として捉えにくい内容になってしまうことがあります。
ターゲットと情報を絞り込むことで、万人受けではなく、本当に必要としている顧客に響くホワイトペーパーを作成できます。
改善策
ターゲット顧客のニーズに合わせた情報設計
顧客分析に基づいて、ターゲット顧客が本当に必要としている情報、課題解決に役立つ情報に焦点を当てて構成します。
情報の整理と構造化
情報を論理的に整理し、見出しや箇条書きなどを活用して構造化することで、顧客が短時間で内容を理解できるように工夫します。
簡潔で分かりやすい表現
専門用語を避け、平易な言葉で分かりやすく説明することを心がけます。図やグラフなどを効果的に活用することも有効です。
顧客視点の徹底
常に「顧客にとって価値があるか」という視点に立ち、内容を精査します。
問題3 メンテナンス性を考慮しない制作
デザインにこだわり、インパクトのあるホワイトペーパーを作成したり、スライドごとに多様な装飾を施すことは、見た目の魅力を高める一方で、メンテナンス性を著しく低下させる可能性があります。
一度作成して終わりではなく、情報の更新やアップデートが必要になった場合、複雑なデザインは修正作業を困難にし、担当者が限定されてしまうことで、活用のスピードを遅らせてしまいます。
また、他のテーマでホワイトペーパーを作成しようとした際に、デザインを流用しにくいため、費用対効果の低いものになってしまう可能性があります。
改善策
汎用性の高いデザインの採用
将来的な更新や流用を考慮し、シンプルで汎用性の高いデザインを採用します。
テンプレートの活用
デザインの統一性を保ち、効率的な制作とメンテナンスを実現するために、社内テンプレートを作成し活用します。
デザインガイドラインの策定
フォント、カラー、レイアウトなどのデザインルールを明確に定めることで、誰が修正しても品質を維持できるようにします。
編集可能なデータ形式での保存
制作データは、後々の編集が容易な形式で保存・管理します。
問題4 自社の専門性を活かせないテーマ選定
BtoC、BtoBを問わず、顧客は困った時に、自分よりもスキル・経験・知識のある専門家を頼りたいと考えます。
ホワイトペーパーで自社の専門性を効果的に表現するには、会社のブランドとテーマを連動させる必要があります。
例えば、資料作成を専門とする会社がホワイトペーパーを作成する場合、「ランディングページで成功する3つのポイント」というテーマよりも、「ホワイトペーパーでやってはいけない10個のこと」というテーマの方が、自社の専門性をより明確に打ち出すことができ、顧客からの信頼を得やすくなります。
自社の強みや専門性を活かしたテーマを選定することで、ホワイトペーパーの魅力を高め、ブランドイメージの向上にも繋がります。
改善策
自社の強みと専門性の明確化
自社がどのような分野で専門性を持っているのか、競合他社と比較してどのような強みがあるのかを明確に定義します。
ブランドイメージとの整合性
ホワイトペーパーのテーマや内容は、自社のブランドイメージと一貫性を持たせるようにします。
顧客の課題と自社の専門性の接点を探る
ターゲット顧客が抱える課題の中で、自社の専門知識やノウハウがどのように役立つのかを検討し、テーマを設定します。
問題5 露骨な営業色の強さ
ホワイトペーパーの最終的な目的は売上に貢献することですが、制作段階から営業意識が強すぎると、顧客は警戒感を抱き、本来の目的であるリード獲得や信頼構築が難しくなります。
例えば、ホワイトペーパーの前半から自社製品やサービスの売り込みがされたり、期待してダウンロードしたにも関わらず、知りたかった情報がわずかしか掲載されていない場合、顧客満足度は低下し、その後の関係構築も困難になります。
顧客の課題解決や情報提供を第一に考え、自社のアピールは控えめにすることが重要です。
④ 獲得したいリード像とのミスマッチ
ホワイトペーパーの重要な役割は、将来的な顧客となる見込み顧客(リード)を獲得し、彼らの自社に対する期待感や信頼感を醸成し、最終的に商談フェーズへと移行させることです。
このプロセスを考慮すると、どのような顧客層と繋がりたいのかを明確に設計した上で、ホワイトペーパーを企画・制作・活用していく必要があります。
流れ
STEP1 無関心
STEP2 興味関心
STEP3 比較検討
STEP4 意思決定
これらの各フェーズに合致するホワイトペーパーの種類は異なり、どの種類のホワイトペーパーを作成するかによって、獲得できるリードの質やその後の成果が大きく左右されます。
問題1 見込み顧客のフェーズに合わせたコンテンツ設計の欠如
ホワイトペーパーは、その目的や内容によって多岐に分類され、それぞれ獲得できるリードの属性や確度が異なります。
例えば、顧客の課題解決に役立つHow-to系のノウハウ集は、広範な層にリーチできる可能性がありますが、その後の製品やサービスの商談に繋がるまでには距離があることが多いです。
これは、情報収集が目的であり、現時点では製品やサービスを必要としていない、あるいは具体的な検討段階ではない顧客層に多くダウンロードされるためです。
一方、導入事例や成功事例を紹介するホワイトペーパーは、実際に製品やサービスの導入を検討している顧客が、最終的な意思決定に必要な情報を得るために参照するケースが多く、商談に繋がりやすい傾向があります。
同じ種類のホワイトペーパーばかりを作成するのではなく、顧客の状況に合わせて複数の種類のホワイトペーパーを用意することで、より効果的に成果を上げることが可能になります。
成功事例系のホワイトペーパーを作成する際には、既存顧客へのインタビューが不可欠です。
しかし、貴重なインタビューの機会を設けたにも関わらず、顧客から有益な情報を引き出せなかったり、魅力的なエピソードを聞き出せなかった場合、再度インタビューを設定することは難しく、ホワイトペーパーの質が低下するリスクが高まります。
インタビューに不安がある場合は、専門的なスキルを持つ外部パートナーに相談することも有効な手段です。
改善策
カスタマージャーニーに合わせたコンテンツマッピング
各購買フェーズにいる顧客が求める情報と、提供すべきホワイトペーパーの種類を対応付けたコンテンツマップを作成します。
多様な種類のホワイトペーパー制作
ノウハウ系、事例紹介系、製品紹介系、業界分析レポートなど、様々な種類のホワイトペーパーを企画・制作し、各フェーズの顧客ニーズに対応します。
インタビュー技術の向上または外部委託
顧客インタビューを行う担当者のスキル向上を図るか、専門的なスキルを持つ外部パートナーにインタビューを依頼することを検討します。
問題2 資料請求意欲を高めるための工夫不足
多くの顧客は、最初から特定のホワイトペーパーを入手しようとして情報を探しているわけではありません。
多くの場合、何らかの課題や興味関心を持ち、情報収集を行う中で、たまたま魅力的なホワイトペーパーを見つけてアクションを起こします。
そのため、オウンドメディアの問題でも触れたように、まずはウェブサイトへのアクセス数を増やし、顧客との接点を増やし、ホワイトペーパーの存在に気づいてもらうことが基本となります。
しかし、さらに重要なのは、顧客に「このホワイトペーパーを手に入れたい」と思ってもらうことです。ダウンロードという行動を起こしてもらうためには、顧客の心理的なハードルを下げる必要があります。
例えば、多くのダウンロードフォームでは、氏名、会社名、連絡先などの個人情報の入力が必須であり、これは顧客にとって一定の心理的負担となります。ここで企業側の都合で多くの質問項目を設定してしまうと、回答の手間が増え、いくらホワイトペーパーに興味があっても、途中で離脱してしまう可能性が高まります。
顧客の気持ちの変化率を最大限に高めるためには、提供する価値と入力の手間のバランスを考慮した設計が不可欠です。
改善策
価値訴求の強化
ホワイトペーパーのタイトル、概要、ランディングページなどで、顧客が得られる具体的なメリットを明確かつ魅力的に伝えます。
入力フォームの最適化
収集する情報の目的を明確にし、必要最低限の項目に絞り込むことで、入力の手間を減らし、離脱率を低減します。
プレビュー機能の導入
ホワイトペーパーの一部を事前に公開することで、顧客は内容を確認でき、ダウンロードへの安心感や期待感を高めることができます。
代替手段の提供
ダウンロード以外にも、メールマガジン登録やウェビナー参加など、顧客がより気軽に情報に触れることができる代替手段を提供することも有効です。
⑤ ホワイトペーパーの効果的な活用戦略の欠如
手間暇かけて作成したホワイトペーパーも、その後の活用方法を誤ると、期待した成果を得ることはできません。
完成したことに満足するのではなく、その後の展開を見据えた戦略的な活用が重要です。
もしホワイトペーパーの効果が実感できていない場合は、その活用方法に問題がある可能性を考慮し、以下のポイントを見直す必要があります。
問題1 部署間の連携不足
ホワイトペーパーは、一般的に売上に貢献する部署、すなわち営業、マーケティング、制作などの組織が連携して活用します。ここで問題となりやすいのが、営業部門とマーケティング部門におけるホワイトペーパーに対する認識のずれです。
営業部門の視点
商談に直結する質の高いリードを求めている
マーケティング部門の視点
とにかく多くの見込み顧客を獲得したいと考えている
このように、組織が異なれば、必然的に目標設定や評価指標も異なってきます。
片方が短期的な売上目標を重視するのに対し、もう片方が中長期的なリード獲得数を重視する場合、連携がスムーズにいかず、それぞれの活動が分断され、本来であれば協力してより大きな成果を生み出せるはずの力が分散してしまいます。
ホワイトペーパーそのものの問題ではなく、組織間の連携不足が成果を阻害する大きな要因となることがあります。
改善策
共通目標の設定
営業部門とマーケティング部門が共通の目標(例:売上に貢献する質の高いリードの獲得数)を設定し、その達成に向けて協力体制を構築します。
定期的な情報共有と意見交換
両部門が定期的に情報共有を行い、ホワイトペーパーの活用状況やリードの質に関するフィードバックを交換することで、認識のずれを解消し、改善策を共有します。
役割分担の明確化
ホワイトペーパーの各段階(企画、制作、プロモーション、リードナーチャリング、商談)における各部門の役割と責任を明確にし、スムーズな連携を促進します。
問題2 リード獲得後のフォローアップ体制の不備
ホワイトペーパーの提供を通じて獲得したリードに対して、適切なフォローアップを行うことは、その後の商談化率を高める上で非常に重要です。
例えば、製品に関するホワイトペーパーをダウンロードしたリードは、具体的な比較検討段階に入っている可能性が高いため、電話や個別相談などを通じて、より詳細な情報提供や課題解決に向けた提案を行うことが効果的です。
その一方で、ノウハウ系のホワイトペーパーをダウンロードしたリードは、まだ情報収集段階である可能性が高いため、すぐに営業をかけるのではなく、定期的なメールマガジン配信などを通じて、段階的に関係性を構築していくことが重要です。
このように、獲得したリードの属性や興味関心に合わせて対応を個別化することが理想的ですが、これらのルールが明確に定められていない場合、獲得したリードに対して一律に電話をかけたりするなどの不適切な対応が行われ、結果として商談機会を逸失してしまう可能性があり、リード獲得後のオペレーションを事前に設計し、顧客との無駄のないコミュニケーションを実現するための準備が不可欠です。
改善策
リードの属性に応じたナーチャリング戦略の設計
ダウンロードされたホワイトペーパーの種類や、フォームに入力された情報に基づいてリードを分類し、それぞれの属性に合わせたフォローアップのシナリオを設計します。
SFA/CRMツールの活用
リード情報を一元管理し、フォローアップの進捗状況を可視化することで、効率的かつ効果的なナーチャリングを実現します。
営業・マーケティング連携によるフォローアップ体制の構築
マーケティング部門が獲得したリードを、適切なタイミングで営業部門に引き継ぎ、スムーズな連携によるフォローアップ体制を構築します。
問題3 目的と異なるリードの獲得
すでに十分な数のリードが存在する場合、量よりも質を重視し、成約に近い確度の高いホットリードの獲得に注力すべきですが、一方でリードの絶対数が少ない場合は、確度は低くても多くのリードを獲得できる施策を優先すべきです。
このように、状況によって求められるリードの質と量は変化しますが、その目的を深く考えずに、ただホワイトペーパーを作成・公開するだけでは、本来獲得したかったリードとは異なる層からのダウンロードが増えてしまう可能性があります。
ホワイトペーパーの制作には時間と労力がかかるため、方向性を誤ってしまうと、再度作り直す必要が生じ、さらなる時間とコストがかかってしまいます。
最初から、目的達成に繋がるリードを獲得するために、どのような属性の顧客と繋がりたいのかを明確に設計し、そのターゲット顧客に響くホワイトペーパーの種類を選定し、制作する必要があります。
改善策
リード獲得目標の明確化
どのような質のリードを、どの程度の数獲得したいのか、具体的な目標を設定します。
ターゲットリードの再定義
目標とするリードの属性(役職、業界、抱えている課題など)を明確に定義し、チーム全体で共有します。
コンテンツとプロモーションの最適化
定義したターゲットリードに響くようなホワイトペーパーのテーマ、内容、タイトル、デザインを検討し、適切なプロモーションチャネルを選択します。
最後に
ホワイトペーパーの作成における失敗は、その準備段階から活用段階に至るまでのあらゆるプロセスに潜んでいます。
順調に進んでいるように見えても、潜在的な問題が隠れており、後になって表面化することも。
単にホワイトペーパーを制作することに集中するのではなく、その後の活用方法までを見据え、一連のプロセス全体を考慮しながら戦略的に取り組むことが、ホワイトペーパーの効果を最大化するための重要な鍵となります。