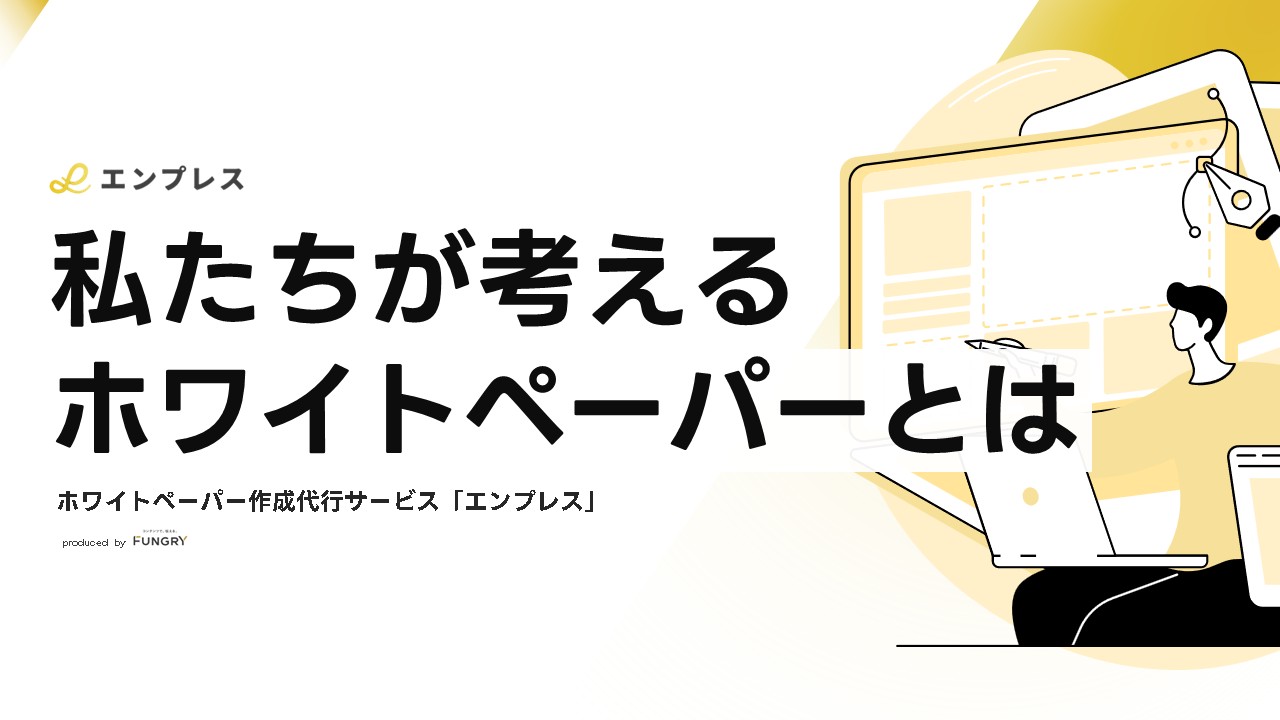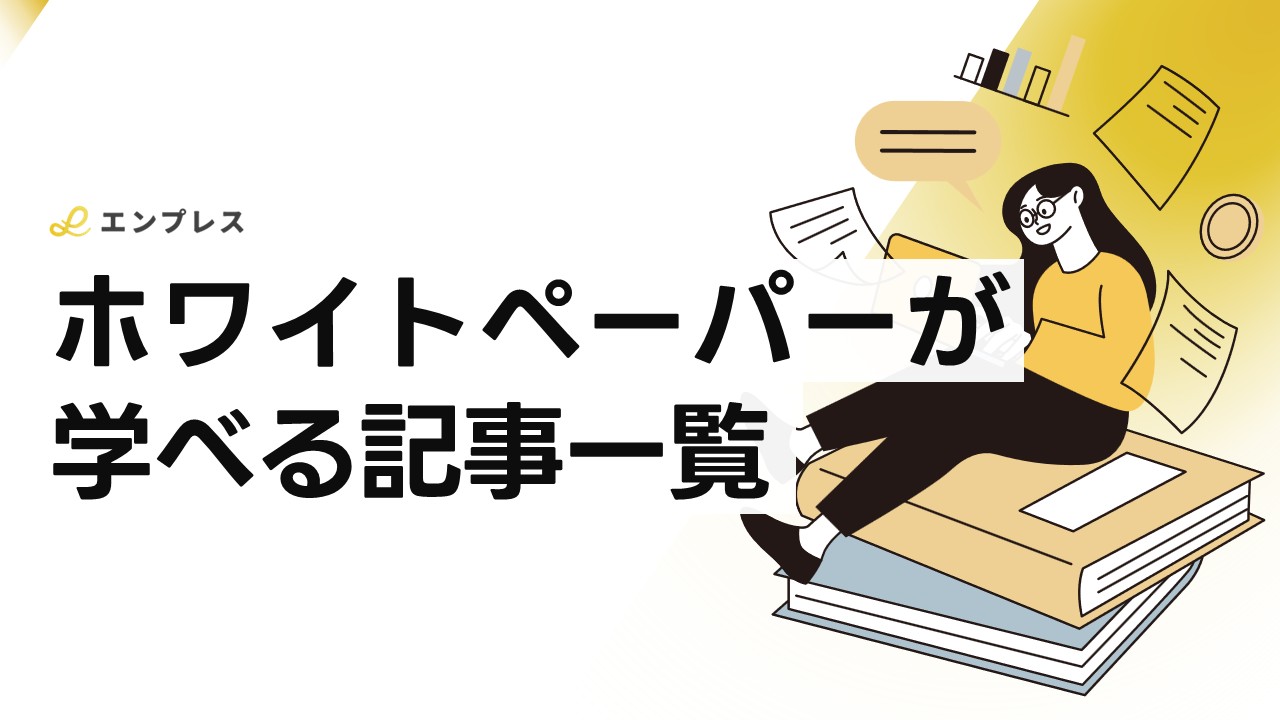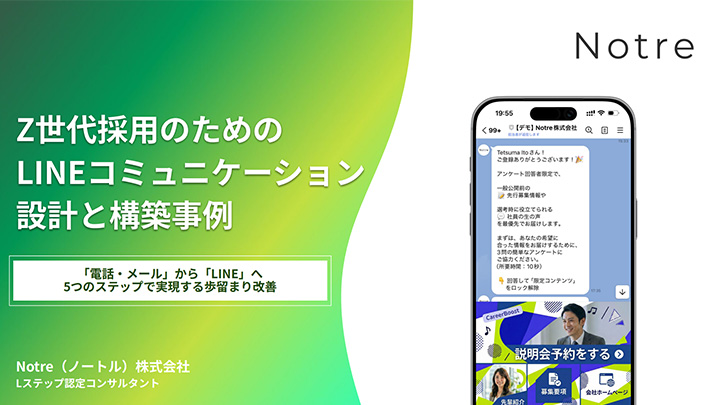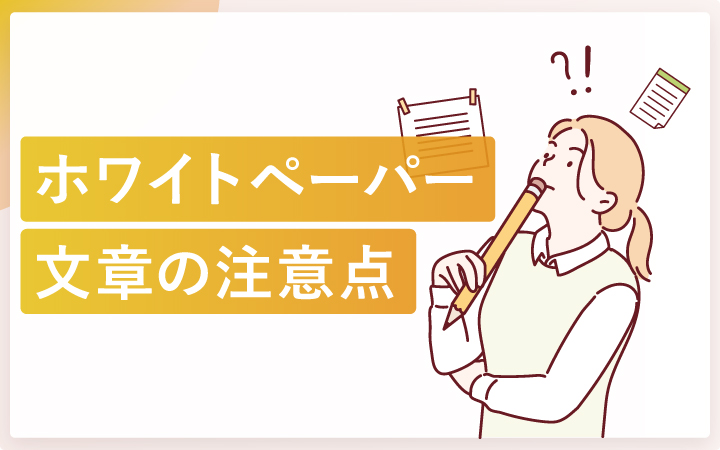
いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーは、文章に気を付けるほど、品質が高くなっていきます。
「ホワイトペーパー」と聞くと、多くの場合「自社の強みをアピールする資料」と捉えがちです。
しかし、どれだけ時間とコストをかけても、成果につながらないホワイトペーパーは少なくありません。
その成否を分けるのが文章の質。
なぜなら、ホワイトペーパーは、読み手が一人で読み進めるものだからであり、直接口頭で補足説明をすることもできません。
アイコンや図解も重要ですが、伝えたい意図や詳細な情報は、やはり文章で示す必要があります。
文章が読みにくかったり、意味がわからなかったりすると、読み手はすぐに読むのをやめてしまいます。
現在活用しているホワイトペーパーは「伝える」で終わらず「伝わった」へ進めていますか?
本当に大切なのは、作った側の意図が、読み手にきちんと「伝わる」ことです。
この記事では、あなたのホワイトペーパーが「伝わらない」状態になるのを防ぐ、3つの重要なポイントと具体的な改善策を解説していきます。
ホワイトペーパーが「伝わらない」3つの要因
ホワイトペーパーの文章が「伝わらない」状態になってしまうのには、いくつかの共通した理由があります。
あまり作り慣れていない場合に陥りやすい、3つの要因を詳しく見ていきましょう。
要因1:作り手の「伝えたい」が強すぎる
ホワイトペーパーは、企業がリード(見込み顧客)を獲得するために制作することが多いものです。
そのため、どうしても下記の熱量が強くなってしまう。
- 自社の製品やサービスがいかに優れているか
- 導入実績はこれだけある
- 商談や契約したい気持ち
このように、気を付けたとしても作っているうちに、企業側が伝えたい情報ばかりを詰め込んでしまいがちです。
たとえば、新しいマーケティングツールを紹介するホワイトペーパーを作る場合、企業側の「伝えたい」意識が強いと、ツールの機能一覧を羅列したり、「業界シェアNo.1」など、自社に都合の良い数字を並べたりする傾向があります。
しかし、初めてそのテーマに触れる読み手は、いきなり専門的な機能や自社アピールを見せられても、そのツールの必要性を理解できません。
それよりも、このツールを使うことで日々の作業がどう楽になるのか、どんな課題を解決できるのか、自分にとってのメリットを知りたい。
このように、企業側の視点だけで作られたホワイトペーパーは、情報が多すぎて読み解くのが大変なだけでなく、「なぜこの情報が必要なのか」が読み手に伝わらないため、結局は関心を持ってもらえず、成果につながりづらくなってしまいます。
要因2:提供側の「当たり前」をそのまま持ち出している
ホワイトペーパーの作り手は、その業界や製品、サービスについて、深い専門知識を持っています。
長年、特定分野で働いている人にとっては、その知識や用語も当たり前の存在。
しかし、その分野外の人からすれば、全く知らない言葉である可能性が高いです。
例えばマーケティング用語なら、
- SaaS(サース)
- ROI(投資対効果)
- CPA(顧客獲得単価)
- リードナーチャリング
- ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)
など、業界に精通していなければピンとこないと思います。
これらの言葉を説明なしで使ってしまうと、読み手は途中で思考が止まり、「これは自分向けの資料ではない」と判断して、すぐにスライドを閉じてしまいます。
調査レポートなど、業界の専門家をターゲットにしたホワイトペーパーであれば問題ありませんが、目的が新規顧客の開拓や、まだ業界知識の浅い層をターゲットにする場合は、読み手がその言葉を知らない前提で文章を書くことが非常に重要です。
要因3:読み手が誰なのか明確化できていない
ホワイトペーパーは、ダウンロードしてくれた人に見て読んでもらい、その内容を理解してもらい、そして満足してもらうことで初めて、企業が求める成果につながります。
つまり、誰に読んでもらいたいのか読み手を明確にすることが、文章を書く上での大前提となります。
もし、読み手を具体的にイメージしないまま文章を書き始めると、誰にも響かない、曖昧な内容になってしまう。
ターゲットが経営者なのか、現場担当者なのか、それとも新入社員なのかによって、抱えている課題や知りたい情報は全く変わりますよね。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 経営者 | 投資対効果や将来の事業展開など、全体像や経営的な視点を重視する傾向があります。 |
| 現場担当者 | 業務効率の改善や具体的な操作方法、導入後のサポート体制などを知りたいと考えます。 |
| 新入社員 | そもそも業界の基礎知識を求めているかもしれません。 |
このように、読み手のペルソナ(具体的な人物像)を深掘りせずに文章を書いてしまうと、誰の心にも刺さらない、ただの情報の羅列になってしまいます。
ホワイトペーパーで「伝わる」文章にする3つのチェック項目
どうすればホワイトペーパーの文章が「伝えた」で終わらず、「伝わる」のか。
次に挙げる3つのチェック項目を使って、文章を見直してみましょう。
チェック項目1:読み手の状況を前提にする
文章を書き始める前に、「誰が」「どんな状況で」 このホワイトペーパーを手にするのかを徹底的に考え抜くことが大切です。
具体的なステップ
読み手の状況を徹底的に掘り下げることで、初めて「この読み手だからこそ響く表現」「この読み手に最適な情報量」を判断できるようになります。
読み手のペルソナを具体的に設定する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 役職や部署 | 購買担当者、人事担当者、マーケティング担当者など。 |
| 抱えている課題 | 「従業員の定着率が低い」「Webサイトの集客に悩んでいる」など。 |
| 情報収集の目的 | 「自社の〇〇に関する最新情報を知りたい」「他社の導入事例を参考にしたい」など。 |
知識レベルを想定する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 専門知識がない初心者 | 専門用語は使わず、噛み砕いて丁寧に解説する。 |
| 専門知識がある中堅層 | 専門用語を使いつつ、独自性や専門性を高めた情報を盛り込む。 |
読むタイミングを想像する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 情報収集の初期段階 | 課題の背景や解決策の全体像を提示する。 |
| 比較検討の最終段階 | 他社との違いや具体的な価格、導入事例を提示する。 |
チェック項目2:自分が「読み手」になったつもりで客観視する
文章を書き終えたら、一度時間を置いて、自分がダウンロードする側の気持ちになって読み返してみてください。
実はこれ、ものすごく大切なチェック項目です。
作っている最中は気づきにくいですが、振り返る状況を作り客観視することで、読み手に合っているかを改めて確認できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| このタイトルでダウンロードしたいと思うか? | 期待通りの内容になっているか、読み始める前にワクワクするか。 |
| 読み進められる文章量か? | ひとつの段落が長すぎないか、情報量が多すぎて疲れないか。 |
| 分かりやすいか? | 接続詞や文脈がおかしくないか、専門用語に説明は加わっているか。 |
| メッセージは伝わったか? | 読み終えたときに、ホワイトペーパーの目的や伝えたいことが理解できたか。 |
作り手は読まれる前提で文章を書いてしまいがちですが実際は…
- 見てくれない
- 読んでくれない
- 理解されない
これらが普通であり、だからこそ、厳しい視点で自分の文章をチェックすることが欠かせません。
チェック項目3:無理に文章化せず視覚的な表現に置き換える
文章は情報を伝えるための強力なツールですが、そもそも長すぎたり、要点を得ない文章は読み手の負担になります。
特に、複数の事柄を説明したり、複雑な関係性を示す内容は、文章で長々と説明するよりも、図・イラスト・グラフなどを使って視覚的に表現する方が、はるかに効率的で情報を伝えられます。
例えば「AとBの課題を解決するために、CとDのプロセスが必要」このような文章があった場合、「課題」と「解決策」の関係図を示したり、フローチャートにすることで、読み手は一目で全体像を把握できます。
文章を読み解くのに苦労する、または5行以上になりそうだなと感じたら、一度立ち止まって、「この内容は図解にできないか?」 と考えてみてください。
文章を短くシンプルに保つことで、読み手の集中力を維持し、よりスムーズに理解を促すことができます。
最後に
ホワイトペーパーの文章は、単に情報を並べるだけでは不十分で、「伝わる」状態を目指すためには、徹底的に読み手目線に立つことが重要です。
- 作り手の「伝えたい」ではなく読み手の「知りたい」を満たす内容になっているか
- 提供側の「当たり前」を押し付けていないか
- 読み手のペルソナを明確に設定しそれに合わせて文章を調整しているか
これらのポイントを意識して改善することで、あなたのホワイトペーパーは、単なる資料から、読み手の心を掴む強力なコンテンツへと生まれ変わっていきます。