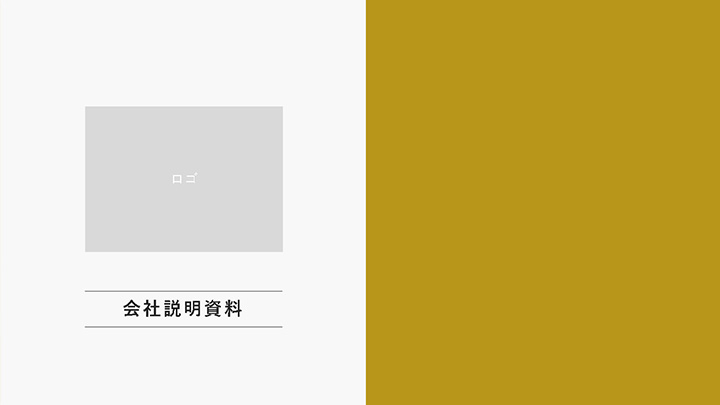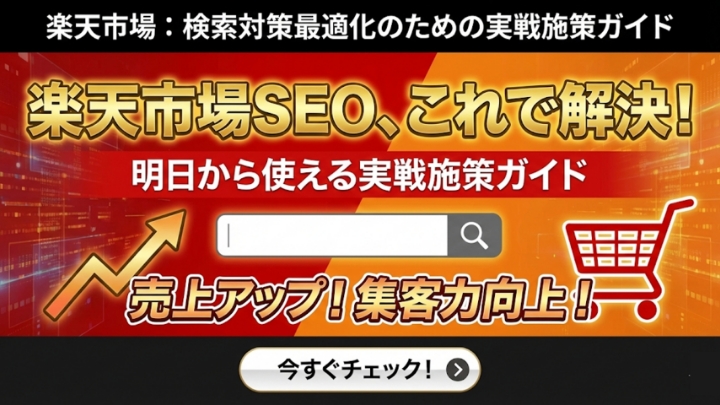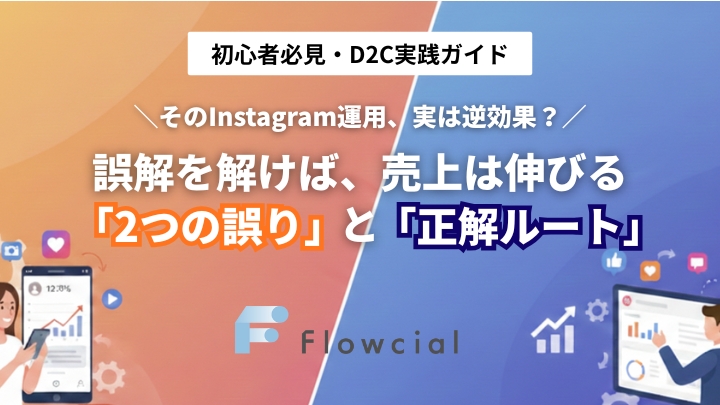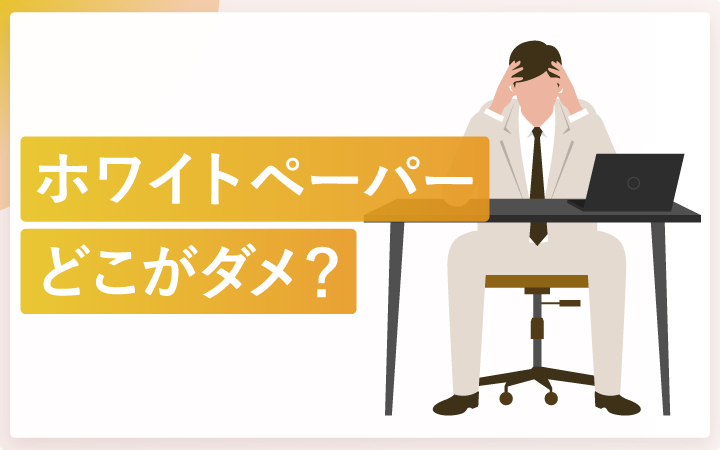
いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。BtoBマーケティングに欠かせないホワイトペーパーが見直せる情報をまとめました。
自社で、または外注で作成したホワイトペーパーが思うような成果を上げられていないと感じたことはありませんか?
たとえば下記のようなポイントが、実は成果を妨げている原因かもしれません。
- 見込み顧客のニーズに沿っていない
- デザインばかりに意識が偏っている
- そもそもリード獲得できる環境ではない
また「リードが獲得できない」と「商談や契約に結びつかない」これらの課題は、別々の原因が絡んでいる可能性が高く、二つを混ぜてしまうと正しい改善策を見誤るリスクがあるため、それぞれを明確に切り分けることが大切です。
この記事では、ホワイトペーパーが成果を出せない背後にある様々な問題点を整理し、具体的な改善方法を事例とともに解説していきます。
原因1. 表紙の情報から期待ができない
見込み顧客がホワイトペーパーをダウンロードするかどうかを決める要素は何なのか。
もっとも重要と言えるのは表紙(タイトル)です。
ダウンロード前に中身が全て見れないからこそ、表紙から得られる情報が判断軸となるため、リードが取れないホワイトペーパーの一番の原因は表紙にあると言えます。
改善策:タイトルと文字サイズの調整
タイトルの例
× 効果的なメルマガを配信する方法
〇 開封率が3倍になったメルマガの配信方法
NGタイトルは、効果的な方法と謳っているものの、どのくらい効果的なのか具体性に欠けているためイメージが浮かびません。
しかし、OKタイトルは具体的な「数字」でイメージのしやすさを高め、効果が得られる「対象」を指定することで分かりやすさが増しました。
ホワイトペーパーのダウンロード促進を目指すなら、分かりやすく見込み顧客の中でイメージ化が出来る情報を、表紙に入れ込む必要があります。
文字サイズの例
× 小さくて凝視しないと分からない
〇 パッと見てすぐ分かる
文字サイズに配慮する理由は、少しでも「見づらい」「分からない」と思わせた時点で、ダウンロードの発生確率を下げるからです。
見込み顧客は最初から、ホワイトペーパーをダウンロードするつもりでwebサイトへ訪問しているわけではなく、掲載されている別の情報を目指してwebサイトへ訪れている。
そのような状況下で、仮にホワイトペーパーのサムネイルを見せても、意識はそもそも別のところへ向いているため、素通りされてしまう可能性が高い。
一瞬の判断で興味を引かせるには、情報そのものが読み取れなければ意味がありません。
デザイン性は保ちつつも文字サイズを大きくして、瞬間的に情報が伝わる状態になるよう心がけましょう。
原因2. 見込み顧客のニーズを捉えていない
どれだけ優秀なチームがホワイトペーパーを企画・制作しても、見込み顧客の真のニーズに応えていなければ、ダウンロード数は伸びません。
実際、各顧客が抱える課題や求める解決策は多岐にわたるため、すべてをピンポイントで把握するのは簡単ではない…。
その結果、どれだけ時間や費用を投入しても、成果が上がらない場合があるのです。
改善策:点が難しければ面で対応
顧客のニーズが捉え切れない場合は『点』に固執せず、『面』全体でアプローチする戦略を取りましょう。
つまり、見込み顧客が直面しているさまざまな課題に対して、包括的な解決策を提供する複数のホワイトペーパーを展開することで、より広いニーズに対応し、ダウンロード数向上の確率を高めることができます。
原因3. 集客コンテンツに連動したホワイトペーパーがない
ホワイトペーパーがダウンロードされるまでの一連のステップは、一般的に下記のようになります。
STEP1 インターネット検索
STEP2 知りたかった情報の記事を閲覧
STEP3 ホワイトペーパーの存在に気づく
STEP4 ダウンロード
この流れを見れば、ホワイトペーパーの存在に気づいてくれたら、自然とダウンロードまで進むと思いがちですが、実際はそう単純な話ではありません。
街中の広告と同じで、自身が知りたいこと以外の情報をいくら見せられても、興味が出ないものには反応しないのが通常です。
改善策:集客コンテンツに連携したホワイトペーパーを用意する
集客からダウンロードまで繋げるには、既に集客効果がある記事と連携したホワイトペーパーを用意することが重要です。
具体的には、集客記事のテーマをさらに掘り下げたホワイトペーパーを作成すること。
このように、記事とホワイトペーパーがシームレスに連動することで、見込み顧客の関心を逃さず、ダウンロード率を向上させることが可能になります。
原因4. タイトルを製品・サービス名にしている
製品またはサービス資料として使うのであればいいですが、ノウハウを提供しつつ、製品・サービスを紐づけて紹介する構成でも、表紙のタイトルをそのまま製品・サービス名にしているケースがよくあります。
ホワイトペーパーを制作した企業側は、製品・サービスについて熟知しているため、製品名・サービス名を言われれば、どのような内容なのか具体的にイメージができます。
しかし、見込み顧客は製品・サービスに対する前提の知識がないため、名称を伝えられても理解ができません。
理解ができないものに手を出す方はそうそういませんので、結果としてダウンロード率も下がってしまいます。
改善策:見込み顧客の便益に繋がる表現にする
最初から自社の製品・サービス名を知っている、または指名検索で探しに来ている方に対しては、名称を伝える形で大丈夫です。
それ以外の場合は、製品・サービスの前提知識がないため、見込み顧客が自身の利益または便益になると感じられる表現を用いて、興味関心を引かせることから始めます。
タイトル例
× 資料掲載サイト「エンプレス」のご提案
〇 BtoBで見込み顧客の第一選択になる方法(補足でサービス名を入れる)
このように、見込み顧客が自社の製品・サービスをどの程度知っているのかによっても、タイトルの付け方は大きく変わるため、ホワイトペーパーをダウンロードしてもらいたい対象を予め深く理解することが重要です。
原因5. 存在が認知されていない
ホワイトペーパー自体に問題は見当たらないのに、ダウンロード数が増えない場合があります。
さまざまな要因は考えられますが、まず一番最初に見直したいのは、ホワイトペーパーの存在が認知されているかどうか。
そもそも存在自体を認識してもらえていなければ、ダウンロードが増えないのもしかたありません。
改善策:見込み顧客とホワイトペーパーのタッチポイントを増やす
ホワイトペーパーの存在を認知してもらうため、複数の施策へ取り組みタッチポイントを増やしていきます。※ タッチポイントとは顧客と接触する機会のこと
① 集客コンテンツの強化
② webサイト内の露出を増やす(例:バナーやテキストリンクなど)
③ ホワイトペーパーをまとめたページの作成
webサイトの改善は必須で行い、見込み顧客へリーチできる範囲を広げていきます。
原因6. チラシをそのままホワイトペーパーとして活用
ホワイトペーパー制作は、企業のマーケティング予算次第であるため、リード獲得はしたいが制作リソースがない場合、既存の資料やチラシをホワイトペーパーの代わりとして使用するケースがあります。
しかし、別の用途で作成した媒体でそのまま代用しても、ホワイトペーパーとして扱うには不十分であり、活用しても成果はあまり得られません。
改善策:ホワイトペーパーの体裁へ整える
見込み顧客に資料をダウンロードしてもらうことは、思った以上に難しいことです。
既存の資料やチラシなどは、別用途で使うために作られており、そのままホワイトペーパーとして代用しようとしても、見込み顧客に合わずダウンロードはしてもらえない。
そのため、少しでもダウンロード頂ける確率を高めるには、見込み顧客が欲しいと思う情報があり、尚且つ見やすく理解しやすい状態にしなければいけません。
改めて、ダウンロードしてほしい見込み顧客に合わせて、構成や文章、そしてデザインなども整えましょう。
・やってはいけないホワイトペーパー(WP)制作9つのこと
・ホワイトペーパーの制作代行サービスおすすめ
原因7. 高い外注費をかけすぎている
ホワイトペーパーの制作スキルがない、または使える社内リソースが少なく外部へ制作を依頼したい時は、制作代行会社へ外注されている方もいらっしゃいます。
外注費の相場としては10ページで10~30万円ほどですが、中身をこだわるためイラストや文章を増やし、10ページ以上にもなればさらに費用が高くなります。
ただ、ホワイトペーパーの制作を外注するのはいいですが、まだリード獲得できていない状態で、ホワイトペーパーだけをピカピカに仕上げても、あまり成果が出ないことも。
むしろ、ホワイトペーパーは少し質を落としても複数制作して、見込み顧客へ試しながら調整を繰り返すことで、成果を高めていける施策であるため、外注して作りっぱなしにしていると、リード獲得にはあまり貢献しません。
改善策:どのようなホワイトペーパーの作り方がいいのかフェーズを理解する
ホワイトペーパー制作の外注を考えるより前に、まずは自社の状況理解が必要です。
状況① ダウンロードが少ない
→見込み顧客のニーズが捉えられていない
状況② ダウンロードが多い
→見込み顧客のニーズを捉えている
たとえば資料ダウンロードが少ない状況であれば、ホワイトペーパーだけの問題ではなく、ダウンロードへ至る環境整備も不十分であるのに、ホワイトペーパーだけの品質を高めても結果は出ません。
その逆で、資料ダウンロードが多くて定期的にリード獲得できているなら、環境を整備できニーズも捉えられていることから、外注によるスキルやリソースの補填をしても、十分活かせます。
このように、自社がどのようなフェーズなのかを理解できないまま、外注費だけが高くなっていると、費用対効果の低さから施策が継続できなくなる場合も。
まず外注するのではなく、自社で見た目よりも中身を重視しながらホワイトペーパーを制作して、ダウンロードが入る状態まで試して頂くのがお勧めです。
原因8. 集客チャネルが限定的
ホワイトペーパーはさまざまなシーンで活用できますが、基本は自社のwebサイトにダウンロードリンクまたはフォームを用意して提供する方法です。
自社のチャネルで集客が十分できているなら問題ありませんが、webサイトの媒体力が低ければ集客が難しいですし、競合他社のwebサイトよりも検索順位をあげることは簡単なことではありません。
改善策:あらゆるチャネルを活用
webサイト一本では、集客力が賄えない場合、他の媒体もうまく活用していきます。
① SNS(例:X、Instagram、pinterestなど)
② 他媒体(例:note、広告媒体など)
③ 直接的なアプローチ(例:現場担当者がクライアントへ紹介など)
テクノロジーの進歩によって、多方面の情報収集場所ができるようになり、見込み顧客はそれらの場所へ自由にアクセスして情報を収集しています。
そのため、見込み顧客がアクセスしそうな場所でも展開することで、ブランド認知や比較検討の候補にも入りやすくなり、資料ダウンロードの向上にも期待ができます。
原因9. ブランド力で競合他社に負けている
見込み顧客は、具体的なアクションを起こす前に、複数の媒体を通じて事前に情報収集を行っています。
たとえば、ウェブ検索やSNS、業界ブログなどで得た情報をもとに、どの企業やサービスに信頼を置くかを判断。
このプロセスにおいて、すでに見込み顧客は自社と競合他社の比較を行っており、ブランド力が十分に確立されていなければ、そもそも自社が検討候補にすら上がらない状況に陥ります。
つまり、信頼できる情報源として認識される前に、ホワイトペーパーの存在に気づいてもらっても、見込み顧客はダウンロードに踏み切りません。
信頼できないサイトでいきなり個人情報の入力を求められても、自然と他の企業の方が魅力的に映るため、ダウンロード数が増えない負のループが起きます。
改善策:ダウンロード前の信頼形成
まずは見込み顧客と事前の信頼関係を築くことが必要であり、具体的な対策としては以下2つの取り組みが有効です。
| 信頼性の高い記事コンテンツの提供 | 業界に精通した専門記事、成功事例、導入事例、顧客の声などを用いて、自社の実績や専門性をアピール。これにより、見込み顧客は「この企業なら信頼できる」という印象を持ち、自然と自社サイトに足を運ぶようになります。 |
|---|---|
| 一貫したブランドメッセージの発信 | Webサイト、SNS、メールマガジンなど、すべてのタッチポイントで一貫したブランドメッセージを伝え、企業の価値や強みを強調することが重要。これにより、見込み顧客は複数の接点で自社の信頼性を確認でき、ホワイトペーパーのダウンロードに対する抵抗感が薄れます。 |
このような事前の信頼構築とブランド強化の取り組みにより、見込み顧客は具体的なアクションを起こす前から自社に対して好印象を持ち、ホワイトペーパーのダウンロードへとつながりやすくなります。
原因10. ターゲットを広めすぎて無難な内容になっている
ホワイトペーパーでリードを獲得しようとする際、よくあるミスは「ターゲットを広く設定しすぎる」ことです。
もちろん、より多くの見込み顧客にアプローチしたいと思う気持ちは分かりますが、対象を広げるほど、各セグメントのニーズに応じた具体性が薄れ、結果として以下のような問題が発生します。
| メッセージの薄さ | 多様なニーズに配慮しすぎると、伝えるべき核となるメッセージがぼやけ、説得力に欠ける表現になりがちです。 |
|---|---|
| 制作工数の増加 | 伝える情報が増えるため、コンテンツ制作にかかる手間や時間が膨大になり、結果的に中途半端な品質に留まる恐れがあります。 |
| 独自性の欠如 | 幅広いターゲット向けに作成されたホワイトペーパーは、他社との差別化が難しく、見込み顧客の興味を引きにくくなります。 |
改善策:ターゲットを絞る勇気を持つ
ターゲットを絞ると「ダウンロード数が減るのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、すべての層に中途半端な内容を提供するよりも、特定の層に向けて徹底的に価値を追求する方が、結果として強い印象を与えることができます。
たとえば「みんなのために作る」アプローチでは、どうしても内容が平均的な品質(60~70%程度)に留まってしまいます。
その一方で、特定のターゲットに向けたメッセージであれば、その層の具体的な課題やニーズに焦点を当て、他では得られない情報や解決策を提示できます。
- ターゲットの明確化
- ニーズに合うコンテンツ
- 専門性と独自性の提供
このように、ターゲットを絞り込む勇気を持つことで、結果としてコンテンツの質が向上し、リード獲得にも大きく貢献。
広く浅く訴求するよりも、狭く深くアプローチすることが、情報過多な現代においてはむしろ逆に強みとなるのです。
原因11. ターゲットの集客ができていない
資料ダウンロードも定期的に入り、順調にホワイトペーパーマーケティングが進んでいるように見えても、商談へ繋がらないケースが多々あります。
これは、自社が定義した見込み顧客よりも、手前の見込み顧客(情報収集フェーズ)の多さが原因です。
比較検討フェーズだと商談に引き上がりやすいですが、まだ情報を探している状況だと、営業を嫌って話を聞いてもらえない。
改善策:ターゲットを引き寄せるコンテンツ強化
あまりナーチャリングはせず、比較的早いタイミングで商談化を狙いたい場合は、見込み顧客が課題解決の手段を本格的に探しているタイミングで出会う必要があります。
今まで単純なノウハウコンテンツで集客していたのであれば、比較検討のタイミングで検索するようなキーワードでコンテンツを作り、ターゲットを引き寄せていきます。
キーワード例
× ホワイトペーパーとは?
〇 ホワイトペーパーの制作代行サービス
原因12. 信頼形成に繋がる質ではない
リード獲得後のインサイドセールスにて、電話またはメールで次のフェーズへ進んでもらえるよう、見込み顧客へアプローチを行っていきますが、このタイミングで毎回「今は結構です」「情報収集だけなので」とお断りが入る場合は、見込み顧客と信頼を築けていない可能性が考えられます。
まず、ホワイトペーパーをダウンロードした時点ではあくまで「期待」の段階であり、このタイミングでいきなり十分な「信頼」を獲得できるわけではありません。
実際に中身を見て、見込み顧客自身の悩みや問題の解決につながり、専門性の提供によって権威者として認められた際、初めて少しばかりの信頼が築けます。
しかし、悩みも解決できず、インターネットで探せばすぐ探せるような情報ばかりで専門性も薄い中身だと、期待外れだと感じて、ホワイトペーパーを提供して企業にいい感情を抱きません。
マイナスブランディングにより、商談創出まで長引く、または獲得そのものが出来ない事態に陥ります。
改善策:自社よりも見込み顧客を第一優先する
たとえ興味があったとしても、ホワイトペーパーが1つダウンロードされたからと言って、見込み顧客は話を聞いてくれる気持ちにはなってくれません。
「ダウンロード」と「話を聞いてくれる」、これらは両方とも見込み顧客のアクションですが、その性質は大きく違います。
ダウンロード :個人の行動で完結
話を聞いてくれる:時間を合わせたり確保しないといけない
話を聞く方が、行動的にも心理的にもハードルがとても高い。
そのため、まずは少しでも「話を聞いてもいい」と思ってもらえるように、ホワイトペーパーで見込み顧客の問題を解決してあげなければいけません。
売り込みよりもまずは小さい信頼獲得から。
この意識でホワイトペーパーを制作していきましょう。
原因13. ずっと同じレベルの情報を提供している
リード獲得後、多くの企業はメルマガを通じて定期的にホワイトペーパーを提供していますが、毎回同じレベルの情報やテーマでホワイトペーパーを提供すると、以下のような問題が発生します。
- ・専門性や権威性の提供不足
・顧客の成長速度に合わない内容
・商談機会の喪失
見込み顧客の成長速度に合わせた情報提供ができていないことで、せっかく得られた繋がりが先に進められません。
改善策:段階的にレベルを引き上げていく
見込み顧客も、自身が気になる情報については、能動的に調べていると仮定すれば、どんどん知識を身に付けて日々レベルアップしていきます。
それなのに、提供するホワイトペーパーがいつも同じレベルで、専門性・独自性もなければ、見込み顧客の成長力についていけず、役に立たないと思われてしまう。
定期的にホワイトペーパーを提供するなら、中身の難易度を段階的に引き上げて、見込み顧客の成長を手助けしていきましょう。
自分の成長に役立つ情報をくれる企業には、信頼や権威を感じ取り、相談相手の第一候補に入りやすくなります。
原因14. 枚数が少ない
ホワイトペーパーはあまりじっくり見られるものでもないため、1枚300~500文字に抑えて、10~20枚ほどシンプルにまとめることが基本の作り方となっています。
ただし、見込み顧客が今すぐ実践して解決できるような悩みや、調査データを軽く公開するだけならいいですが、専門性・独自性を出すためには、それなりの情報量が必要。
また、全てのスライドを読むかどうかは別として、枚数の少なさが専門性・独自性の低さに捉えられてしまうケースもあるため、特定のテーマによっては枚数が求められます。
改善策:シンプル版とボリューム版で作成
ホワイトペーパーの目的やターゲットに応じて、2種類の資料を用意するのが効果的です。
シンプル版
よくある課題を解決するためには、すぐ対応できそうな手法をシンプルにまとめたホワイトペーパーにする。
ボリューム版
信頼をさらに積み重ねていくには、競合他社も作成が苦労するほどの専門性と独自性を詰め込んだ、ボリュームのあるホワイトペーパーにする。
このように、テーマや目的に応じてホワイトペーパーの構成を工夫することで、単に枚数が少ないという問題を解消し、見込み顧客に対して信頼性と専門性を効果的に伝えることが可能になります。
原因15. 作って終わりになっている
ホワイトペーパーは、以下のような多様なシーンで活用されています。
・資料ダウンロード(例: ウェブサイトやメルマガからの取得)
・直接手渡し(例: 印刷物やPDFとしての提供)
・イベントの特典(例:セミナー参加者へのプレゼント)…など
しかし、一度作成したホワイトペーパーをそのまま改善せず使い続けていると、実際のお客様からのフィードバックや市場の変化が反映されず、ニーズの捉え違いや情報の過不足が起きて、商談や契約へ繋がるアクションが生まれにくくなります。
改善策:定期的なフィードバックと反映
ホワイトペーパーの効果を持続させ、見込み顧客を次のフェーズへ誘導するためには、作成後も継続的な改善が不可欠です。
- フィードバックの収集(社内・社外含めて)
- 内容の見直しと更新
- 改善サイクルの導入
作って終わりにせず、常にアップデートを心がけることで、ホワイトペーパーのパフォーマンスは高まっていきます。
原因16. デザインばかりにこだわっている
お客様に提供するからと、見た目ばかりに意識が向けられてしまうケースがあります。
たしかに見た目は重要ですが、ホワイトペーパーは試しながら改善することが基本の扱い方になるため、デザインよりもまずは企画・構成など中身に変化を起こして、反応を確かめていく必要があります。
初見での印象に頼り過ぎると、提供すべき情報作成にリソースが回らず、結果として中身の質が低下してしまう。
ホワイトペーパーに求めているのは、魅力的なデザインではなく、具体的で有益な情報であるため、専門性や独自性が低いと見込み顧客からの信頼が獲得できず、次のフェーズへ進みません。
改善策:表紙以外はシンプルにまとめる
目に付きやすい表紙はデザイン性を求めたいですが、その他中ページに関しては、情報が正しく伝わればいいのでシンプルにまとめるのがお勧めです。
中身の充実を図ることで、自社の専門性などが示せて見込み顧客から相談相手の候補として上がりやすくなります。
原因17. 作り手が伝えたいことばかり
ホワイトペーパーは営業ツールとして活用されるものですが、作り手が伝えたい情報を盛り込みすぎると、結果的に見込み顧客が本当に知りたい内容よりも自社のアピールが前面に出てしまいます。
たとえば、
「この情報も入れたい」
「あれも伝えておかないと」
関係者が多くなるほど、要望が膨らんでいき、結果として自社をアピールする情報ばかりになってしまう。
そういった営業視点に偏ったホワイトペーパーでは、見込み顧客が必要とする具体的な解決策が提示されず、結果として商談や契約へと進むきっかけが失われてしまいます。
改善策:見込み顧客の課題解決を最優先にする
まずは見込み顧客が抱える課題や悩みをしっかりと理解し、その解決に向けた情報提供を最優先に考えることが重要です。
自社をアピールしたい気持ちを一旦抑え、相手のニーズに寄り添う内容を中心に構成することで、読者にとって真に役立つホワイトペーパーとなり、結果的に信頼関係の構築や商談・契約への道筋を作ることができるのです。
原因18. データや根拠が乏しい
ホワイトペーパーで伝えたい情報の納得感を高めるため、調査データ(主に数字)を活用する機会があります。
数字は具体的なイメージ化に繋がり、情報の分かりやすさを向上させますが、何を元にした数字なのか示されていないと、根拠が乏しくなります。
改善策:出典元を入れる
数字を出すなら必ず、出典元(データの提供先)を示します。
もし、出典元が出せないのであれば、数字を出しても出所が分からないことで、疑いの目が入り信用を失うことにも。
原因19. 論理的な構成になっていない
ホワイトペーパーは見込み顧客にとって分かりやすい内容でなければいけまsん。
しかし、たとえ専門性や独自性が盛り込まれていても、論理的な構成になっていないと、情報が一貫性を持って伝わらず、読者は「よくわからない」と感じやすくなります。
作り手は自分の伝えたいことに注力しすぎるため、情報が断片的になり、全体としての理解度が低下し、結果として商談や契約への具体的なアクションを引き出すことが難しくなります。
改善策:読み手に疑問を発生させない構成にする
課題解決型ホワイトペーパーであれば、まず基本的な構成を意識し、情報を段階的かつ論理的に整理して提示することが重要です。
たとえば、まず表紙で見込み顧客の興味を引き、次に具体的な課題を明確に示し、その後に解決策を提示し、最後にその根拠やデータを提示するという流れを確立します。
作り手自身の高い理解度に頼るのではなく、知識や経験が少ない見込み顧客でも理解しやすいよう、順序立てて説明することで、情報が一貫して伝わり、結果として信頼感が醸成され、商談や契約に繋がる可能性が高まります。
原因20. ターゲットが分かる言葉に翻訳されていない
ホワイトペーパーが専門用語や業界特有の表現に偏っていると、見込み顧客が直感的に理解しにくくなります。
顧客自身が日常的に使用している言葉で情報が提供されていないため、「自分たちの状況に当てはまる」と感じにくく、情報が自分事化になりません。
その結果、商談や契約に至らない可能性が高まります。
改善策:ターゲットが分かる言葉へ翻訳する
ターゲットとなる顧客が実際に使っている言葉や事例を取り入れることで、情報を分かりやすく、具体的に伝える工夫が必要です。
専門用語や抽象的な表現は、よりカンタンな言葉に置き換えて、見込み顧客が今現在悩んでいる課題や状況に寄り添った説明を心がけます。
こうすることで、見込み顧客は自分の問題解決につながる内容だと感じ、商談や契約へと自然に進む土台を作ることができます。
原因21. 期待をしすぎてダウンロードユーザーの温度感に合わない対応をしている
多くの見込み顧客は資料ダウンロードなどを通じて、まだ情報収集の段階にあります。
しかし、温度感を無視してすべての見込み顧客に直接電話でアプローチすると、実際にすぐ相談したいと考えている人はごく一部であるにもかかわらず、準備が整っていない顧客に対して強引なアプローチをかけることになってしまいます。
その結果、顧客はプレッシャーを感じたり、逆に興味を失ってしまい、商談や契約へと結びつく機会を失う結果にも。
改善策:見込み度を判断したアプローチを実行
資料ダウンロード後やその他の接点を通じて、各見込み顧客の行動データを収集し、情報収集段階か具体的な相談に進む準備ができているかを判断する仕組みを整えることが必要です。
情報収集中の顧客には、すぐに電話でアプローチするのではなく、メールや追加コンテンツを通じたフォローアップを行い、徐々に信頼関係を構築します。
具体的な相談や導入の意欲が見受けられる顧客に対しては、適切なタイミングで直接電話や個別のアプローチを行うことで、商談・契約へと効率的につなげることができます。