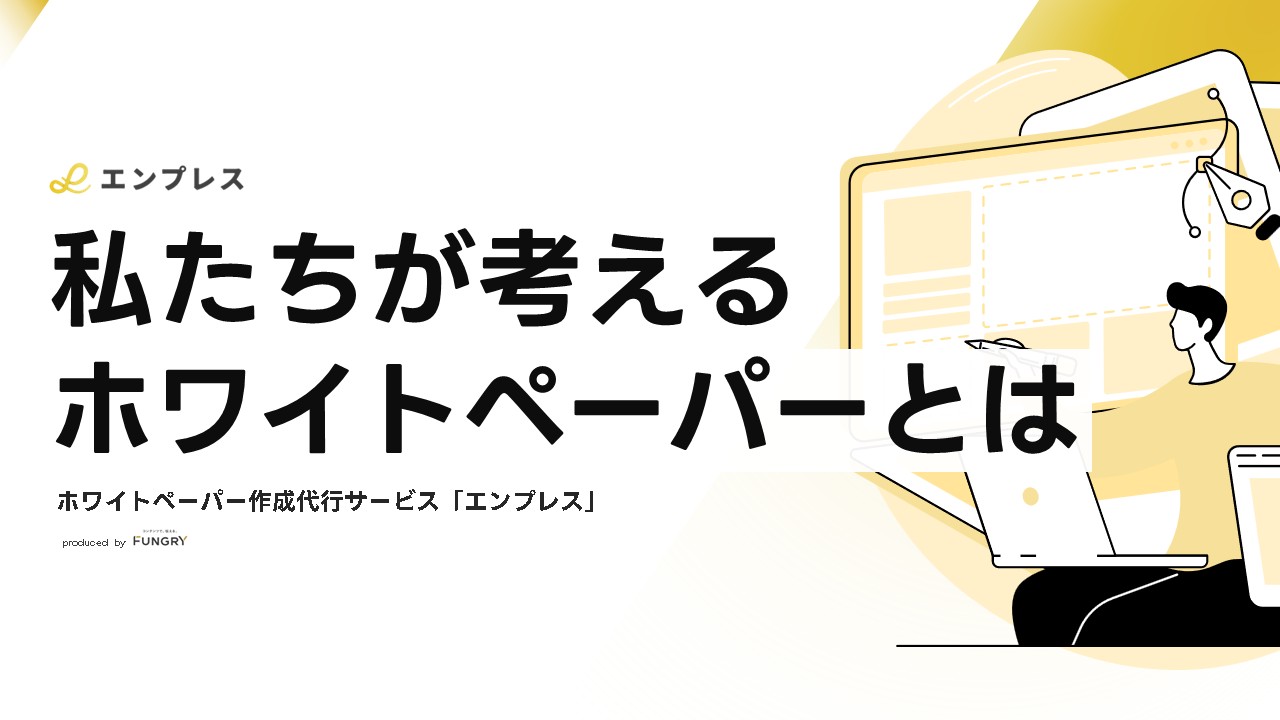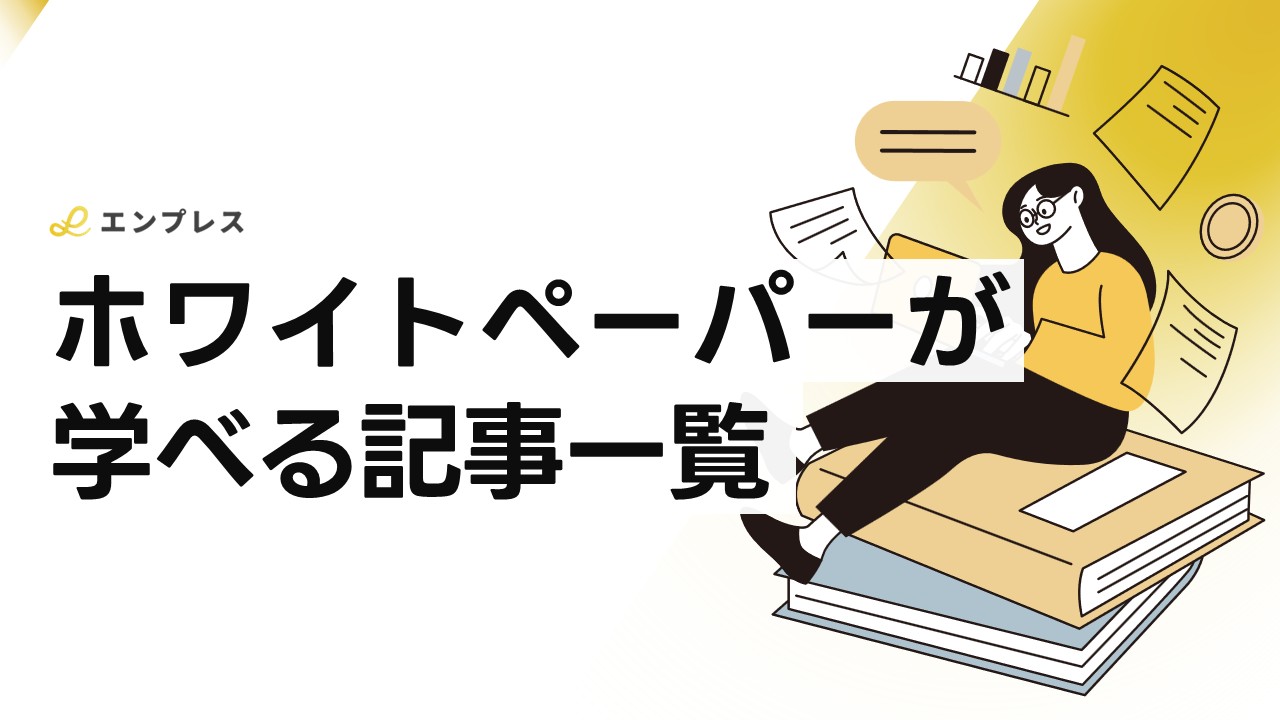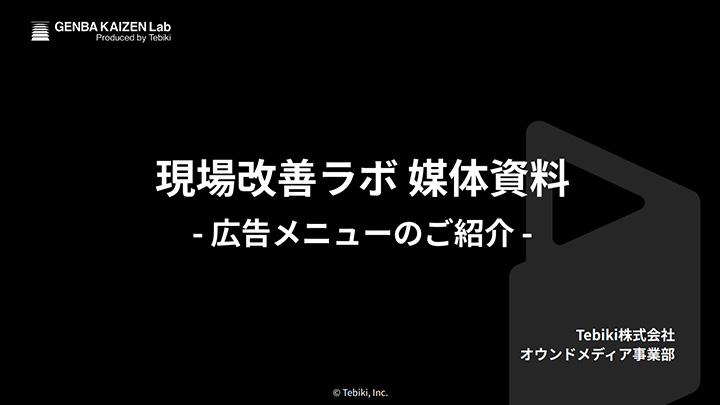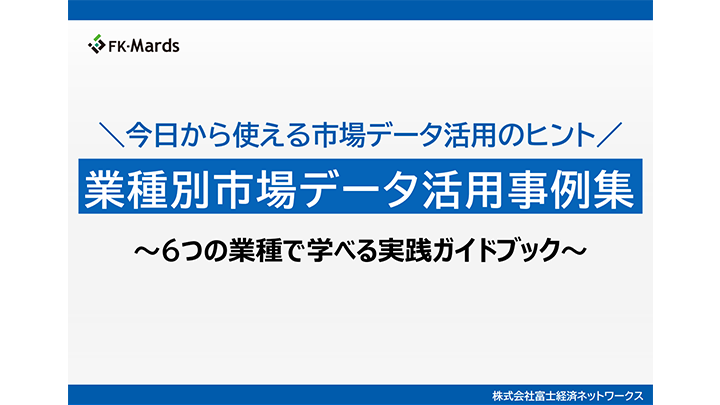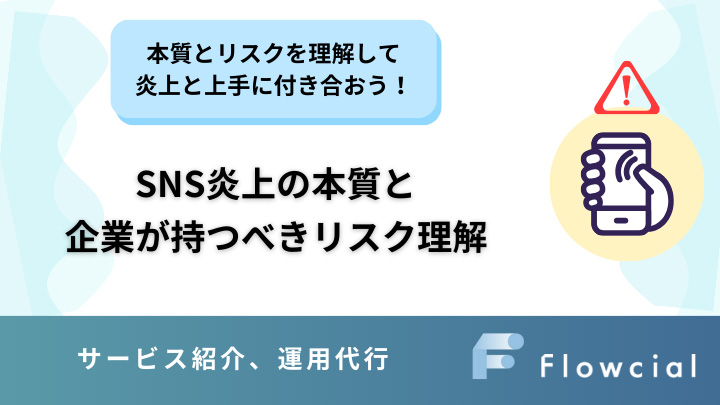いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ワンランク上のホワイトペーパーを作るためには、フィードバックが重要です。
ホワイトペーパーを作成したあと、上司やクライアントに対して「これでいいか」と、フィードバックを求めますよね。
完成前にチェックフローを通すことは、より良いものにしたいと、強い思いがあるからだと思います。
しかし、このフィードバックのやり方を少しでも間違えると、せっかくのホワイトペーパーが迷走し、本来の目的から大きく外れてしまうことがあります。
なぜそんなことが起こるのか、原因と対策を見ながら、今よりもいい状態のホワイトペーパーを作るための考え方を見ていきましょう。
フィードバック失敗の根源は「意図を伝えない」こと
最もよくある失敗は、フィードバックを求める際に、ホワイトペーパーの制作意図を何も伝えないことです。
実際にイメージすると怖いのですが、「制作したので確認してください」とだけ言って、確認してもらいたい相手にホワイトペーパーを見せた場合どうなるでしょうか?
確認した人は、それが「誰のために、何のために、どう使われるのか」と背景を全く知らない状態だと、自分の主観で判断するしかありません。
結果として「このデザインはもっと派手な方がいい」「この文章はもっと柔らかい表現の方が好みだ」と、個人の好みに基づくフィードバックが中心になってしまいます。
これはとても危険なことです。
なぜなら、ホワイトペーパーの「価値」を決めるのは、作り手でも、確認した人でもなく、最終的にそれを読む「読み手」だからであり、個人の好みだけで判断されたフィードバックを元に調整を重ねると、本来ターゲットにすべき読み手のニーズからどんどん離れていってしまうからです。
なぜ個人の主観が危険なのか?
ホワイトペーパーの「価値」は、単なる見た目の美しさや情報の多さではありません。
その本質は「読み手が、自分の課題を解決するヒントや具体的なアクションプランを得られたか」この一点につきます。
別の言い方をすれば、読み手が「納得」または「理解」できたかどうかです。
たとえば、あなたがBtoB(企業向け)のSaaSサービスを扱っているとして、そのサービスに興味を持つ、特定業界の担当者に向けてホワイトペーパーを作成した場合、このホワイトペーパーの本当の価値は、担当者がそれを読んで「自社の問題が解決できる可能性がありそう!」と感じられることにあります。
しかし、意図を伝えないフィードバックは、こうした本質的な価値ではなく、デザインや文字の大きさなど「表面的」なものに留まりがち。
本質的な改善につながらないフィードバックばかりを受けても、本当に読み手に役立つホワイトペーパーにはならないため、注意が必要です。
よくあるフィードバックの失敗例
ホワイトペーパーの失敗フィードバックは、様々なシーンで起こりますが、特にありがちな2つのケースを見てみましょう。
ケース① デザイナー・上司間の失敗フィードバック

ある企業のデザイナーが、自社製品のホワイトペーパーを作成。
上司に確認を求めると「デザインが少し単調だから、もっと派手にしてほしい」とフィードバックが来ました。
上司はデザイナーなので、デザインの美しさ自体を評価することはできますが、そのデザインが「どのような状況で、誰に読まれることを想定して作られたのか」背景を共有していなければ、フィードバックは見た目の良し悪しだけにとどまり、本来求めたかったフィードバック内容とはズレていきます。
ホワイトペーパーは見た目だけでなく「読みやすさ」や「理解しやすさ」も重要な要素ですが、自社のマーケティング状況から考えて、何をどのように扱えば成果が出るのか、作る前と後のことがとても重要で、そこを加味していないフィードバックは意味を成しません。
見た目だけ追求して調整を重ねても、状況や活用まで考えられていなければ、成果にはつながりません。
ケース② 制作会社・クライアント間の失敗フィードバック

制作会社がホワイトペーパーを完成させ、依頼主であるクライアントに確認してもらおうと「制作したのでご確認ください」とだけ伝えました。
すると、クライアントから「もっと会社の理念を強く打ち出してほしい」「この専門用語はうちの会社ではこう呼んでいるから直してほしい」とフィードバックが来ました。
クライアントは自社のアピールや成果を出したい気持ちが強く、どうしても「自社視点」で物事を見てしまいます。
これは悪いことではないのですが、自社の製品やサービスに対してとても詳しいからこそ「自己都合」的な考えになりがち。
無意識のうちに、業界でしか通じない専門用語を使ったり、自社にとって都合の良い表現を求めてしまったりします。
しかし、実際にホワイトペーパーを読むお客様は、必要な専門知識を持っていません。
お客様(読み手)は、企業が使いたい言葉ではなく「自分が知りたいこと」を解決してくれる情報を求めているため、クライアントの主観に振り回されてしまうと、お客様(読み手)には響かない、独りよがりなホワイトペーパーができてしまいます。
しかも、そこに気づかず使い続けてしまった場合、途中で間違っていることに気づければいいですが、そうでなければ求めていた成果を出すまで時間がかかりすぎてしまうことにも。
適切なフィードバックに必要な5つの前提知識
ホワイトペーパーの失敗を避けるために、フィードバックを行う人は、次の5つの前提知識を必ず理解している必要があります。
1. ホワイトペーパーを使う側のマーケティング状況
ホワイトペーパーは、必ず何かしらの課題を解決するために、制作されるマーケティングツールです。
そのため、自社のマーケティングのどの位置で使うのか理解していないまま制作すれば、当然使えないものができてしまう。
フィードバックを受ける時も、現在のマーケティング状況を理解していることが前提になります。
- 自社のマーケティング活動の中でどのような役割を担うのか?
- 競合他社と比べてどのような強みや弱みをアピールすべきか?
- ホワイトペーパーを読むまでにどのような情報をどこで目にしているか?
過去・現在・未来のマーケティング状況を理解することで、フィードバックは「見た目」ではなく「市場での効果」を考慮されたものになります。
2. 制作目的
自社のマーケティング状況を理解したうえで、なぜホワイトペーパーが必要なのか、そしてどのような目的のために制作するのか。
ここを明確に理解していないと、的確なフィードバックをすることは難しい。
そのため、ホワイトペーパーの最終的なゴール(目的)は何か?を明確にすることが重要です。
例:
・リード獲得
・見込み客の育成
・ブランディング、(顧客の信頼獲得)
など
そしてなぜこの目的を達成したいのか? それは、誰の、どのような課題を解決するためのものなのか?
目的を明確にしてフィードバック側も理解していなければ、チェックのしようがなく、逆に理解していれば「なんとなく良さそう」ではなく、「この目的を達成するために、この部分は〇〇すべき」と具体的なフィードバックが可能になります。
3. 活用計画
自社のマーケティング状況を理解していれば、ホワイトペーパーをどのように扱えばいいのか、分かっていると思います。
むしろ、ホワイトペーパーを制作するより、活用しながら改善する方が難しく、対応する期間も長いので、活用計画をどこまで理解できているかが重要。
フィードバックは必ず、このホワイトペーパーが、完成後どのように使われるのか?具体的な計画のもと行われる必要があります。
活用計画例
| 項目例 | 説明例 |
|---|---|
| ウェブサイトでダウンロードさせるのか? | 冒頭で「ダウンロードするメリット」を強調したい。 |
| 営業資料として使うのか? | 営業担当者が顧客に説明しやすいよう、図解を多めにしたり、章立てを分かりやすくする必要がある。 |
| メールマガジンの特典として送るのか? | 読者がすぐに役立てられる実践的な情報が求められる。 |
活用方法によって、ホワイトペーパーの最適な形式や内容も変わってくるため、フィードバックの視点も変わります。
4. ターゲット
このホワイトペーパーは一体「誰に」読んでほしいのか、ターゲット像を深く掘り下げましょう。
たとえば初心者向けなのに専門用語を多用していたら分かりませんし、その逆もある。
そしてホワイトペーパーが「良かった」のか「悪かった」のかを評価できるのも、読み手であるお客様だけ。
ターゲットの理解不足は、的確なホワイトペーパーを作れないと言っているようなものでもあります。
- ターゲットはどのような立場の人か?
- 彼らはどんな悩みを抱えているか?
- 彼らが求めている情報、解決したい課題は何か?
ターゲットが明確であれば、フィードバックは「この表現はターゲットに響くだろうか?」「この情報は見込み顧客の悩みを解決できるだろうか?」と、さまざまな視点から検証を行い、適正なホワイトペーパーへ導きやすくなります。
5. 制作時の意図
最後に重要なのが、このデザイン・文章・構成にした「理由」を伝えること。
このプロセスがないと、さらにフィードバック者の主観が入り込みやすく、ホワイトペーパーの調整が明後日の方向へいってしまいます。
ホワイトペーパーが完成する前に、途中途中で確認はしていると思いますが、最終的なアウトプットへ至った思考もきちんと説明しておくべき事項です。
| 項目例 | 説明例 |
|---|---|
| なぜこの配色にしたのか? | 信頼感や安心感を与えるため。 |
| なぜ専門用語を避けたのか? | 初心者でも理解できるようにするため。 |
| なぜこの章から始めたのか? | 読み手の関心を引くために、最も重要な情報を冒頭に持ってきた。 |
| なぜこのイメージになったのか? | ブランドを統一するため。 |
| なぜこのフォントにしたのか? | 読みやすさを重視するため。 |
制作側の意図を伝えることで、フィードバックをする人は、ただの「感想」ではなく、「意図を理解した上での建設的な意見」を返せるようになります。
正しいフィードバックへ導くための準備
ホワイトペーパーのフィードバックを成功させるためには、適切なフィードバックを行ってもらえる状態へ整えることが重要です。
たとえば口頭で伝えたとしても、「聞いてない」や「言った言わない」問題にも発展するので、確実に情報共有できる状態を作るため、ヒアリングシートを事前に用意して、関係者全員で共有しておく。
そのシートには、先ほどの「適切なフィードバックに必要な5つの前提知識」を元にした、具体的な項目を抽出してリスト化します。
ヒアリングシートの具体的な質問例
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 制作の背景 | どのような状況で、なぜこのホワイトペーパーが必要になりましたか? |
| 目的とゴール | 最終的にこのホワイトペーパーで何を得たいですか? |
| ターゲット像 | 理想的な顧客像は誰ですか?彼らは現在、どんな悩みを抱えていますか? |
| 活用方法 | このホワイトペーパーは、完成後にどのように使われますか? |
| 期待する行動 | 読んだ後、どのような行動をとってほしいですか?(例:製品デモを申し込む、サービス資料をダウンロードする、など) |
もしヒアリングシートを用意する時間がない場合は、最低限のフィードバックを求める際に、必ず「こういった状況のため、このような意図で制作しました」と申し送りを添えるようにしましょう。
申し送りの例文
このホワイトペーパーは、〇〇という課題を抱える新規顧客の獲得を目的としています。
特に、△△という情報に価値を感じてもらえるよう、専門用語を避け、図解を多くしました。
この点を踏まえてフィードバックをお願いします。
説明は地味で手間もありますが、これを怠ると不毛な調整のやり取りが続き、成果が出るまでの時間もどんどん長くなってしまいます。
ホワイトペーパーは、作って終わりではなく、適切なフィードバックを通じて改善し、ターゲットに届けることで初めて成果に繋がっていく。
そのため、フィードバックの質を高めるには準備をしっかり行い、最短ルートで成果を目指していきましょう。