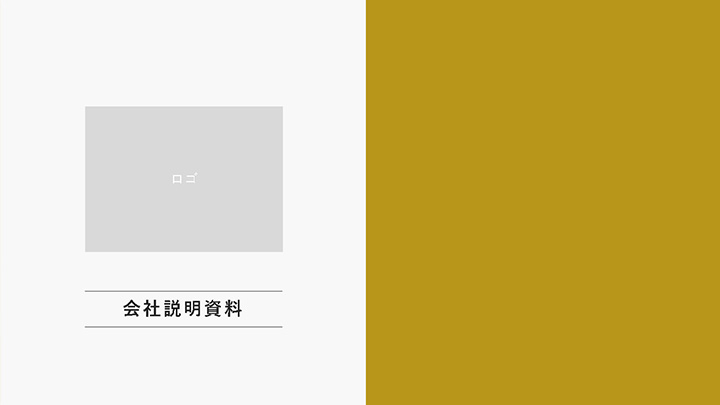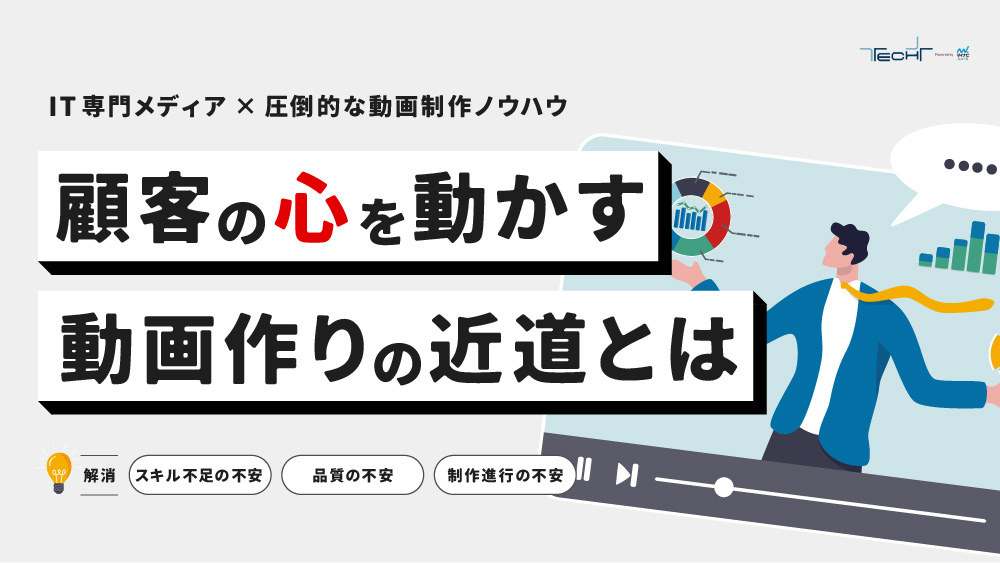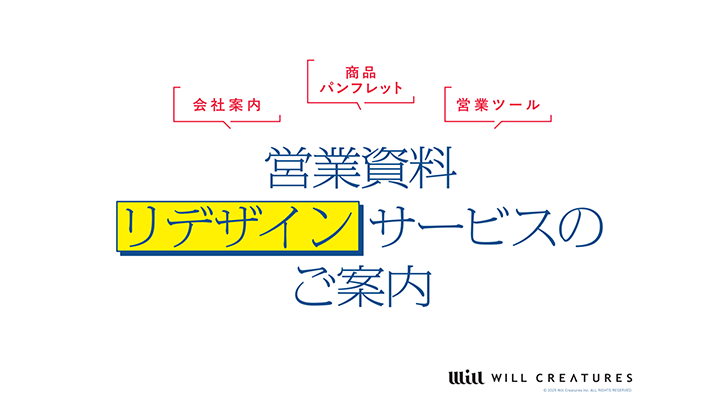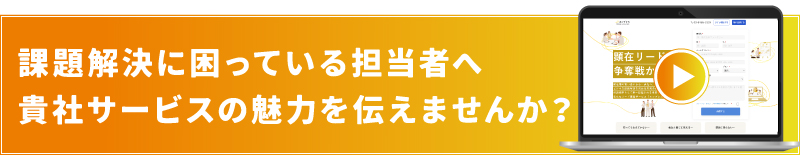いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。動画は制作するのもお金がかかりますし導入すべきか迷いますよね。メリット・デメリットをまとめました。
インターネットを使うと、至る所で見ない日はないと言えるくらい、色々なシーンで動画が使われていますよね。
動画があるとついつい見てしまう…これはあなただけではなく、他の人が見たとしても、つい手を止めて見てしまう魅力を動画は秘めています。
文字だけのコンテンツだと、ユーザーさんとのコミュニケーションに限界を感じるため、ユーザーさんを惹きつける動画を、どんどん取り入れていきたいところ。
動画のメリット・デメリットをまとめたので、見て頂けると嬉しいです。

「AI」に代替えできないホワイトペーパー制作とは
enpreth(エンプレス)は、15年以上コンテンツ・動画制作を行ってきた株式会社ファングリーが運営しています。初めて動画を作る、またはもっと別の動画アプローチを試したい場合など、ご相談は無料なのでいつでもお気軽ご連絡頂けるとうれしいです。
文字コンテンツと動画コンテンツの違い
動画を単純に表せば、連続した静止画、パラパラ漫画みたいなものですが、動画がここまで一般的な存在になったのか。
まずは通常のコンテンツ(記事コンテンツ)と動画コンテンツではどんな違いがあるのか、比較をしてみましょう。
| 文字コンテンツ | 動画コンテンツ |
|---|---|
| 視覚への刺激(静止画) 終わりが見えづらい サイト全体のボリュームが分かりずらい | 視覚への刺激(画面内の動き、人の動き、多数の色) 聴覚への刺激(音楽、声など) 全体像が簡単に把握できる(終わりが分かる) 見たい部分を自分で調整して見れる 真実性の高さ(人が出ていることで嘘っぽさが減る) 人の気配が強くコミュニケーション性が強い |
文字コンテンツ
→ 入ってくる刺激が少なく、不自由が多い
動画コンテンツ
→ 一瞬で入ってくる刺激と情報量が多く、ユーザー自身でコントロールもできる(自由度が高い)
テキスト < 写真(画像) < 動画 < リアルタイム映像
映像になり、時間軸を感じることができるようになっていくと、一瞬で手に入る情報量と価値の高さが変わってきます。※ だからこそテレビが今まで王者として君臨していたんだと思います。
情報量の違い
動画は文字コンテンツと比べても、受け取れる情報量に大きな差があり、一気に情報が入ってくるので脳の中でその処理ができず、思考が止まってしまうので見入ってしまうのではないかと思っています。(私の仮説)
たとえば、あなたもyoutubeを見たとき、ついつい見てしまい、さらにオススメされた別の動画も見続けてしまった経験はないですか?
私の場合は、早く仕事に戻るべきだと自分では分かっていたとしても、つい別の動画をポチっと押してしまいます…。
なぜこんなことが起きてしまうのかと言えば、写真と文字だけの情報量を比べると分かりやすいのですが、写真は1枚で多くの情報を含んでいるのに対し、文字だと何行も書かなければ説明ができませんよね。
写真の方が情報量が多く、さらに動画になると連続した写真(静止画)に対して、音や動きなども入り、情報量をさらに増やせる。
思考停止と没入感が紙一重
もしあなたが、人間が居て、言葉を喋っていて、背景は緑で、音楽も鳴っていて、文字が横から飛び出してきて…。たくさんの情報を一気に渡されたらどうでしょうか?ちょっとフリーズ、情報を処理しきれなくて思考が止まってしまいませんか?
悪い言い方をすれば思考停止、良い言い方をすれば他のことが考えられなくなるので没入させられる。集中できる。
動画になると情報量が多くなるからこそ、人を引きつけます。
これが誰もが体験している「ついつい現象」であり、動画最大の魅力。
動画の魅力というのか、魔力とも言うべきか……動画の価値を理解すると、動画の必要性をもっと感じてもらえると思います。
動画のメリット・デメリットとは?
オウンドメディア、広告、SNSなどに動画が使われることが一般的になってきていますが、みんなは動画のどの部分に惹かれて、使い始めているのか。
もっとも代表的なのは、Youtuberさんの人口拡大や、Instagram・Tik tokなどの動画アプリの普及によるところが大きいですが、そうではなくとも、いずれ動画がコンテンツ作りの基本になっていたかと思います。
しかし、動画はたいへん役立つ存在ではありますが、万能ではありません。
扱う前に、しっかりとメリット・デメリットを把握して、リスクも確認しておくのがオススメです。
動画コンテンツのメリット
ユーザーさんを惹きつけページからの離脱を防ぐ
人間は昔からの習性で、動くものに反応しやすいです。※ 大昔は、些細な変化の見落としが命を落とす時代だったので、動くものに敏感な遺伝子がそのまま残っていると言われています。
そのため、動画として動きをつけるだけで、遺伝子が目の前の「情報」を見逃さまいと「見る」ことに集中させるようにする。
ビジネスをするのであれば、見にきてくれたユーザーさんを何かしらの理由で離脱させないようにする必要があるので、そんな時に動画が役立ってくれます。
自由度が高い(三次元でコンテンツを作ることができる)
今までは、文字や画像だけの平面な形でしか情報提供ができませんでした。
動画の中では遠近感や奥行きなど、情報に対して空間を持たせることができます。
音も出せるので、視覚と聴覚への刺激も促し、三次元的な情報が作れるため、非常に自由度が高い情報提供ツールとなっています。
平面な情報に慣れてしまった人たちは、より刺激があり自由度が高く作られた動画を好む傾向があります。
一瞬で伝える情報量を多くできる
文字コンテンツの場合は、見せられても「文字」と「意味」いう情報だけなのですが、動画コンテンツでは、文字・色・音・人間・背景・動きなど、一瞬のうちに多くの情報を見せることができます。
ユーザーさんからにしてみれば「視覚」と「聴覚」をフルに使った情報収集のため、今まで10分かかっていた情報収集が、動画だと3分(仮)で済むようになる。
たとえばGoogleで検索すれば、あっという間にほしい情報が手に入りますよね?
情報取得の速さに慣れきってしまったユーザーさんは、すぐに情報が取得できない、文字コンテンツを長々見て情報を得ることにストレスを感じています。
動画は一瞬で伝えられる情報量が多いことで、情報取得のスピードを圧倒的に早めることができ、ユーザーさんの満足度を高める効果があるんです。
ユーザーさんが直感的に「良い」「悪い」の判断できる
動画は視覚で訴求可能であり、直感的にユーザーさんの反応を得ることもできます。
「この動画好きかも」と思ってもらえれば引き続き見てもらえる確率は高いですし、「この動画好きじゃないな」と思われてしまったら見てもらえなくなる。
良い悪い両方の反応を得られますが、良ければ継続して、悪ければ改善のきっかけにもなります。
すぐに反応が得られると、動画提供側の改善スピードも早くなるため、高速にPDCAも回していける。
早いサイクルで改善できるのも動画の魅力の一つです。
SNSでの拡散力を強めることができる(広告効果もあり)
各種SNSは、投稿される情報が膨大すぎて、一つのコンテンツに対する継続視聴が低く、じっくりと確認することはされません。
そのため、SNSの投稿では一瞬のうちにどれだけ多くの情報をユーザーさんに届けられるかが勝負。
より反応を得るために、インパクトを出したり、感情に訴えかけるストーリーを作ったりして、ユーザーさんの気持ちを強烈に引き寄せます。
文字だけのコンテンツだと、ユーザーさんの心に訴求するための情報量が少ないため、動画という一瞬で大量の情報量を届けられる形がSNSとマッチングしているんです。
ユーザーさんの心を掴むと、SNSの特性によって多く方に情報が拡散されて、広告の効果も期待できます。
信頼性を得やすい
インターネット上には情報が溢れすぎていて、何が正しくて間違っているのかも分かりづらい状況になっています。
さらに、フェイクニュースなども出回っている。
このような状況の中、ユーザーさんに信頼してもらえる情報を作るためには、真実であることを証明しなければいけません。※ ここでいう真実とは、嘘がないこと。
信頼を得るためには、何が言われているかより、誰が言っているのかが重要。
動画では「誰」が「何」を「どうして」発信しているのか伝えやすく、情報提供者本人が出ていればなおさら信頼性を得やすくなります。
インターネットの情報に不安を抱えているユーザーさんにとって、動画の情報は不安を解消するために、重要な情報取得ツールの一つなんです。
コンバージョン率を高めることができる
コンバージョンはユーザーさんが感じた「期待」や「信頼」によって得られる成果。※ コンバージョンとは、お問い合わせ・電話・フォーム送信・メルマガ登録・購入などの成果を表す言葉。
期待や信頼を感じてもらうためには、それに必要な情報を提供しなければいけないのですが、提供した情報を全てユーザーさんが見てくれるとは限りません。
そのため、短い時間で信頼できる多くの情報提供ができる動画は、コンバージョン率を高める効果的な方法となります。
記憶に残りやすい
人間の記憶は、短時間だけの情報を記憶する「短期記憶」と、長い期間保持される「長期記憶」の二つが存在します。
コンテンツを頑張って作っても、一瞬で忘れ去られてしまっては意味がありません。
通常は短期記憶で情報は入ってきますが、長期記憶の中のある「エピソード記憶」によって、長い間、記憶を残し続けることができる。出典:記憶の仕組み
エピソード記憶は、情報取得時の体験や感情と一緒に記憶に入ってくるため、瞬間的な記憶以上に残りやすくなるんです。
文字だけのコンテンツだと、感情の揺れ幅もそう大きくはない…。
動画を使ったコンテンツだと、感情は大きく動き、その時の体験と一緒に記憶されるため記憶に残りやすくなる。
覚えてもらえる確率を高くすることが可能な動画は、文字コンテンツよりもメリットは高いです。
メリットまとめ
- 伝達スピードが早い
- 一瞬で多くの情報を伝えられる
- 信頼性を高めることができる
- 利益につながるコンバージョン率を高めることができる
- 記憶に残りやすいので覚えてもらいやすい
- SNSで広告効果を期待できる
文字コンテンツは全体像も分かりづらく、最初は断片的な情報しか分からないので離脱されやすいのですが、動画があると一度立ち止まって見る姿勢へ強制的に変えてくれます。※ 記事だとパッと見、どのくらいの長さか分かりませんよね。
これらのメリットを活かし、動画を有効活用していきましょう。
動画コンテンツのデメリット
本格的な動画を作るためにはスキルや時間が必要
動画の撮影、編集には、それなりの知識やスキルが必要となりますが、動画制作を行なっていない企業では、社内に制作スキルをもつスタッフさんはいないことが多いです。
また、社内で新しく動画を使いたいと思っても、一から勉強できるような体制にもなっていないのと、スキルを習得するのに時間もかかる。
このような状況では、ノウハウも貯められず、思ったような動画活用ができないため、なかなか動画作りを進めることが難しいかもしれません。
たとえ動画が作れたとしても、専門知識がない人が作れば、十分な効果が得られない場合もあるため、動画を作るには専門性が必要なことも覚えておいて頂ければと思います。
動画の必要性はどんどん高まっている、だけど社内では作れない……そうなったら、動画制作を外注するしかないですよね。
せっかくお金をかけて作った動画を何かしらの事情で取り下げる場合もある
いくら頑張って作ったとしても、何か倫理的に欠けていたり、周りからの批判が多くなってしまうと、作った動画を取り下げる必要も出てきます。
それだけでなく、社内スタッフをキャスティングしたけど、退職に伴って動画を削除しなければいけない場合も。
作った当初はいいかもしれませんが、動画公開後に何かしら取り下げの原因が発生する可能性もあるため、あらかじめそれらの原因が発生しないよう段取りを組んでおくのがオススメです。
取り下げの原因としては、
- 時代に合わない、または倫理的に炎上や批判を受ける (youtuberさんとのタイアップでも同様)
- スタッフの退職に伴って(撮影時に掲載の条件を定めておく必要あり)
- 時期がくれば変化してしまうもの(古いデータなど)
この他にもありますが、取り下げ理由が多い内容を記載してみました。
私が携わっている事業では、自社スタッフさんを活用した動画を多く作っていたので、退職に伴って多くを削除した経験が…。
その動画を掲載していたページのコンバージョン率が高かったので、悲しい気持ちでいっぱいにもなりました。
動画掲載後のリスクも考えておくと、私みたいな失敗をしないと思うので、できるだけ考えておいてほしいです!
安い動画の場合は他社も作りやすいのでコモディティ化(品質の同質化)が起こる
動画は撮影や編集、またはキャスティングなど、色々な人を動かすため、それだけ費用も高くなります。
高いお金が出せないと、格安プランで動画を作ってもらったり、何かテンプレートを使うことで安く動画を作れるサービスを使ってもいいかもしれません。
しかし、安い価格にはそれなりの理由があり、特にオリジナル性を省くことで安くしている場合が多いです。
安さを追求していくと、同じような品質、同じような見せ方も多くなり、他と被ることが多くなってくる。
品質が同質化してくれば、他と比べても、あなたの会社を選んでもらう理由も少なくなってしまいますよね…。
お金を出して作った動画が、全く役割を果たしてくれない事態にもなるため、格安動画にはそれだけリスクがあることを覚えて頂ければと思います。
オリジナルを追求すると費用が高くなっていく
競合他社とは被らないようにするためには、自社の強みや特徴を出した、自分たちの「らしさ」を表現する動画を作ることが一番です。
しかし、その一企業に特化した内容の動画を作ろうとすれば、社内ヒアリングや企画構成などから、じっくりと対応していくため、それなりの時間もかかる。
それだけでなく、企業の「らしさ」を追求するには、音楽を用意したり、動画内に出演してもらうスタッフさんまたは役者さんの手配など、人が大きく広い範囲で動くことになります。
人が動けばそれだけお金も掛かるのですが、撮影した内容を編集して、まとめ上げるのもまた大変。
今では、撮影した内容を単純に編集するだけではなく、インタラクティブ動画と呼ばれる、ユーザーさんとのコミュニケーションを意識した動画もあります。
動画内で気になった商品の説明がポップアップで確認できたり、ストーリー仕立てになって選択肢を選ぶごとに、別のルートへ進めていけるようなものも開発されています。
企業の「らしさ」やオリジナルを追求していくと、それなりのお金が掛かることは覚悟しなくてはいけません。
デメリットまとめ
- 本格的な動画は専門知識やスキルがないと作れない
- 掲載後に取り下げのリスクもある
- 格安動画は内容が似てしまう
- 外注すると費用が高くなる
- オリジナルを追求すると高くなる
これらのデメリットを覚えて頂き、あなたにあった動画作りをして頂ければと思います。
目的別の動画作りの進め方
あなたが動画を作りたいと思っているように、他の方もさまざまな理由で動画を作りたいと思っています。
その中でも大きく3つのタイプで、動画を作りたい理由を分けてみました。
- 汎用性重視 :webサイトやSNSなどにも活用できる汎用性の高い動画が作りたい
- スピード重視:欲しい時に動画を用意して迅速に展開したい
- 品質重視 :ブランドを高めたり事業にインパクトが大きい動画を作りたい
それぞれどんな作り方になるのか、詳しく見ていきたいと思います。
汎用性重視 :webサイトやSNSなどにも活用できる汎用性の高い動画が作りたい
下記のような場合、汎用性重視で動画を作るのがオススメです。
- webにもSNSにもセミナーにも使いたい(色々使い回したい)
- 予算があまり取れない
- 動画を作成する頻度が低い
一度動画を作ったら、さまざまな媒体で使いたかったり、何個も動画を作成しないのであれば、急がずあなたのペースで進めていく作り方が合うと思います。
予算も何回も取れなかったりすると、作りたくても動画は作れないので、一つ一つを丁寧に作っていき、汎用性を持たせた動画が便利。
例えば、会社紹介や商品・サービス紹介の動画を作り、webサイト・SNS・セミナー・お客様への説明の際など、さまざまなシーンで使えるように作る。
または、それぞれの活用シーンごとに用意する。
一通り、事業運営で活用できる動画が作れてしまえば、ある程度は使いまわせたり、継続的に使えるので、追加でかかる動画のお金は少なくなります。
多く作れないからこそ、さまざまなシーンで使えるような動画を作り、活用していく形がオススメです。
スピード重視:欲しい時に動画を用意して迅速に展開したい
下記のような場合、スピード重視で動画を作るのがオススメです。
- 事業展開が早い
- スタートアップや新規事業を展開している
- 圧倒的な量でライバルを突き放したい
- 社内リソースで高速にPDCAを回していきたい
例えば、動画制作を外注で作ろうと思った場合はコミュニケーションロスなどが発生し、必要な時に動画が間に合わなくなります。
納期や品質がコントロールしづらいのも影響して、旬なタイミングで動画が出せないのは、機会損失でしかありません。
ビジネスのスピードが日に日に早くなっているのを横目に、指をくわえて待っている状態にもなってしまう。
このようにスピード重視の場合は、自分たちで動画を高速に生み出せる体制が必要となります。
参考として、近年急激な成長を遂げているDELISH KITCHEN(運営:株式会社エブリー)と、クラシル(運営:dely株式会社)の成長要因がまさに、動画のスピード制作。参考:日経トレンディネット レシピ動画成長の理由 プロが制作、視聴は1分
DELISH KITCHENさんもクラシルさんも、動画の企画から制作までを社内スタッフさんでワンストップ対応をしており、動画の品質とスピードを担保している状況。
もし、動画制作を外注化してしまうと、細かいクオリティの調整や、必要なタイミングで公開もできない。
何か変更するにも、動画制作会社の対応を待たないといけないので、事業側はもっと前に進みたいのに、無駄に止められる状況が作られてしまってストレスばかりが増えることに。
そのため、スピード制作を実現するには、自社内に動画制作のチームを作る、または動画制作を簡単にしてくれるサービス(月額制のものなど)を契約して、自社スタッフで動画を作る体制を整えるのが勝機となります。
品質重視 :ブランドを高めたり事業にインパクトが大きい動画を作りたい
下記のような場合、品質重視で動画を作るのがオススメです。
- 圧倒的なオリジナリティと品質で競合他社を寄せ付けない動画を作りたい
- 動画を大規模に展開したい
- 絶対的な成果を打ち立てたい
競合他社が強かったり、一気に認知度を向上させたい場合は、魅力を高めるため品質重視で動画を作るのがオススメです。
品質を求めれば、オリジナリティも追求していくことになるので、企画の段階から時間をかけていく。
時間をかければ、その分かかるお金は高くなります。
動画作りが初めての場合は、費用対効果も分からない段階で、いきなり100万円(仮)以上の予算は出ないと思うので、品質を求めるのであれば社内の根回しや協力は必須。
慎重に進めながら予算を獲得し、品質重視の動画を作っていきましょう。
よくある質問とご回答
動画を作りたい!から始まって、動画作りの基礎的な情報を見て頂きましたが、それでもまだ疑問や不安もありますよね。
基礎から少しだけ発展して、よくある質問とその回答もまとめてみました。
オシャレな動画じゃなくてもいい?
動画を作ろうと思うと、オシャレで反響が良さそうな内容にしなければいけないの?とプレッシャーに感じるかもしれませんが、全くそんなことはありません。
確かに動画で情報を届けたい人が「オシャレ」を気にしている人であれば、そのように作る必要もあるかもしれませんが、最優先にするのは動画で情報を届けたい人に伝わる内容にすること。
オシャレが必ずしも必要ではないので、ご安心ください。
メンテナンス代は掛かるの?
動画を一度作ったら、そのあとは何もしなくていいの?と不安になりますよね。
基本的に動画は一度作ってしまえば、そのまま使い続けることが多いので、メンテナンス代はほぼ掛からないと言えます。
動画は撮影素材が必要なことが多く、その素材があるからこそ作れた動画ならば、取り直しや公開後の調整は難しいので、ほぼそのまま公開し続けるか、ダメなら公開を取り下げる形。
ただ、部分的なマークの交換や、映像・音声などに関わらない部分であれば、比較的調整は可能です。
新しく作り直すより、少しの調整で済むのであれば安く収まるので、その場合は調整を依頼して費用を抑えた形で動画を使えるようにするのがオススメです。
パソコン購入時に入っている無料編集ツールで作るのはダメなの?
windows10で使えるフォトというアプリや、Macで使えるiMovieなどを使って動画を作ることも出来ます。※ windowsではムービーメーカーという編集ソフトがありましたが、今は使えません。
これらの編集ツールは無料ながら様々な機能がついており、iMovieに関して友人の結婚式など、簡易的な動画公開の場で使われていますが、やはり動画の品質を高めるのであれば、専門のソフトを使ったり、編集のプロに頼んでもらった方が確かな品質で作れます。
あなた自身で挑戦してみて、ダメならばプロに頼む。
または、動画の編集が簡単にできるサービスを利用することも検討して頂くのがオススメです。
動画の寿命は?
動画は一度公開すれば、そのまま使い続けられるので、寿命という概念はないかもしれません。
しかし、自社スタッフの退職や、出演者の行動に問題が発生した場合など、その動画内に含まれる情報に、何かしらのトラブルが発生したならば、公開を取り下げなければいけない場合も。
最初から考えられるリスクは最初から潰しておき、できるだけ長い間公開できる企画にして、動画を作って頂くのがオススメです。
作るか分からないけど、見積もりを頼むだけでも大丈夫ですか?
動画制作会社さんはどこも、相見積もりが前提となっていることを把握しているため、見積もりだけでも問題ありません。
しかし、見積もりは無料でも、制作会社さんにしてみたら、調査をしたり見積もりを作るのも時間がかかるので人件費がかかっています。
無理難題を伝えて見積もりをとると、次回に見積もりをお願いしても断られてしまう場合もあるため、ある程度節度を持った見積もり依頼が必要となります。
自分たちで撮影した素材を使いたい場合も可能ですか?
すでに撮影した素材があれば、その内容で動画を作ることも可能です。
どの動画制作会社さんも臨機応変に対応してくれるので、まずは気軽に相談して頂くのがオススメです。
撮影のみでも大丈夫?
撮影だけプロに頼んで、実際の編集は自社内で行う場合でも大丈夫です。
動画作りでは「撮影」の品質が、動画全体の品質にも関わってくるので、自社内で編集が対応できるのであれば、品質の良い素材を手に入れるために、動画制作会社へ「撮影」のみの依頼をするのもいいと思います。
動画制作からDVDの制作も可能ですか?
動画の制作だけでなく、作った動画をDVD化したりすることも可能です。
ただ、動画制作会社によっても、DVD制作まで行なっていないこともあるので、どこまで対応できるのか予め確認頂くのがオススメです。
有名な声優さんや俳優さんもキャスティング出来ますか?
キャスティングは可能ですが、有名な方をキャスティングする場合は、それなりの費用がかかります。
予算が十分にあるなら、より魅力的な動画にもなると思うので、ご検討頂くのもオススメです。
動画を作るには、どのくらいの日数が必要ですか?
簡易的な30秒〜1分程度であれば2週間前後で出来てしまう場合もあります。
1〜3分ほどの動画であれば、使う映像素材やナレーターさんのキャスティングなど、企画〜撮影〜編集という流れで進むのと、人が大きく動くため1~2ヶ月かかることも。
どんな内容の動画を作りたいかによっても日数は変わってくるため、30〜100万円ぐらいの内容だと1ヶ月以上かかると覚えて頂くのがいいかもしれません。
動画を作るなら、何分にすればいいの?
一つのコンテンツに対して集中して視聴できる人はあまりいないので、15〜30秒ぐらいの動画に人気がありますが、企業が依頼する動画の多くは、費用もかかることから、1〜3分程度の動画となっているため、基本は1〜3分程度だと覚えて頂ければいいかもしれません。
現在は短い動画の人気を示すかのように、2020年8月5日に、インスタグラムで15秒の尺で作れる「リール(Reels)」機能が新たに追加されました。
しかし、15秒という短さで、伝えたい情報を全て伝えることはできないのと、ユーザーさんの興味関心を強烈に作り出すことができれば、時間は長くなっても見てもらえます。
最後に。
コンテンツ作りにおいて、文字主体の記事作りから動画作りに変わったとしても、考え方は何も変わりません。
ユーザーさんが動画によって、何の価値を感じてくれるのか。
動画を作るため基礎を覚えて頂きながら、ユーザーさんに価値を届けられる動画作りに役立てられる情報になれれば嬉しいです
相手に届く価値を最優先にすればきっと、ライバルよりも有利になる動画が作れて、ビジネスを加速させることができると思います。