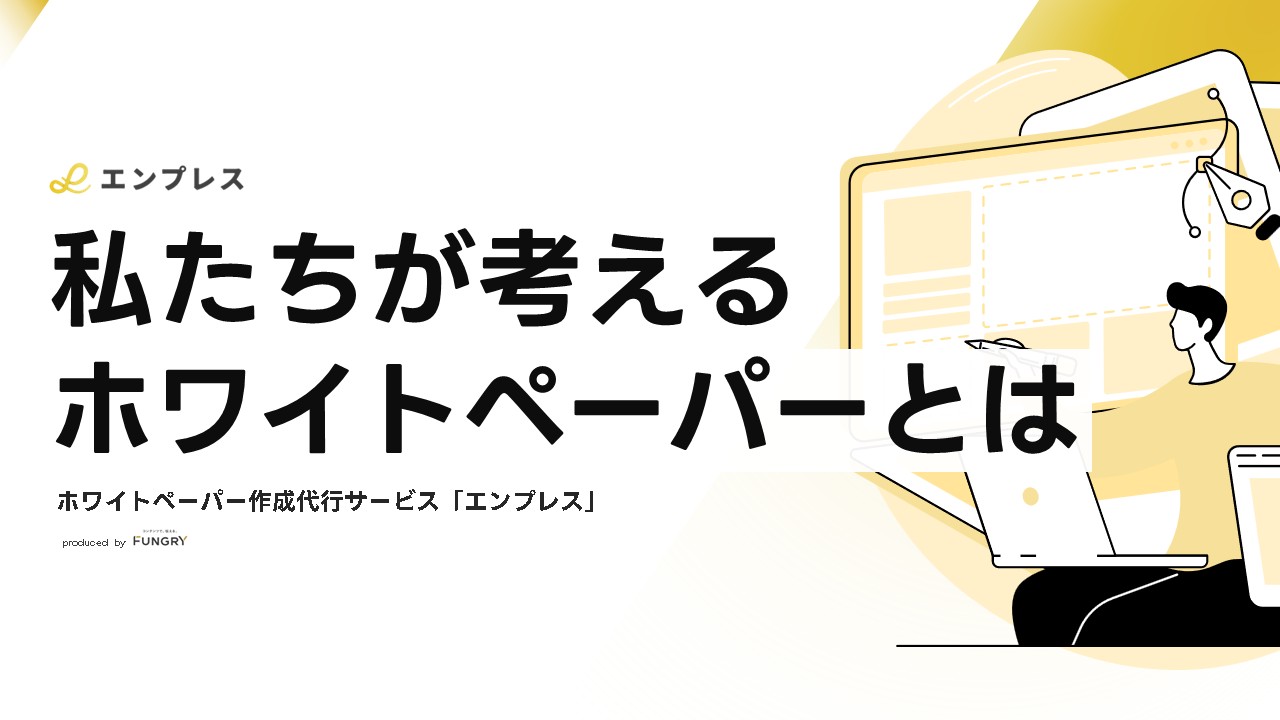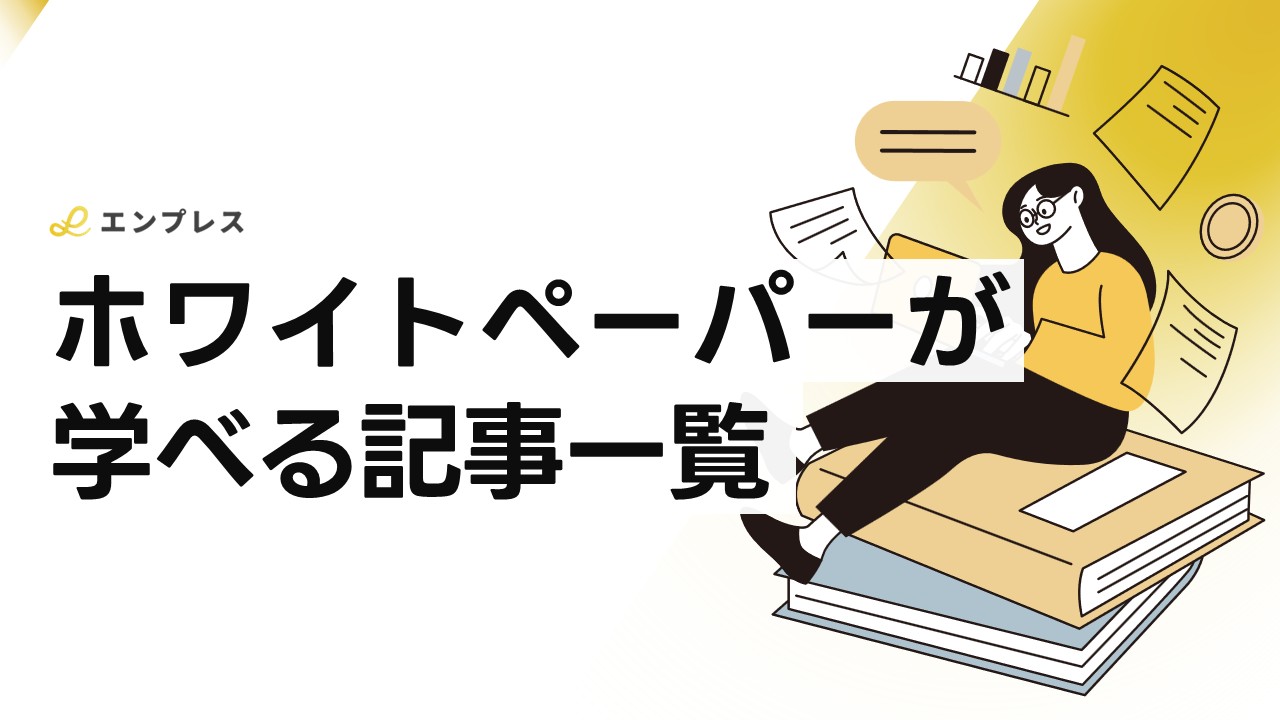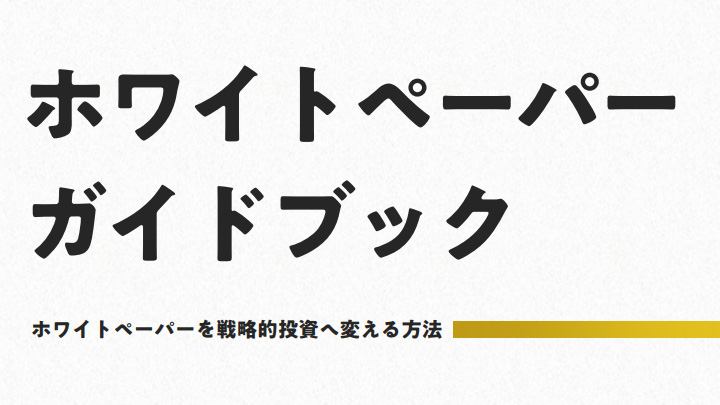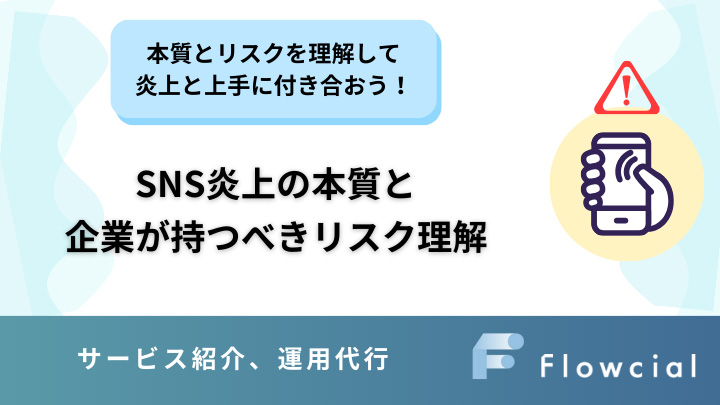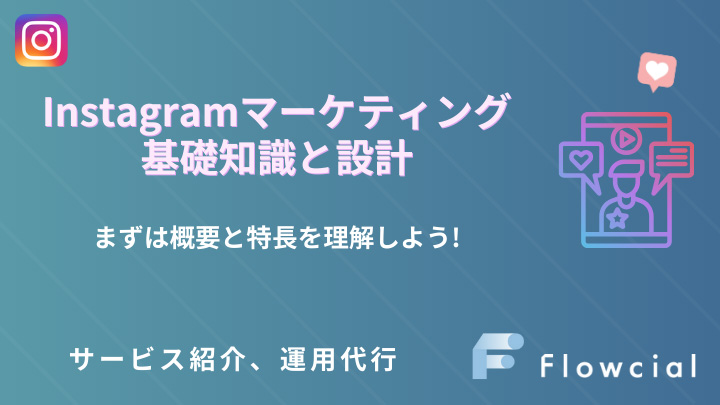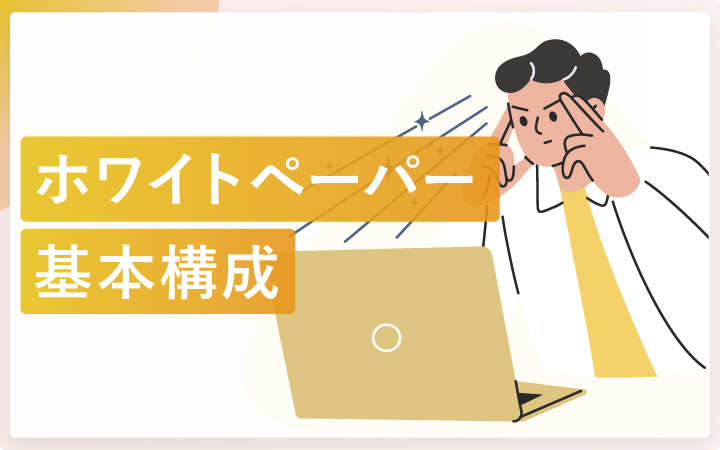
いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーを作るための基礎、それも根幹となる構成について、知っておきたい情報をまとめています。
「ホワイトペーパーを作りたい。」
「だけど、何を、どの順番で、どのくらいの情報量で構成すればいいのか分からない。」
そんな不安を抱えたまま、PowerPointを前に手が止まってしまった経験はありませんか?
とくにホワイトペーパー制作が不慣れな場合、最初の一歩となる“構成”が分からず迷子になりがちです。
しかし、実はホワイトペーパーの構成には「型」が存在しており、基本を理解すれば、どのテーマでも応用できるようになります。
本記事では、ホワイトペーパー制作の根幹となる「構成」に焦点を当て、その重要性から具体的な組み立て方までを徹底的に解説。
あなたのマーケティング活動におけるホワイトペーパーの効果を最大化するため、役に立てられれば幸いです。
- 目次
- ホワイトペーパーの構成とは?基本的な考え方
- なぜホワイトペーパーに構成は欠かせないのか?制作側・読み手側のメリット
- ホワイトペーパーを構成する基本要素:スライドの種類
- ホワイトペーパーの基本構成(課題解決型)
- テーマ別ホワイトペーパー基本構成への応用
- ホワイトペーパー構成に関するよくある質問
- 最後に
ホワイトペーパーの構成とは?基本的な考え方
ホワイトペーパーにおける構成とは、単に情報を羅列するのではなく、作り手(企業)と読み手(顧客)双方にとって必要な情報を最適なバランスで配置し、両者の目的達成をスムーズに促すための大きな流れを設計することです。
この構成作りには、主に「どのような情報(スライドの種類)を含めるか」と「それらの情報をどのような順序で見せるか(スライドを見せる流れ)」の二つの要素が不可欠となります。
これらが揃うことで、初めてホワイトペーパーは効果的な形が成せる。
一見難しそうに思えるかもしれませんが、実は基本的な成功パターンが存在するため、その基本さえ押さえれば、どのようなテーマのホワイトペーパーでも自信を持って制作できるようになります。
なぜホワイトペーパーに構成は欠かせないのか?制作側・読み手側のメリット
そもそも、なぜこれほどまでに構成が重要視されるのか。
それは、構成案なくしては、適切で分かりやすいホワイトペーパーは成り立たないから。
重要性が理解できるよう、まずは私たちの日常生活にたとえて、構成がどのように関係しているのか見てみましょう。
例)料理
材料を買う ⇒ 調理の順番を決める ⇒ 下ごしらえをする ⇒ それぞれ調理していく ⇒ 味を調える
例)プラモデル制作
プラモデルを買う ⇒ 説明書見る(パーツ切る)⇒ 小さい部品を組み合わせていく ⇒ 部品を組み上げていく ⇒ シール貼りや色塗り
このように何をするにも、小さな要素を組み合わせ、段階を経て最終的なゴールにたどり着いています。
ホワイトペーパーの構成は、まさにこの「段取り」や「流れの軸」を整える役割を果たしており、構成が明確でないと、どの情報をどこに配置し、どのように見せれば読み手に伝わるのかが分からなくなり、制作の途中で迷子になってしまいます(特に複数人で制作する場合)。
しかし、しっかりとした構成があれば、制作チーム全体で現在地とゴールを共有でき、一貫性のあるブレないコンテンツを作り上げることが可能に。
これは作り手にとって、効率的かつ質の高い制作を行う上で非常に大きなメリットです。
一方、読み手にとっても構成は非常に重要で、構成が整っているホワイトペーパーは、話の流れが論理的でスムーズなため、内容を無理なく深く理解できます。
知りたい情報へスムーズにたどり着け、自身の課題解決に向けた道筋が見えやすくなる。
このように、構成は作り手と読み手の双方にとって、目的達成を強力に後押しする存在なのです。
もし構成を用意しなかったら?
逆に、構成を考えず手当たり次第に情報を盛り込んだり、話があちこちに飛んだりするホワイトペーパーは、読み手を混乱させ、「結局何が言いたいのか分からない」印象を与えてしまいます。
これでは、せっかく時間とコストをかけて制作し、リード獲得・ナーチャリングのチャンスとして用意したにも関わらず、期待した成果は得られず、費用対効果が低下。
さらに、分かりにくいホワイトペーパーを、手間をかけてダウンロードした読み手は、企業に対して不信感やマイナスイメージを抱きかねません。
作り手にとっては何一つ良いことがない状況と言えますよね。
ホワイトペーパーの構成とは成功パターンである
ホワイトペーパーの基本構成そのものが、長年の知見に基づいて構築された「成功パターン」である点も重要です。
もちろん、テーマやターゲットによって多少のカスタマイズは必要ですが、根幹となる流れは大きく変わりません。
この成功パターンに沿って制作することで、お客様にとって最も理解しやすく、かつ作り手も効率的に制作を進めることができるのです。
特に企業内でマーケティングリソースが限られている場合、ゼロから全てを考えるよりも、型に沿って制作を進めることが、迅速に成果を出すための有効な手段となります。
さらに、現代のマーケティングにおいては、一つの万能なホワイトペーパーで全てのターゲットに対応することは、非常に難しくなっている。
そのため顧客セグメントや関心事に合わせて、複数のホワイトペーパーを用意することが効果的なのです。
多種多様なホワイトペーパーを効率的に制作するためにも、基本となる構成パターンを理解し、使いこなせるかどうかが、時間がない中で成果を出すための鍵となります。
ホワイトペーパーの構成は、まさにその骨組みであり、ここがしっかりしていなければ、どんなに素晴らしい情報も読み手に届きません。
ホワイトペーパーを構成する基本要素:スライドの種類
ホワイトペーパーを実際にページとして構成していく上で、基本となるスライドの種類は以下の通りであり、これらは多くのホワイトペーパーに含まれる基本的な要素となっています。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 表紙 | 読み手の興味を引きつけ、続きを読みたいと思わせる最初の扉。 |
| 目次 | 全体の内容とボリューム感を把握させ、安心感と読み進めやすさを提供。 |
| 内容 | 課題・解決手段・根拠などホワイトペーパーの中心となる、読み手が知りたい情報や企業が伝えたいソリューションを盛り込む部分。複数のページで構成されます。 |
| CTA | 読み手に次の具体的な行動(問い合わせ、資料請求など)を促すための情報。※ CTAとはCall to Actionの略 |
| 会社概要 | ホワイトペーパーの発行元が信頼できる企業であることを証明するための情報。 |
要素が分かっていると、構成作りでは何を用意すればいいのか分かりやすくなります。
ホワイトペーパーの基本構成(課題解決型)
制作の基礎となる「課題解決型(ノウハウ系)」のホワイトペーパーの基本的な流れを、読み手の心理と行動に沿って段階的に解説していきます。
この流れを理解することが、効果的な構成を組み立てる上で非常に重要。
課題解決型ホワイトペーパーの主な目的は、読み手が抱える課題の解決に役立つ情報を提供し、最終的に自社の製品・サービスへの興味を喚起してもらえた上で、商談に繋げる可能性を高めることです。
扱うテーマによって多少の変更はありますが、この基本形を押さえておけば応用が効く。
以下がその典型的な流れ(10ステップ)で、最初の7ステップは主に読み手の課題解決に焦点を当て、その後の3ステップで企業の目的達成に繋げます。
スライドの流れ
① 興味の引き付け
② 内容の全体感の把握
③ 課題の再認識
④ 現状維持のデメリット
⑤ 解決した際のメリット
⑥ 具体的な解決策
⑦ 解決できる根拠
———–ここまでがお客様の目的達成向けで、この先は企業側の目的達成向け
⑧ 解決に役立つ製品・サービスの紹介
⑨ オファーによる行動喚起(CTA)
⑩ 企業の存在証明
※ 各流れでスライドが2~3枚ほどになる場合もあるので全体とし10~20枚ほどを想定
フロー① 興味の引き付け
サンプル:表紙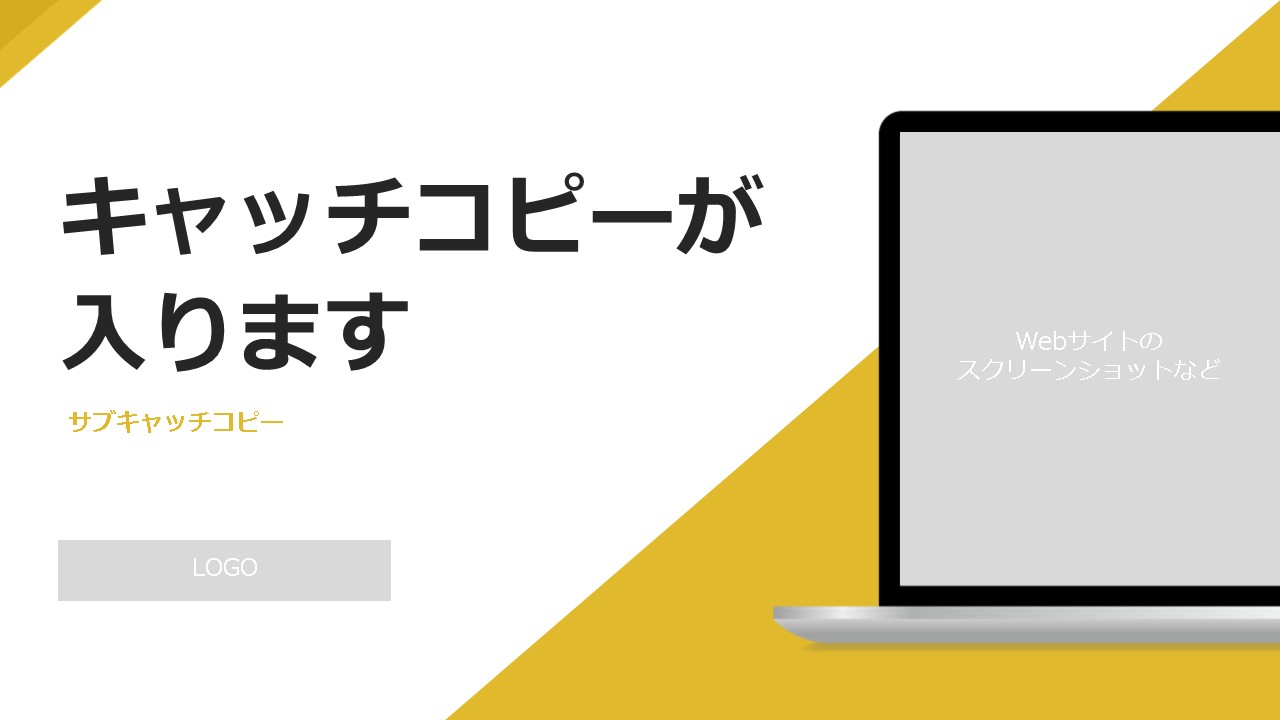
お客様は、自分が「今」欲しい情報、あるいは「いつか知りたいと思っていた」情報にしか意識を向けません。
ホワイトペーパーを手に取ってもらう最初のきっかけは、多くの場合、タイトルや表紙を目にした時です。
ここでいかに「これは自分にとって必要な情報だ」「読んでみたい」と思わせられるか、情報の「自分事化」を促せるかが、その後の行動に繋がるか左右します。
オンラインでのダウンロードなど、作り手側が受け身の形で読者の行動を待つ状況であれば尚更、最初のチャンスで読み手の心を掴めるかどうかが、ホワイトペーパー全体の成果を大きく左右する重要な勝負所となる。
表紙のデザインやキャッチコピーには、特に工夫を凝らす必要があります。
フロー② 内容の全体感の把握
サンプル:目次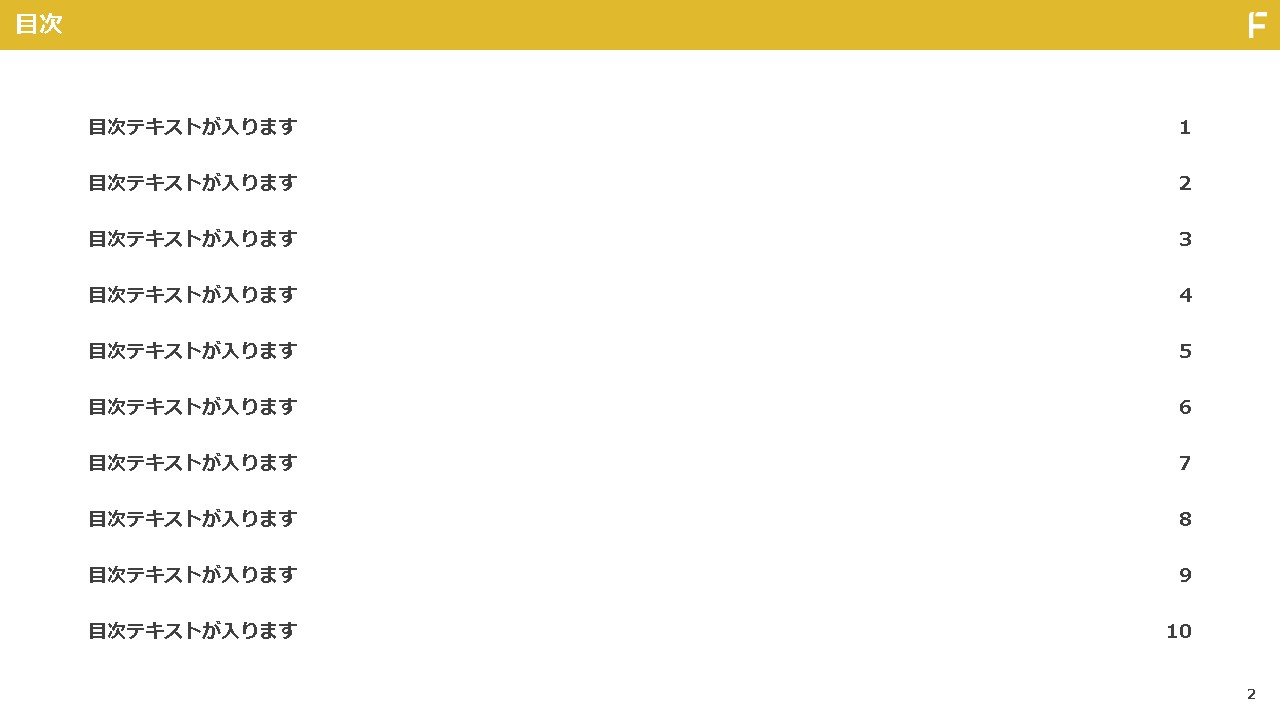
多くのホワイトペーパーは、ある程度のページ数(10ページ、20ページなど)になりますが、ダウンロードする前に正確なボリュームが分からない場合も多いです。
まるで書籍のように、冒頭に目次があることで、全体の構成や情報量、そして自分が知りたい情報がどこに書かれているかを事前に把握でき、読み手は安心して読み進めることができます。
内容の全体像を分かりやすく提示し、読み手の抱く潜在的な不安を軽減する配慮が求められます。
ただし、目次として必ず入れる必要性はないため、ターゲットに合わせて必要・不必要を検討していきましょう。
フロー③ 課題の再認識
サンプル:課題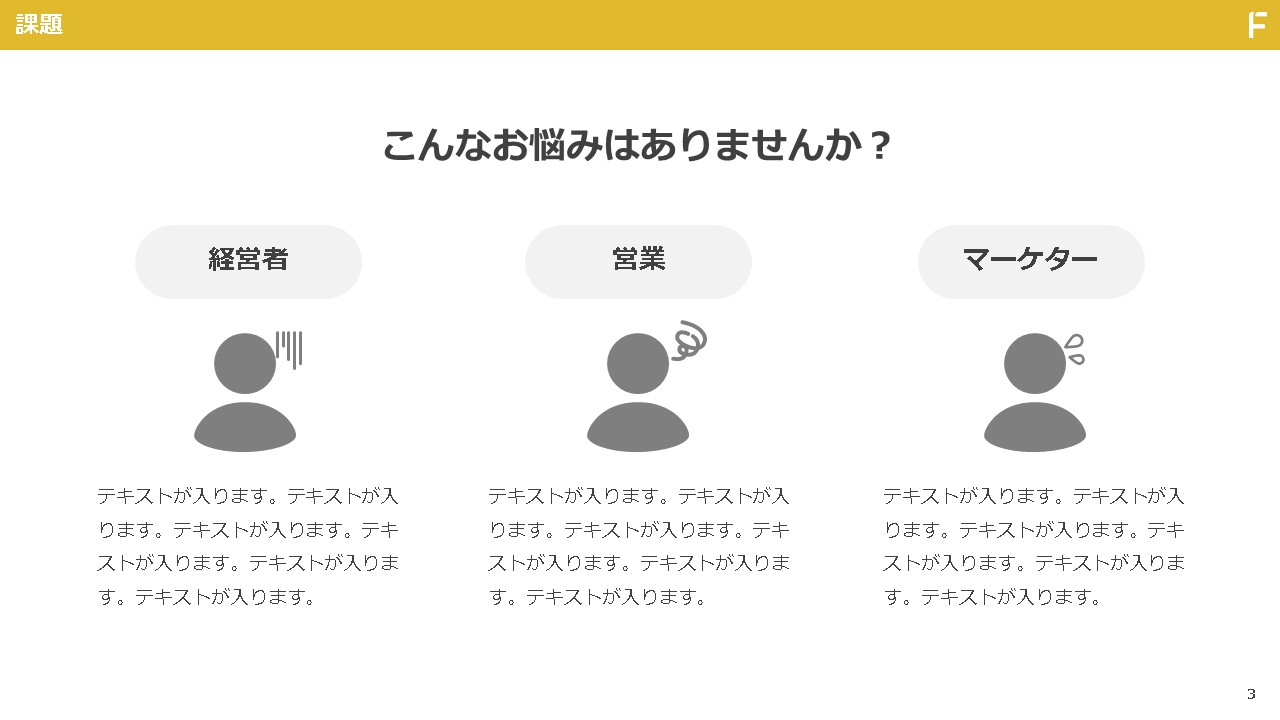
読み手自身が認識している課題は、往々にして氷山の一角に過ぎないことがあります。
一つの課題の背景には、それに紐づく様々な問題が存在し、何を根本的に解決すべきかが見えていない場合も少なくありません。
このステップでは、読み手が漠然と感じていた課題をより具体的に、そして潜在的な関連課題も含めて「改めてこれが自分の課題だ」「他にもこんな問題があったのか」と再認識できるような情報を提供します。
自身の課題が明確になることで、解決策やメリットに関する内容が、より一層「自分事」として捉えられるようになり、読み手の能動的な関心を高める効果があります。
フロー④ 現状維持のデメリット
サンプル:現状維持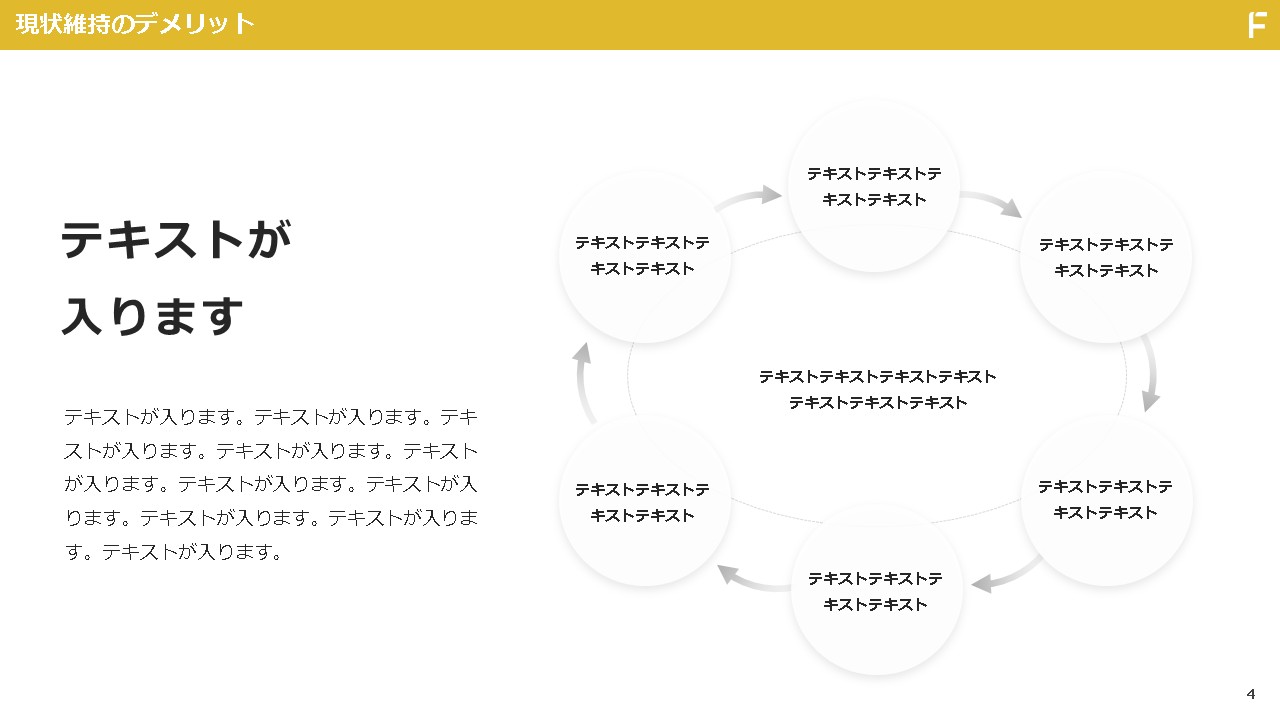
課題を解決せずに放置した場合、将来的にどのような不利益やリスクが発生するのかを、ハッキリ伝えます。
「今のままでいると、状況はさらに悪化する可能性がある」と伝えることで、読み手の「今すぐなんとかしなければ」など危機感による意識に引き上げを行い、課題解決の必要性を強く認識してもらいます。
これは、読み手の思考を「今」だけではなく「未来」にも目を向けてもらうことで、行動へのモチベーションを高めるための重要なステップです。
フロー⑤ 解決した際のメリット
サンプル:解決後のメリット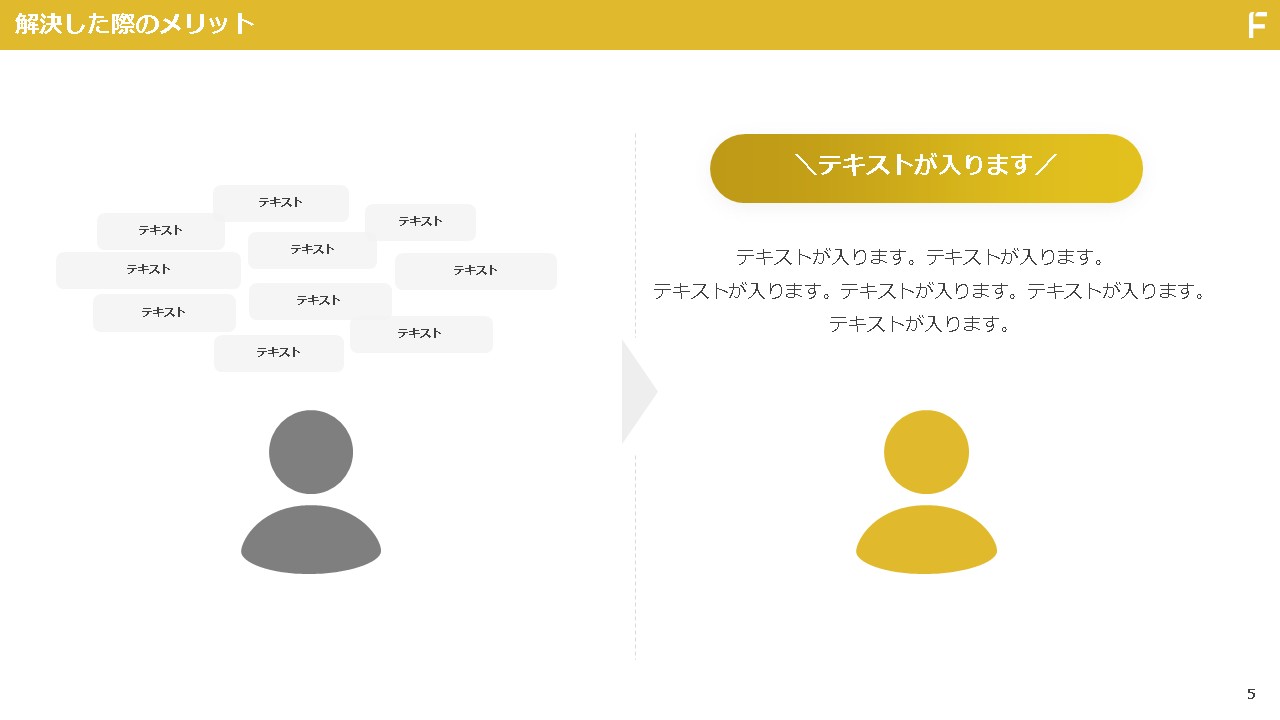
現状維持のデメリットの後に、課題が解決された場合にどのような明るい未来や理想の状態が待っているのかを具体的に示します。
「この課題を解決すれば、こんなに素晴らしい成果が得られる」「仕事や生活がこのように改善される」といったポジティブな未来像を描くことで、読み手の期待感を高め、「この後続く具体的な解決策を見てみたい」と思う意欲を掻き立てます。
たとえホワイトペーパーのページ数が少なくても、読み手の離脱を防ぎ、最後まで読み進めてもらうための工夫が必要です。
フロー⑥ 具体的な解決策
サンプル:解決策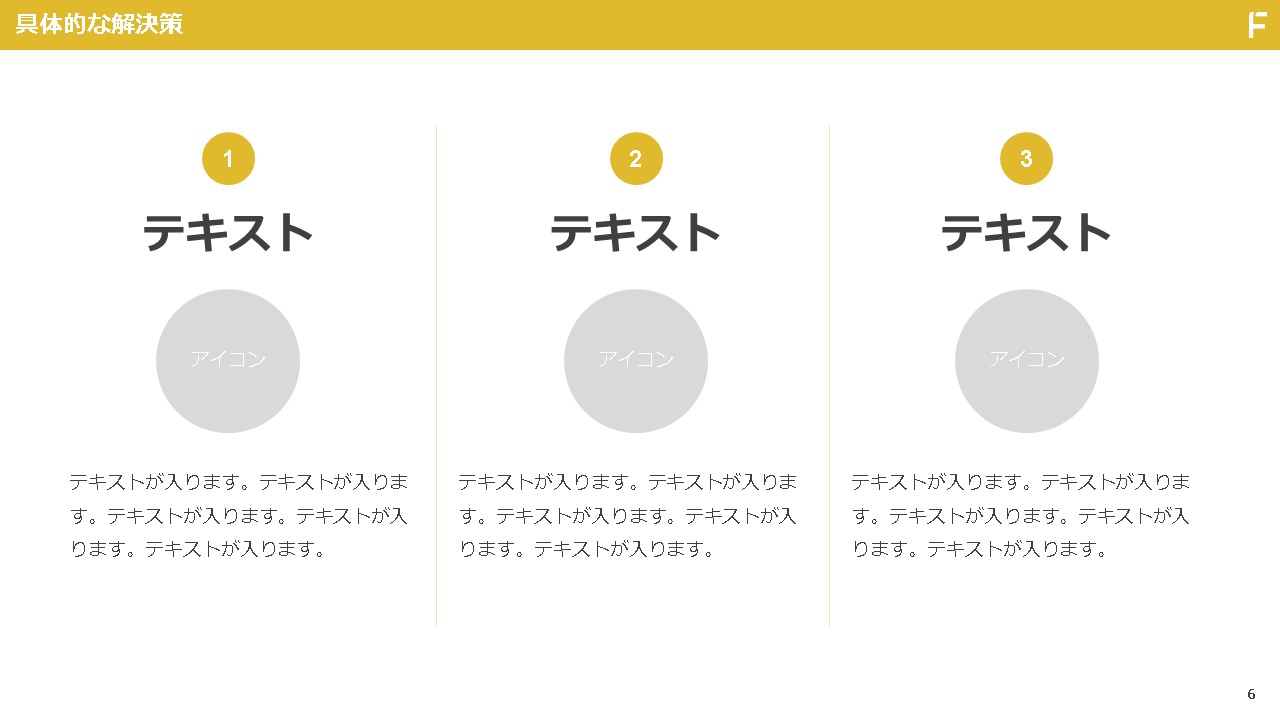
読み手が抱える課題を解決するための、具体的かつ実践的な方法を提示します。
この段階では、まずお客様自身の手元や、比較的容易に始められる範囲で実行可能な解決策を伝えることがポイント。
高額な投資や、大きな手間がかかるような解決策から入ってしまうと、心理的なハードルが高くなり、せっかくホワイトペーパーを読んでもらったのに「自分には無理だ」と諦めさせてしまう可能性があります。
お客様が自分で「これならできるかもしれない」と思えるような、取り組みやすい方法や考え方を解説してあげることで、解決への第一歩を踏み出すきっかけを提供します。
フロー⑦ 解決できる根拠
サンプル:根拠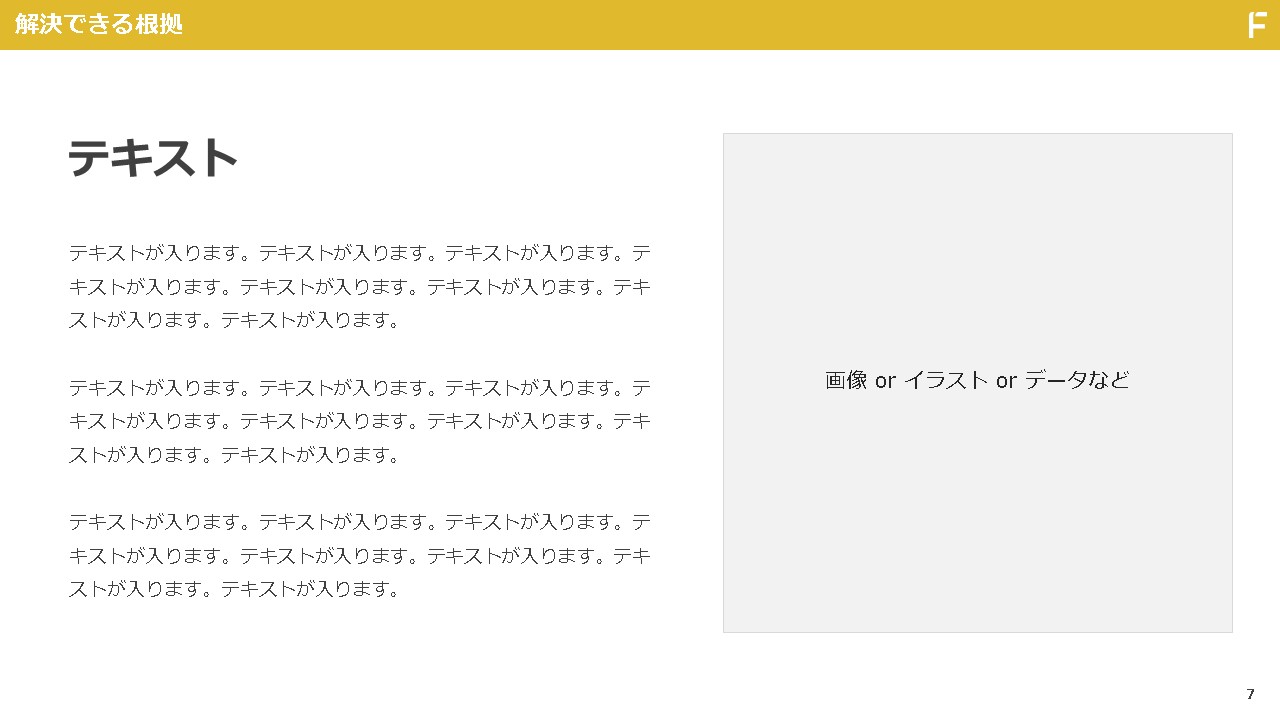
先ほど提示した具体的な解決策が、なぜ実際に課題を解決できるのか、その信頼性を示すための根拠を提示します。
第三者機関の調査データ、お客様の成功事例、専門家の意見、技術的な説明などがこれにあたり、納得のいく理由や裏付けが示されることで、具体的な解決策の有効性が高まり、読み手の納得感と信頼を獲得。
これにより、読み手は提示された解決策に対してより能動的な意識を持ち、行動に移しやすくなります。
フロー⑧ 解決に役立つ製品・サービスの紹介
サンプル:製品・サービス紹介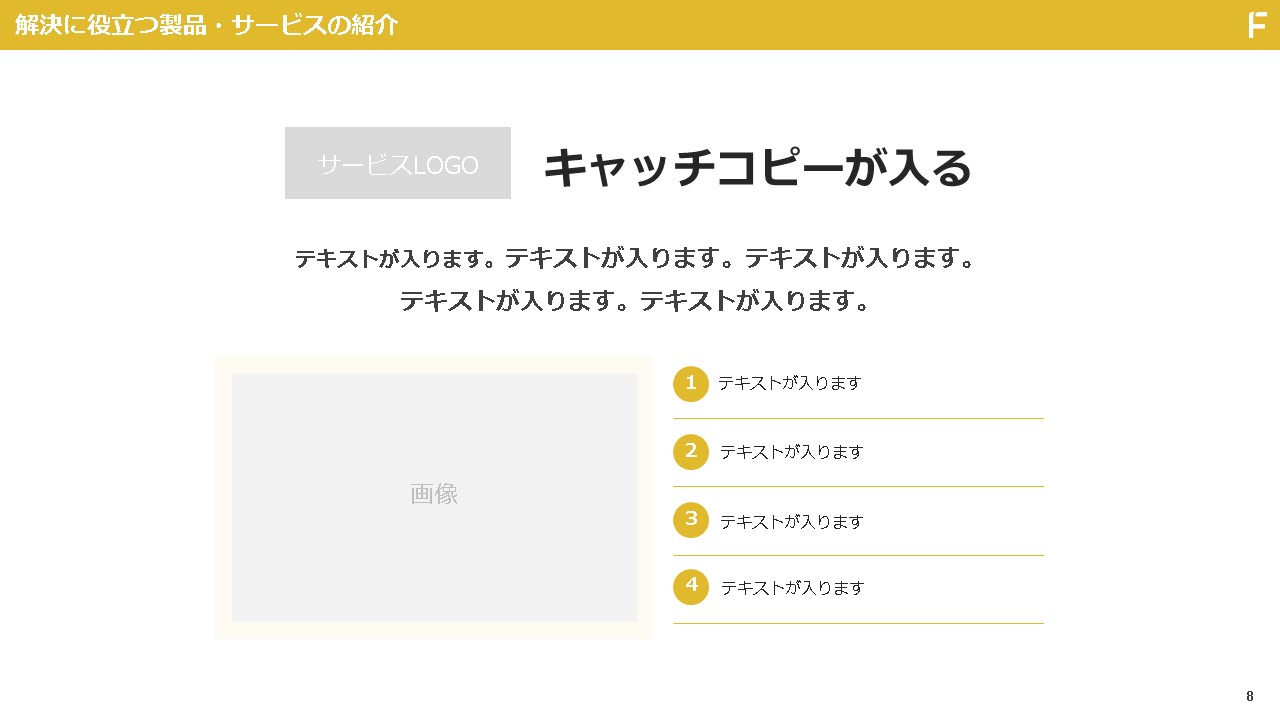
フローの①~⑦までで、読み手は自身の課題を再認識し、その解決策の方向性と根拠を理解しました。
この段階で、自社の製品やサービスが、先に提示した具体的な解決策をさらに効率的、効果的、あるいは比較的簡単に実現するための手段であることを紹介します。
「先ほどの解決策は有効ですが、当社の〇〇を使えば、もっと手軽に、より大きな成果を得られます」と、製品・サービスを紹介。
製品・サービス自体の機能説明だけでなく、それがどのように読み手の課題解決やメリット実現に貢献するのか、具体的に伝えることが重要です。
フロー⑨ オファーによる行動喚起(CTA)
サンプル:CTA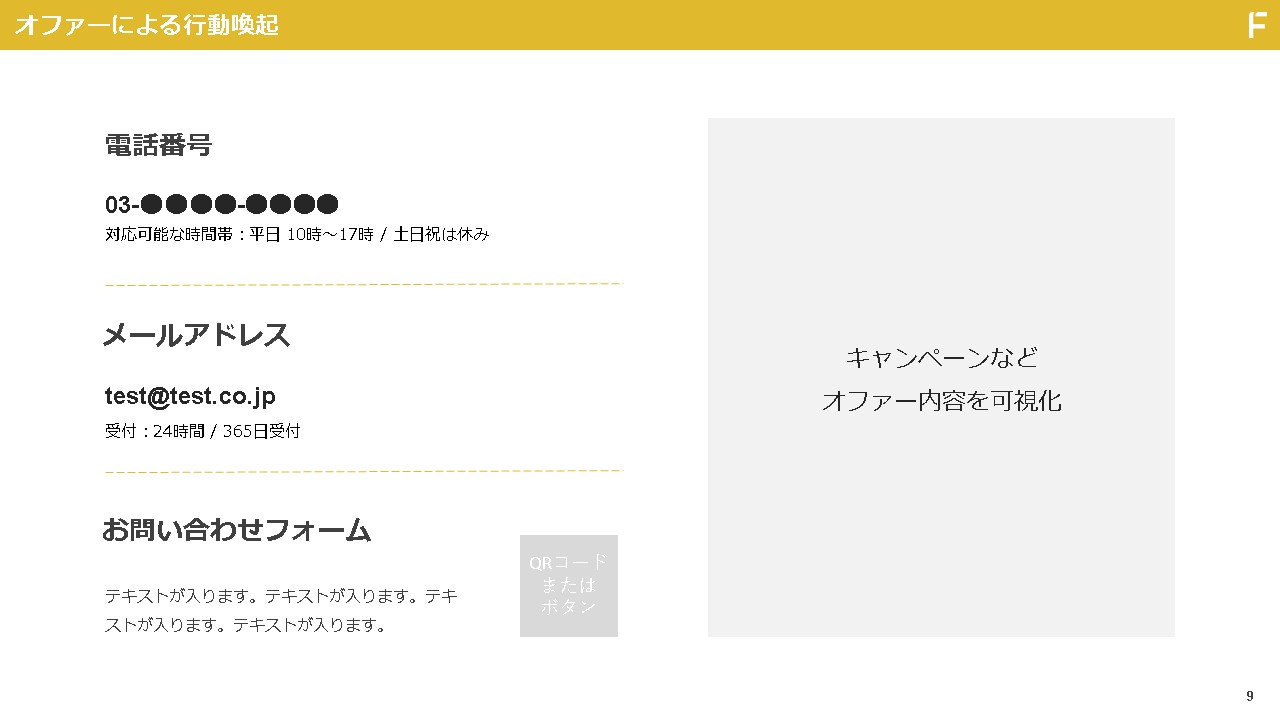
製品・サービスの紹介をしただけでは、多くの読み手はすぐに具体的な行動(問い合わせや申し込みなど)に移りません。
少しでも多くの見込み顧客を次のステップへ進めるためには、具体的な行動を明確に促す「CTA(Call to Action)」が必要です。
「無料トライアル」「資料請求」「デモ」「個別相談」など、読み手が次に取るべき具体的な行動を示すと共に、なぜ今すぐその行動をとるべきなのか、読み手にとって魅力的で具体的な「オファー」(期間限定キャンペーン、特典、割引など)を提示。
行動へのハードルを下げ、一歩踏み出す後押しをするための、具体的で分かりやすい表現が求められます。
フロー⑩ 企業の存在証明
サンプル:目次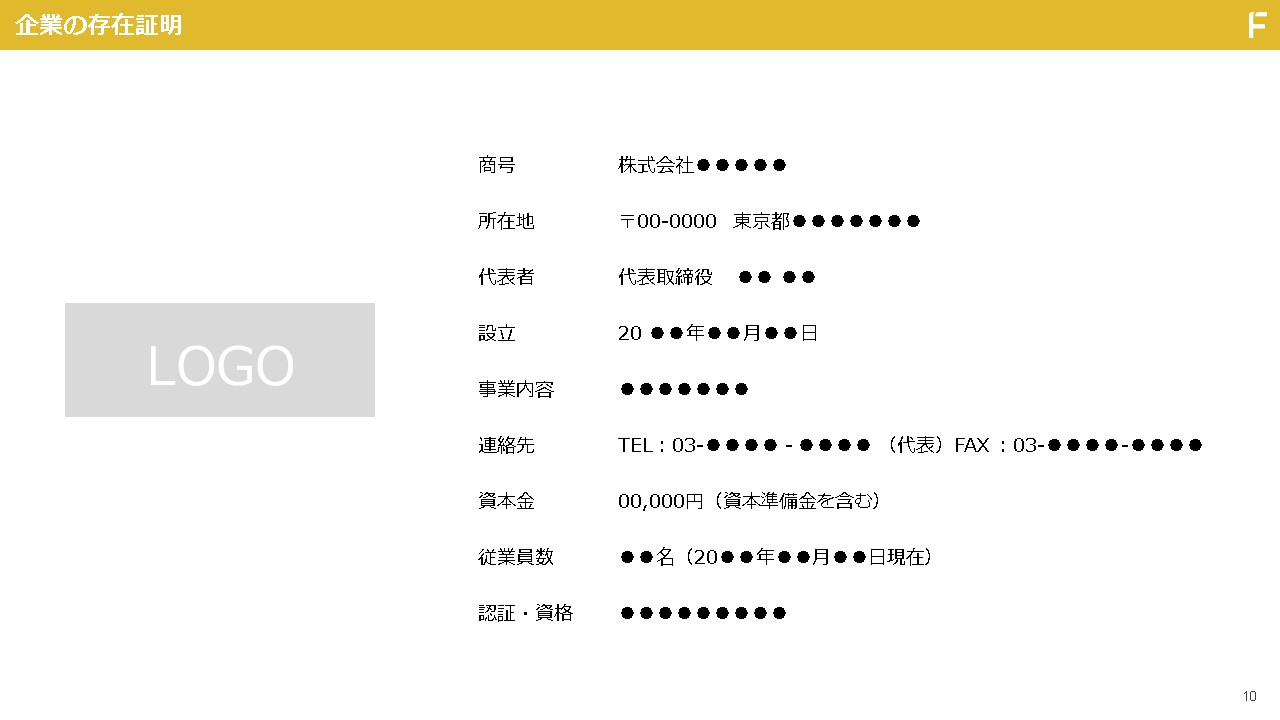
最後に、この有益な情報を提供してくれたのはどのような企業なのか、その存在を証明するために会社概要を掲載します。
企業名、所在地、連絡先、代表者名、設立年などの基本的な情報はもちろん、企業のビジョンや信頼性を示す情報を加えることも有効です。
会社情報がないホワイトペーパーは、読み手に不安や不信感を与えてしまうため、信頼できる情報源であることを示すためにも、必ず含めるべき項目。
この10ステップは、ホワイトペーパーの骨組みそのものであり、あいまいになると中身をどれだけ充実させても、読み手に意図した通りに伝わらず、成果に繋がりません。
テーマ別ホワイトペーパー基本構成への応用
ホワイトペーパーには、課題解決型以外にも様々なテーマがあります。
しかし、どのようなテーマであっても、基本的な構成要素や流れから大きく外れることはありません。
情報の種類や重点を置く部分が多少異なるだけなので、主要なテーマごとの基本構成も確認しておきましょう。
ホワイトペーパーの主なテーマは4種類
課題解決型 :読み手の課題解決に役立つ情報を提供
調査レポート型 :特定の市場やトレンドに関する調査結果を分析・解説
製品・サービス型:特定の製品やサービスの詳細を解説
事例型 :自社製品・サービスを導入した顧客の成功事例を紹介
それぞれの基本構成を見てみましょう。
⇒課題解決型の構成は「ホワイトペーパーの基本構成(課題解決型)」の章で解説済み
調査レポート型ホワイトペーパーの基本フロー
| フロー | 説明 |
|---|---|
| ① 興味の引き付け | 魅力的なタイトル・表紙で調査テーマへの関心を引く |
| ② 内容の全体感の把握 | 目次で調査概要や構成を示す |
| ③ 具体的な調査内容や根拠 | 調査方法、データソース、収集したデータなどを提示 |
| ④ 調査で得られた考察 | データから読み取れる示唆、トレンド、現状分析などを解説 |
| ⑤ 役立つ製品・サービスの紹介 | 調査結果を踏まえ、自社製品・サービスがどのように役立つかを提示 |
| ⑥ オファーによる行動喚起 | |
| ⑦ 企業の存在証明 | |
製品・サービス紹介型ホワイトペーパーの基本フロー
| フロー | 説明 |
|---|---|
| ① 興味の引き付け | 製品・サービスによって解決できる課題や得られるメリットを提示 |
| ② 内容の全体感の把握 | 目次で製品・サービスの全体像を示す |
| ③ 課題の再認識 | 製品・サービスが解決する具体的な課題を深掘り |
| ④ 現状維持のデメリット | 製品・サービスを導入しない場合のリスク |
| ⑤ 解決した際のメリット | 製品・サービス導入によって得られる具体的な成果 |
| ⑥ 具体的な解決策 | 製品・サービスの機能や使い方、導入プロセスなどの解説 |
| ⑦ 解決できる根拠 | 製品・サービスの優位性、実績、技術的な信頼性など |
| ⑧ 解決に役立つ製品・サービスの紹介 | 製品・サービスの詳細説明自体がメイン |
| ⑨ オファーによる行動喚起 | |
| ⑩ 企業の存在証明 | |
事例型ホワイトペーパーの基本フロー(顧客インタビューの場合)
| フロー | 説明 |
|---|---|
| ① 興味の引き付け | 誰が、どのような成果を上げたのか、関心を引く見出し |
| ② 内容の全体感の把握 | 目次で事例の概要や構成を示す |
| ③ どんな問題が起きていたか | 導入前の顧客が抱えていた課題や背景 |
| ④ どのように解決したか | 自社製品・サービスの導入によってどのように課題解決が進んだか、具体的なプロセス |
| ⑤ 解決したことで得られたこと | 導入によって得られた具体的な成果、効果、顧客の声など |
| ⑥ インタビューした企業からのコメント | 顧客からの評価や今後の展望など |
| ⑦ 解決に役立つ製品・サービスの紹介 | 事例で紹介した製品・サービスを改めて紹介 |
| ⑧ オファーによる行動喚起 | |
| ⑨ 企業の存在証明 | |
このように、テーマが変わっても基本的な流れは共通しており、中心となる「内容」部分で、テーマに応じた情報を重点的に配置していることが分かります。基本構成を理解していれば、どのようなテーマにも柔軟に対応できます。
ホワイトペーパー構成に関するよくある質問
ホワイトペーパーの構成について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1:基本構成に習ってそのまま制作すればいいの?
はい、まずは基本構成に沿って制作してみることを強くお勧めします。基本構成は多くの成功事例に基づいており、効果的な情報伝達の流れとして確立されています。特にホワイトペーパー制作に慣れていない場合は、この型に乗ることでスムーズに制作を進めることができ、一定の成果を期待できます。慣れてきたら、ターゲットや目的に合わせてカスタマイズを加えていくのが良いでしょう。
Q2:課題解決型ではなく、他のテーマ(調査レポート型など)の場合も基本構成は同じ?
はい、基本的な構成の考え方や要素(表紙、目次、内容、CTA、会社概要)は同じです。異なるのは、「内容」部分にどのような種類の情報を重点的に盛り込むか、そしてその情報をどのような流れで見せるかという点です。テーマ別構成で解説したように、例えば調査レポート型であれば調査結果とその考察が中心になる、といった違いがあります。根幹となる「読み手の興味を引き、情報を伝え、行動を促す」という流れは共通しています。
Q3:基本構成を使うと、おおよそページ数はどのくらいになる?
ページ数は、ホワイトペーパーを提供するターゲット層や、そのホワイトペーパーにどのような役割を期待するのか(マーケティング戦略上の位置づけ)によって大きく変わります。例えば、特定分野の初心者向けで基本的な内容を解説するものであれば10~20ページ程度に収まることが多い。一方、専門性の高い内容を深掘りする、または複数の情報を網羅的に掲載する場合は、20ページを超えることも珍しくありません。重要なのはページ数そのものではなく、ターゲットにとって必要な情報が過不足なく、かつ分かりやすく構成されているかどうかです。基本構成は、必要な要素を網羅するための「設計図」として活用してください。
最後に
ホワイトペーパーの構成は、その効果を左右する最も重要な要素の一つです。
基本となる構成パターンを理解し、それに沿って情報を整理することで、読み手にとって非常に分かりやすく、企業にとっても成果に繋がりやすいホワイトペーパーを効率的に制作することが可能に。
この記事で解説した基本的な構成要素(スライドの種類)と、課題解決型ホワイトペーパーの標準的なフローをしっかりと押さえ、さらにテーマ別の構成例を参考に、あなたの目的に合ったホワイトペーパー制作に活かしてください。
まずは基本の型から始めてみることで、ホワイトペーパー制作へのハードルが下がり、マーケティング活動における強力な武器となるはずです。