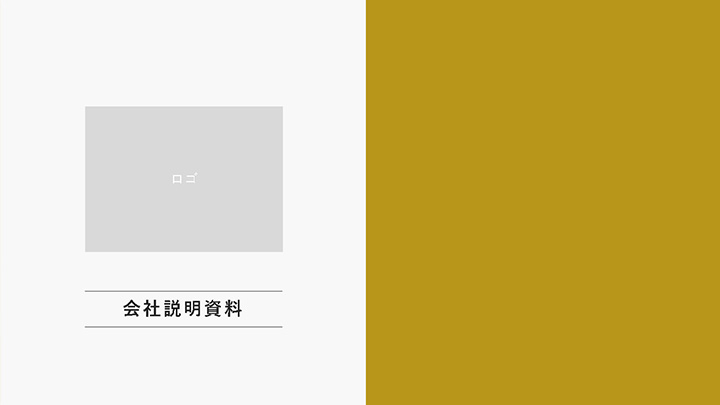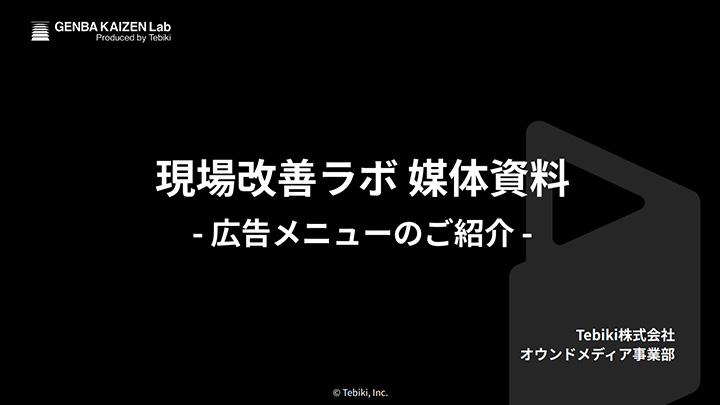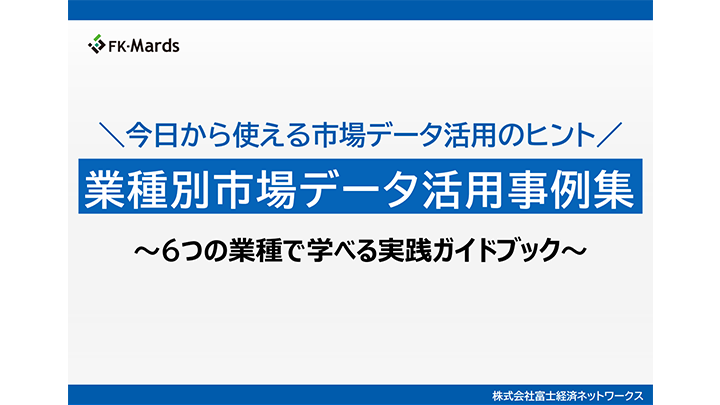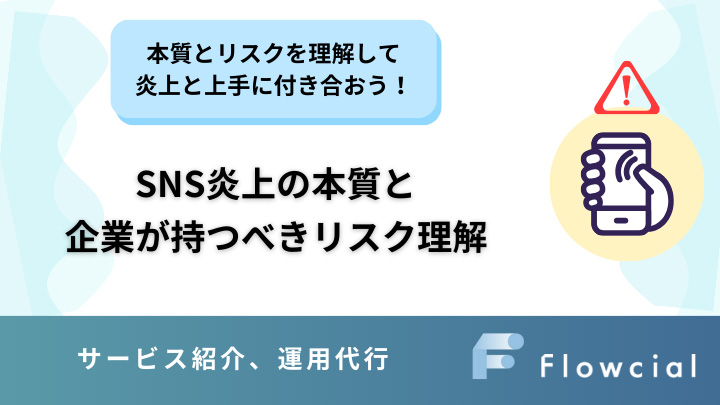いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。オウンドメディアやコンテンツ運用で失敗する兆候をすばやくキャッチして、外注さんとの付き合い方を改善していく方法が分かるようになります。
「なんだか最近、外注先からの連絡が遅くて仕事が止まるんだけど…。」
オウンドメディア(公式サイトやブログなど)を運営していると、コンテンツを継続して公開していくと思いますが、進みが遅かったり止まることありませんか?
内製でコンテンツを作っている場合はまだコントロールできますが、外注に制作をお願いしている場合は、なかなかうまくいかない…。
私自身も外注さんと一緒に進めたり、自社でもコンテンツ提供をしていますが、やはりスムーズに進められる方が少なく、何かしらの課題が発生してその度に解決しながら進めてきました。
オウンドメディアの運用を、外注に依頼した場合の失敗あるあるとして、私の経験をまとめてみたので、この情報があなたのお役に少しでも立てられれば嬉しいです。
外注とは?
外注は、業務を社内ではなく社外に任せることを指し、アウトソーシング・業務委託・外部発注・外部パートナー・委嘱(いしょく)などが外注に該当します。
外注にオウンドメディア運用を依頼する失敗あるある
今まで外注してこなかった、または外注した経験があったとしても、今後はさらに企業だけでなくフリーランスなど働き方が多用となっていくため、外注の需要が各段に高まっていくと思います。
そのため、少しでも失敗を減らせるように、外注での失敗事例と予防策を見ていきたいと思います。
まずはどんな経験をもとに失敗事例を書いているのか、少しだけ私の経歴を下記に。
エンプレス編集部:sugiyama(@pl_enpreth)
テレアポ会社からデザイナーへ転身し、その後は住宅系のマッチングプラットフォームに携わり、チームで育てた事業を譲渡しました。今はさらに別メディアを育て中で、10年以上IT業界のお仕事をしてます。(2020年11月19日時点)
デザイナーやプラットフォームでメディア・コンテンツ運用や事業運営を通して、様々な方とお仕事をさせてもらった経験を元に、下記を書かせて頂いています。
上手くいかないことには、必ず原因がある。
とくに人の心、無意識が行動に表れていることもあります。
コミュニケーションの失敗事例
オウンドメディア運用の一部を外注する場合に失敗するケースで多いのが、コミュニケーションによる失敗。
もしかしたら、失敗の割合としては最も多いかもしれません。
どんなコミュニケーションが失敗を招くのか、見ていきたいと思います。
事象:外注先からの連絡がだんだん遅くなってきた
「最近レスポンスが悪くなってきた。」
「あの担当者って、いつも連絡遅いんだけど。」
外注に依頼した時、この感情を抱かない人はいないのではないか?と思うくらい、かなりの現場で発生していることです。
連絡が遅いから、催促するようになったり、その連絡が無ければ先に進めないのに待たされていると、お金を払っている側からしたら、ストレスの何ものでもない。
あまり「お金を払っているから!」と上から目線の発言はよくないのですが、お金を払っている以上、発注側としても最短で目的(ゴール)達成のため動きたいはずなのに、それが出来ないと心にも負の感情が溜まる一方ですよね。
外注先から連絡が滞るのも必ず原因があり、
- 外注先が他業務でも忙しくなってきた
- 依頼内容の難易度が高く進みが遅い
- 受けたのはいいものの契約を切りたいと思っている
色々考えられますが、一番はあなたに対しての優先度が下がっていること。
契約する前は、営業さんも必死になって対応してくれるのですが、契約できればまずは一安心ですし、実際の作業は他のメンバーへ移行したりと、最初の契約時にかけた想いが、他スタッフに共有されることなく引継ぎされてしまう場合もある。
もちろん実作業のメンバーと顔合わせやお話しながら進めていくと思いますが、営業さんは新しい受注に向けて動き出し、社内でクリエイティブを担うスタッフさんは様々な案件を抱えながら仕事をこなしている。
依頼側としては外注先に依頼している1対1(1to1)の関係ですが、受け側の外注先としては多対多の関係になっており、複数いるお客様の中の1社のような感覚。
しっかりと社内でチームを組み、そのプロジェクトのためだけに動ける組織体制となっていればいいのですが、その体制を作るには大きな予算をもらってないと、現場としてはなかなか難しく、ある程度数をこなしていくことになります。
特に、金額を安く受けてくれた場合などは、安い分、数をこなしている外注さんだと思うので、余計にあなたの会社へ対応してくれる時間は減ってしまいますよね。
全てがこのような状態になるわけではないですが、優先度の低さからくる、連絡の遅さは確実にあるはずです。
対策:連絡を早くもらうためには?
どのくらいだと「早い」のか「遅い」のかは、人によって感じ方はバラバラなので、送った後10分以内に返信がこないだけで遅いと思う場合もあれば、1日は待てる方もいる。
お互いで速さの認識合わせをしておくといいかもしれません。
直接聞きにくいのであれば、いつまでに回答がほしいか明記しておく。
ここで注意したいのは、相手のことも考えず、自分都合の期限を入れないこと。
朝に送って今日の12時までに回答がほしいと伝える。
すぐに回答がほしいと、急かすだけ急かす。
もしあなたがされて、返答しずらいなと思ったのであれば、それは相手も感じることなので、期限は余裕をもって伝えておきましょう。
仕事をしていれば、突然何かの情報が必要になって、回答を急かす場合もあると思いますが、そのような場合はきちんとメールなり電話なりで、事情を説明しておくと配慮があっていいと思います。
ちょっとした工夫で、連絡が遅いストレスが解消できればやっておきたいですよね。
業界特有?かもしれませんが「なるはや」といった急かす言葉があり、これは時間軸が分からず、感情だけで伝えているため、いつまでに返答すればいいか分からないので使わないようにしましょう。
事象:「〇〇が言ってるから!」と思考停止になっている
「部長がこうしろって言ってるから…。」
「チームリーダーの〇〇さんが言ってるから…。」
発言力の高い方が言った内容は、それだけ効力が高く、守るべき法律のような効果が生まれてしまいます。
こう言ってるから、その通りにすればいいのねと、もしかしたら思考停止に陥っていることで、コミュニケーションが依頼側と外注側でうまくいってない場合も。
工場生産のようにベルトコンベアに乗せれば、次々と同じ加工で同じ品質で生まれるモノとは異なり、外注するのであれば、知らない人同士がコミュニケーションを取りながら、お互いの思考と行動を持ち合いながらバランスを見て進んでいくと思います。
もし、誰かに言われたことをそのまま鵜呑みにして進むと、自ら考える思考になりにくく、結果的にそれが行動となって表れ、全体の進みを遅くしてしまいます。
例えば、電話をしている最中、大事な話なのに、途中途中、音声が切れてしまったら、相手が言いたいことも伝わらない、聞き取りたい側も聞き取れない、結局この情報伝達は失敗に終わり、正しい行動も起こせません。
思考と行動をお互いに持ち寄りながら進めることで、コミュニケーションが円滑に進み、正しい情報の受け渡しができるため、目的の達成に近づける。
「誰が」ではなく「自分が」の認識でお互い進めているのか確認しましょう。
対策:その意見が誰のものかを確認
実際にやり取りするのは依頼側の担当者さんと、外注先の担当者さんになると思うのですが、お互いが交わす会話の内容で、誰からの意見なのかを確認し合うのも一つの手です。
「実は弊社の部長が、こう言っているのですが…」
その発言に対して、誰の思惑が入っているのか確認できると、それだけで対応の仕方を臨機応変に変えていけます。
さらに担当者としてはどう考えているのか分かると、一緒になって発言元の人物に対して説得する内容を用意したり、対策だってとれる。
何も隠さず話すことで、本当の情報のやり取りが行えるようになるので、コミュニケーションが円滑に進んでいきます。
お互いで目指すべきゴールへ向かっていくために、誰の発言かを確認しておきましょう。
事象:お互いのことを理解してない
「なんで分かってくれないんだ…。」
「やってくれると思っていたのに…。」
発注側と外注側がお互いに理解し合えていないと、コミュニケーションにも失敗します。
それほど親しい仲でもない、ただ仕事での付き合いだけだとしても、お互いを知らなければ「分かったつもり」で進んでしまい、後から手直しが多くなったりコストも時間もかかることに。
何も親友レベルまで仲良くなる必要はなくて、何が得意で不得意なのか、何に興味があって興味がないのか。
ちょっと理解できるだけで、コミュニケーションがとりやすくなります。
最終的には、お互いで目指すべきゴールへ進んでいくのですが、その過程で何度も連絡を取り合い、認識を合わせていく。
コミュニケーション回数が多いからこそ、一回一回のコミュニケーションの精度を高めて、目標達成へより近づく為に、お互いを理解していくことは大事だと思っています。
対策:複数人ではなく1to1で話す
プロジェクトを進めていくのに、両社で何人か携わっていくと思いますが、まずはメインとなる担当者同士だけで、心理的距離を近づけておくことが大切だと思います。
両社が複数人で対応していくと、どうしても自分事にできず他人事で関わる人が出てきてしまう。
ゴールを目指すためには、オーナーシップが必要にもなるため、他人事のままだと成果も出しにくいです。
そのため、オーナーシップの発揮が必要なメイン担当者の2人が、円滑にコミュニケーションとれるよう、その二人だけで話す機会を作っておくのがオススメなんです。
事象:意図の読み取りで時間が掛かっている
「あれ、依頼したのにまだ仕上がってない。」
「あとどのくらい時間かかる?」
外注先へのお願い事が、期日間近になっても完成しそうになかったり、思っていた以上に時間がかかっている場合、依頼内容の意図を外注先が読み間違えている場合もあります。
読み間違え…これは外注先が意図を理解できなかったからではなく、もしかしたら依頼側の指示が曖昧な場合もある。
例えば、
① こんな感じのデザインにしたい。
② もう少し青色を強くして、角を丸くしたい。
上記2つの依頼の内容、どちらが分かりやすくて、意図を読み間違えないかと言われれば、2つ目の具体的な内容が書かれている方ですよね。
分からないからこそ依頼をしているはずなので、言葉にできないことは当然あるとおもいます。
しかし、外注先としては、よりお客様の想いに応えようと色々動いてくれるのですが、指示が曖昧だと、その意図や背景を読み取るのに時間の多くを使ってしまって、作業や回答が遅くなってしまう。
分からないことは、外注先の方がプロだと思うので「こうしたい、ああしたい」と、希望を素直に話してみて、それが出来るのか難しいのか、話していく中で、本当は何をすればいいのか見極めていけるといいかもしれません。
対策:具体的な指示を出す
単純ですが、具体的な指示を出すことで、指示の読み取りや理解が早くなり、外注先の対応速度が早まる可能性もあります。
使ってはいけない言葉として、
- おまかせで
- こんな感じで
他にも「カッコいい」など形容詞だと、よく分からない内容になってしまいます。
「何」を「どのように」して「どうしたいのか」を伝える。
さらに期限があるなら期日を、量があるなら個数を、数字を入れることでも具体的に表わすことができます。
言いたいことを、ちょっと具体的にするだけで、相手の理解度はグンとあがるので、目的達成に近づくことができます。
事象:詳細を詰め切れてない(要件が定まっていない)
「ここは、こんな感じでいいですかね。」
「参考サイトみたいにしてください。」
何をどうしたいのか、具体的に詳細を詰め切れてない状態で取引がスタートしてしまうと、進めていく途中で追加や変更が多くなって、大きくスケジュールをズラす事態にも。
依頼主は分からないからこそ外注先にお願いしているわけなので、詳細を詰め切れないのは当然?だと思われがちですが、だからこそ外注先がしっかりとコントロールして、詳細を詰めておく必要があるんです。
結局、細かい部分をなぁなぁにしておくと、あとで自分達の首をしめることになる。
コンテンツ(記事)制作の場合、最初に決めたテーマに沿って文章を書いているため、そのテーマが変われば内容も当然変わってくるのですが、テーマ変更はイコール全部変更にも該当。
制作中に、制作の道筋を何度も変えられたら、余計に手間がかかって利益も圧迫していきます。
そんな仕事を続けていたら現場も疲弊してしまうため、結局は最初にどれだけ詳細を固めて進めるかにかかっているんです。
対策:お互いの認識合わせのドキュメントを共有する
ここはどうする。
あそこはこれにする。
依頼側と外注側で、共通した認識がとれるドキュメントを作っておくだけで、お互い幸せになれます。
突然の追加や変更をしたくなったとしても、最初に決めていたことの記録を読み返すことで、無駄な変更がなくなっていく。
もし変更したくなっても、当初と要件が変わることが認識できるため、追加料金に対して健全な話し合いもできる。
大まかなスケジュールは共有しますが、制作に関する詳細は共有してないことが多いため、お互いが分かる形で共有できるようにしておきましょう。
事象:両社間で言いたい事が言えない状態になっている
「これ聞いてもいいのかな。」
「あれ言っておけばよかったな。」
何か言いづらいことがあったり、聞くことにためらいがある関係性のままだと、よいプロジェクトにはならないかもしれません。
あなたはお金を払っている側なので、そこまで遠慮することはないと思うのですが、例えば誰かの紹介を受けて契約した場合、紹介者がいる手前、モノが言いずらい状況になってしまう場合も。
本当はしたいことがあるけど、外注先とのコンディションを崩すと、紹介してくれた人に悪いと思ってしまう。
それはあなただけでなく、外注先も同じような気持ちになっているため、お互いに遠慮が入ってしまう場合もありますよね。
同じゴールを目指していく関係なのに、ゴールではなく紹介者に意識が向けられてしまっている。
結果的にそのプロジェクトが失敗に終わってしまったら、紹介者の顔に泥を塗ってしまう可能性だってあります。
結果を出すことが一番なので、紹介者や外注先には配慮しつつ、言いたい事が言える状態になるのが大切です。
対策:目的やゴールの共通認識を持つ
依頼をするのは、達成したい目的があるからなので、もちろん目的やゴールを意識するのは当然だと思います。
しかし、紹介者へ意識が向けられてしまうと、目的やゴールへの意識が薄まり、紹介者への顔色伺いになってしまうため、依頼側と外注側できちんと、目的・ゴールの認識合わせを行っておきましょう。
このようなケースはあまりないかもしれませんが、お金を支払う分、失敗はなるべくさけたいため、同じようなケースになったら意識してみてください。
事象:悪い出来事を全て相手のせいにしてしまっている
「だから言ったのに…。」
「これ、責任とってくれますか?」
何か悪いことが起きた場合、全て外注先のせいにしてしまう場合もあります。
本当は誰も悪くなくて勘違いしていただけ…こんなこともありますが、実際に悪い出来事が起きたら、メインで対応をしていた外注先に矛先が向けられやすくなります。
外注先が本当に、ミスやトラブルを引き起こしたのであれば、会社としても責任を取ってもらいたいですが、そうではなく依頼主側のミスでトラブルになっている場合も。
あまり認めたくはないので、お金を払っている分、強気にでれる。こんなこともあるかもしれません。
特に、日頃から依頼側が外注の対応に不満を溜めていたら、どこかで爆発して、過剰な糾弾になってしまうこともあります。
まずは冷静になって現場と原因を確認し、どうしたら乗り越えられるかを、両社で建設的に話し合えるといいと思います。
対策:普段から不満を感じさせないようにする
難しいかもしれませんが…日頃のやり取りから、両社間のコミュニケーションを円滑に進めるよう配慮すること。
不満が出たのであれば、必ず詳細を確認して、解消しておくこと。
特に依頼側からすれば、不満を溜めずに、その都度きちんと相手に伝えて、お互いで悪い原因を解消していく歩み寄りが必要です。
自社に関する失敗事例
実は、外注を使ってオウンドメディア運用を行うのに、社内に失敗の原因が隠されていることもあります。
外注先の失敗はコントロールできませんが、社内でならあなた自身でも予防できたり、リスクコントロールは可能。
失敗して上司や社長に怒られないよう、立ち回れるようにしておくのがオススメです。
事象:失敗してはいけない意識が強すぎる
「予算回すからな。」
「このプロジェクト失敗できないぞ。」
半ば脅しのような失敗してはいけない雰囲気、あなたの会社にありませんか?
どの企業も、初めてのことや、ノウハウがないことに対しては、失敗する確率が高いことを理解した上で、挑戦していくと思います。
ファーストリテイリングの柳井氏も「一勝九敗」とった本を出している通り、新しいことをすれば失敗の確率は高い。
スタートアップは成功するか失敗するか分からないけど、果敢に挑戦していますよね。
しかし、通常の企業は、スタッフさんも多く抱え、お給料を払うために、継続的な利益をあげなければいけないので、事業やプロジェクトの失敗によって、その後の経営は大きく崩れる可能性もある。
常に稼ぎ続けなくてはいけないため、大きな博打には出ず、堅実的に売上と利益を高めていく意識が強い。
そのためか、失敗=悪のような意識も強く、失敗に対して過剰になりすぎている場合が多いと思います。
オウンドメディア運用は特に、成果が出るのが遅いため、社内的にはコストモンスター扱いをされる場合も。
成果が出るのに1年かかる場合も普通であり、コストをかけ続けて成果が出ないことで、プロジェクトの打ち切りが早まることもあるんです。
対策:成果が出るのに時間がかかることを社内へ認識させておく
オウンドメディアで成果を出すには時間がかかることを、予め社内(上司や社長)に対して認識させておくことで、早急なプロジェクトの打ち切りは避けられます。
失敗してはいけない意識が強い会社ほど、本当に大事なこと。
しっかりとコンテンツマーケティングが行えれば、1年以内には10倍ものアクセスに増やせたりと、会社にとってもメリットが大きいです。
事象:焦っていて過剰に速いレスポンスを求めてしまっている
「なるはやで!」
「今日の午前中にはもらえますか?」
社内事情で何か焦って進めないといけない場合、外注先に対して過剰に速い返答を求めてしまう場合があるかもしれません。
しかし、改めて情報を整理してみると、実は担当者側の勘違いだったり、期日の読み違いをしていることも。
とりあえず「なるはやで」が口癖の方もいますよね。
外注先にも事情やスケジュールは当然あるので、無理がきかない場合だってあります。
逆に焦らせてしまったことで、品質が低下したり、誰も得をしません。
急ぎたい気持ちは一旦グッとこらえて、外注先にも配慮しながら最短で行動してもらえるように、指示ではなくお願いベースで話してもらうといいかもしれません。
対策:正直にいつまでが期日なのか伝える
曖昧な言い方で、すぐに対応を求めるような言い方をするのではなく、正直にいつまでにほしいのか、具体的な期日をお伝えして頂くのがオススメです。
また、そのタイミングでほしい具体的な理由も添えておくと、外注先としても意図が分かって、気持ちに応えてくれる場合があります。
一番だめなのは、早い返答を求めておきながら、結局確認しなかったり、発言と行動の整合性がとれていないこと。
これを続けていくと、信頼を失ってしまうので、お金を出しても案件を受けてくれなくなる場合がありますので注意が必要だと思います。
事象:外注経験や少なく、ノウハウもない
会社や上司は外注を利用したことはあるけど、担当者レベルで外注に依頼したことがない場合もありますよね。
私も、初めて外注に依頼したときは、正直どうすればいいか分かりませんでした…。
外注の経験が無いのと、オウンドメディアの運用に関するノウハウなどがなければ、何をどこまでやってもらえるのか、その線引きが分からないことも多い。
自社や自分都合で考えてしまい、外注に無理をさせてしまって、結果的なクオリティが下がってしまう場合も。
分からないことは別に恥ずかしいことではなく、分からないことをそのままにしている方が、外注での失敗を招きやすいです。
実際に外注として対応してもらう前に、まずはお互いの知識レベルの把握を行い、共通認識を作っておくのがオススメです。
対策:進める前の事前確認
分からないことは、事前に全て聞いておく。
分からないことが分からない状態かもしれませんが、あなたなりに分からないことがあれば、それは外注先の担当者にぶつけておきましょう。
そうすれば、外注先の担当者も「ここが分からないのね」と、知識レベルを確認でき、それが進め方にも反映されていきます。
また、会話を繰り返しておくことでコミュニケーションがとりやすくなり、お互いの情報伝達がスムーズになることで、仕事の質も高まっていきます。
事象:相見積もりをして安さで選んでしまった
「安くて助かった~。」
「他に予算をまわせる。」
オウンドメディアの運用を外注化しようと相見積もりをした際、安さで選んでしまうと、後々トラブルを招く場合も。
安さには、それなりの理由が必ず潜んでおり、状況によってはあなたに合わない場合もあります。
例えば、あなたのオウンドメディアでは、品質の高い記事コンテンツが必要なのに、安い外注を選んだことで、品質が低い記事コンテンツばかりを納品されてしまった。
または、大量の安いライターさんを囲っていたからこそ、安くできたけど、記事コントロールができなくて、品質がバラバラ…。
他にも、スキルや対応面が不十分なのを知りながら、費用が安いからといって契約してしまった。
あなたが実際に現場へ立って進めていくため自ら外注先を選んだのであればいいですが、外注先を決めたのが上司や部課長陣だった場合、大変なのは現場ですよね。
外注を選ぶ人と、現場の指揮をとる人が違ければ、トラブルは不可避かもしれません。
対策:安さではなく目的達成に一番近い外注を選ぶ
安さはもちろん、選ぶ基準の一つかもしれませんが、最終的に目的達成ができなければ、全てが無駄にもなってしまう場合も。
安さ基準はひとまず片隅に置いておき、目的・ゴールを目指すためには、どの外注がいいのかを考えて選んで頂くのがオススメです。
仮に金額が高かったとしても、よい外注を選べれば、その費用を大きく上回る効果を得られることだってあります。
安さだけで選ぶのは危険!この意識だけでも持ってもらえるといいかもしれません。
事象:全て"おまかせ"の意識を持っている
「丸ごとお願いね。」
「こっちの手間なくて楽だ~。」
分からない、またはリソースが足りないからこそ外注に出しているわけなので、依頼側としては余計な手間がない方が嬉しいですよね。
しかし、外注に出したのは、あくまで目的・ゴールへの最短距離を進むためでもあり、依頼側の足りない時間とスキルを"補ってくれる存在"が外注さん。
全てまかせっきりにしていると、いつまでも時間が足りない、スキルが足りない状況が続いてしまうため、目的・ゴールへの到着が遅くなってしまう場合も。
最終的な判断や価値創出は、自分達でコントロールできるようにならないと、ずっと高いコストが掛かり続けてしまいます。
会社の方針にもよると思いますが、いずれはオウンドメディアの運営をインハウス化(内製)にできるような取り組みができるといいかもしれません。
対策:共創の意識で臨む
外注にお願いすると、何でもしてくれそうな気になりますが、必要な情報を揃えたり、社内折衝などは依頼側が行っていく必要があります。
そのため、外注を使ったとしても、必ず何かしらのお仕事は発生し、それが滞ると外注側の仕事も滞ってしまう。
外注は足りない時間とスキルを補ってくれるパートナーと考え、あなたも一緒に動いてゴールを目指す意識は忘れないようにして頂くのがオススメです。
事象:一度の無理が、二度三度と増えていく
「ここだけ、なんとかお願いします!」
「あと少しだけ対応してほしいです!」
依頼から仕事終了まで、スムーズに何事もなく終わることはなく、突発的な対応が発生することもありますよね。
依頼側が外注側に対して、無理なお願いをすることも少なくはありません。
しかし「一度無理を受けてもらえる」と認識してしまうと、同じような状況になったり、どうしても頼みたいことが発生した場合は、また受けてくれるだろうと甘えが出てしまう場合もある。
その無理が何度も続き、外注側の負担が増える依頼ばかりをしていると、関係性も破綻してしまいます。
品質も対応面もよかったのに、嫌われてしまった場合は契約解消、またはもう受けてもらえず、あなたの目的・ゴールの達成が遠くなってしまうため、お互いですが無理なお願いは極力避けた方がいいと思っています。
対策:無理が発生しないスケジュールを作る
内容によっては、納期が短い場合もあると思いますが、それらは全て自社都合の納期。
結局、オウンドメディアはコンテンツの品質の良し悪しで評価が決まってくるのですが、品質を高めるにはそれなりの時間と熱量とお金がかかります。
無理なスケジュールを立てれば、時間も足りない、熱量も足りない、お金も足りないとなり、品質は担保されません。
品質が担保されなければ、結果的に目的を達成できなくなるので、スケジュールも品質重視に寄せて、十分な時間が確保できるようにするのがオススメです。
そして、品質を崩さないため、無理なお願いは控えましょう。
事象:担当者のこだわりとゴールが結び付いてない
「ここは絶対にこうしたいんだ!」
「いや、ここは、これを追加しよう。」
依頼側も外注側も、同じ目的達成を目指しながら進んでいくと思いますが、どちらかのこだわりによって、ゴールが遠のく場合もあります。
そのこだわり、本当に目的達成に必要なのか?
ただ、自分のこだわりを貫き通したいだけではないのか?
自分達のこだわりと、オウンドメディアを見てくれるユーザーさんが欲しい情報は全然違っていることもあるため、誰のためか分からないこだわりは危険です。
まず、オウンドメディアでは、誰を満足させることが重要なのか、目的達成にはこの考えが深く結びついている。
大切なことを忘れて、自分達のこだわりを演出することに走ってしまうと、失敗する確率が高まるため、注意が必要です。
対策:求められているのは「何か」を認識する
確かに、会社によっては自社が大切にしていることがあり、それを盛り込みたいと思うのは当たり前だと思います。
大事な内容であれば、なおさら外せません。
しかし、その情報が、本当にユーザーさんにとって必要なのかを考えて頂くと、入れるべきか、入れないべきかが判断できる。
特にオウンドメディアに来てくれるユーザーさんは、自社のファンではない限り、欲しい情報が見つかれさえすればいいので、欲しい情報以外書いても、たいていは無視します。
よく電車や駅に広告が掲載されていると思いますが、最近見た広告で覚えている内容はありますか?
たぶん、誰もが何となく見ているだけで、記憶に残っていないと思います。
自分事にならない情報は、見てもらえない、記憶してもらえない、見てもらったとしても人間の記憶力がそこまでよくないので、多くは忘れられてしまいます。
だからこそ、まずは相手が見たいと思う情報でコンテンツを作ることに集中して頂き、自分達のこだわりは一旦忘れて頂くのがいいかと思っています。
事象:緻密な設計、計画がなければ依頼できないと思っている
「まだ調査できてないから…。」
「いや、これじゃまだ依頼できないな。」
完璧主義だったり、外注先にちゃんと説明をしたいと思って、かなり詳しい情報を揃えなければ依頼できないと思ってしまう場合ありませんか?
確かに、外注先としても詳細情報を頂けるなら、喜ばしいことなのですが、その情報を頂けるまで何も作業ができなかったり、次に進めないと目的達成が遅くなってしまう…。
意味のある絞られた情報であればいいですが、無作為に集めた多すぎる情報は判断を鈍らせたり行動を遅くします。
外注先の方が、オウンドメディアのプロでもあるので、完璧思考を持たれているなら、まずは相談ベースで話しながら進めて頂くのがオススメです。
対策:相手を信用することから始める
特に解決方法と言える内容ではないのですが、完璧思考の持ち主だと、自分がどうにかしないといけないと思ってしまいがちかもしれません。
それは、あまり相手を信じられていないからこそ。
まずはパートナーとして、これから一緒に進めていく相棒(外注先)のことを、信じてみることから始めてみてください。
また、頼ることが苦手な方も、自分でなんとかしようとしてしまうため、頼ることから始めてみるのがオススメですよ。
事象:現場に権限がなくて後でひっくり返される
「上司が修正してほしいと言ってまして…。」
「すみません、ここを直してほしいのですが…。」
外注の担当者さんとやり取りするのは、現場の担当者さんになるかと思うのですが、実際に指示を出して権限を持っている人が別にいると、あとで思いもよらないどんでん返しが発生する場合も。
現場に権限がないと、せっかく進めていたことを、方向転換させられたり、軌道修正が余儀なくされることもあります。
対策:現場への権限を強めてもらってから進める
たぶん、この方法しかないのですが、依頼側の担当者さんが現場の権限を貰った上で進めていける状態を作るしかありません。
オウンドメディアの運用は、スピードも大事ですが、品質の高いコンテンツを作るには時間もかかり、簡単に書くテーマを変更して修正などは難しい。
途中で何度も変更することはできないため、現場に入っている人が素早く判断して、コンテンツ作りをサポートしていく必要があります。
ある程度の権限を持たせて上げて、現場で判断できる状態を作るのがオススメです。
事象:目的がズレていく
目指したいゴールがあるからこそ、そこに向かって進めるように外注へ依頼を出すと思うのですが、進めていくうちに、だんだんと当初の目的からズレた目的を作っていってしまう場合があります。
例えば、売上・利益の向上を目指して、コンバージョンを増やせば目的達成に繋がると考えた場合、KPIをコンバージョンへ設定します。※ KPIとは、ゴールを達成するための途中の目標のこと。
ここまではいいのですが、コンバージョンが増えれば増えるだけ達成に近づくのであれば、コンバージョンを高めるだけの施策を考える。
フォームを簡易的にしたり、キャンペーンを打って大量のコンバージョンを集める。
KPIとしてはコンバージョンの数値が大幅達成して「大成功!」ですが、結果的に品質の低いコンバージョンが多くなったせいで、現場の対応コストも増え、売上・利益にも繋がらず、結果的にマイナスが発生してしまった。
目的がズレていくことで、目指したいゴールから遠くなってしまう場合があります。
対策:正しいKPIを設定する
目的達成を目指すのであれば、達成に結び付く正しい指標が必要です。
これが意外と難しく、知らない間に目的からズレてしまうことがあるんです。
KPIの知見がなければ、間違えたKPIによって現場の疲弊が生まれる場合もあるため、改めて目的が何であるか、それを達成するための指標はなにかを考えていく必要がある。
自社で知見がなければ、外注側のノウハウをフルに活用して、正しいKPIを作っていきましょう。
事象:失敗の判断が早すぎる
「このまま続けても効果がでなそうなので撤退を検討したい。」
「運用メディアをコスト削減の対象にする。」
何でも初めから上手く進められることはないと思いますが、本当はこれから成果が高まっていくのに正確な見極めが出来ておらず、失敗の判断を出すのが早すぎる場合も。
オウンドメディアはとくに、成長時期が遅く、どんなにがんばってもスロースターター。
主にGoogleなどで検索した人が見に来てくれる、自然流入を獲得するのが一般的ですが、立ち上げ当初は何の評価も得られてないので、自然流入が集まりにくい。※ すでにオウンドメディアを立ち上げて運用していた場合は上記には当てはまりません。
かなり苦しい時期を過ごしますが、地道に品質の高いコンテンツを公開し続け、ユーザーさんの満足に応えていると、ある時期から突然アクセスが伸び出します。
そこまで我慢できればいいのですが、コストを掛け続けても、なかなか成果が出ない場合は、どうしてもコストに目が行きがちなので、これ以上無駄な投資を避けようと失敗の判断が早すぎてしまう。
対策:費用対効果や実例をもとに説明しておく
依頼側のあなた、もしくは部課長陣が撤退の判断を下す場合もありますよね。
しかし、オウンドメディアは最初は苦労しますが、正しく運用を続けていけば、いずれ大きな集客となって、自社のビジネスを大きく押し上げる結果を作れる。
その実例がないから「投資」ではなく「コスト」と考えてしまう場合が多いと思うので、外注先に対してオウンドメディアの成長や費用対効果を示せる資料を貰っておくのがオススメです。
予め成長が遅くて、成果を出すのに長丁場となることを説明できていれば、すぐに失敗判断も下されず、進めていける可能性を高めていけると思います。
外注先に関する失敗事例
「選ぶ外注さんを間違えて、苦労した…。」
こんな経験はありませんか?
まだだったとしても、オウンドメディアの運用を外注する場合、コンテンツの品質が大きく今後の成果に関わってくるのですが、外注選びで大きく変わってきます。
最初の外注選びだけでなく、継続的にお願いしている場合でも、何か歯車が少し掛け違っただけで、うまくいかなくなるので、外注先に関する失敗事例も見てみましょう。
事象:効率化で品質を落とす
「あれ、最近文章のテイスト変わった?」
「何だか、分かりづらくなってない?」
継続的にオウンドメディア運用を外注に任せていると、ある時から品質がガクッと落ちる場合があります。
発注し続けてずっとお願いしていると、外注先も進め方や、あなたの会社の特性なども読み取って、スムーズな対応ができるようになってくる。
しかし、やり方が分かったのであれば、当然仕組み化と効率化を図ってくるため、このタイミングで一気に品質が落ちる場合もあるんです。
例えば、今まで担当してくれた人が外れたり、担当者は変わらず実際に手を動かす人が変わる。
または内製で取り組んでいたものを、フォーマットが決まっているからと言って、もっと単価が安く済む外部へ制作を出すようになる。
外注側もディレクションや制作を外部に出して効率化を図るのは当然の動きなので問題ないのですが、その仕組みをとったことで品質が下がる場合は問題です。
継続して関係を築いていく場合は、途中で制作体制が変わる場合も考えられるので、注意しなければいけません。
対策:コミュニケーションを欠かさず行い動向をチェックする
外注側の動きを把握するために、コミュニケーションは定期的にとっておいた方がいいと思います。
正直に「制作体制を変えようと思っている」と言ってくれる場合もあれば、こっそりと変更していることも考えらえるので、コミュニケーションを欠かさずとっておき、動向を把握しておくだけで対応ができます。
もし、制作体制を変えて品質が落ちるようなら、改めて話し合いで、どう品質を上げつつ保ち続けるか議論して頂くのもオススメです。
事象:孫請けによって品質を落とす
今はどこの企業もアウトソーシングを行い、自分達がメインに行う業務に集中できる環境を作っています。
あなたがオウンドメディア運用を外部に任せようと思っているのと同じで、外注先の運用・制作会社も外部に業務の一部を出しているはず。
どの企業も行っていることなので、それは問題ないのですが、外部へ出している会社のレベルが低かったり、コントロール出来てない場合は品質が下がります。
対策:品質維持の取り組みを確認する
外注先もわざわざ、自分達の制作業務をアウトシーシングしている事は言わないですし、きちんと求められるレベルのサービス・商品を提供できればいい。
そのため、あなたが確認する事としては、依頼側に対して最終的に納品される品質を、どうやって担保しているのか、その取り組みを聞くことだと思います。
例えば、内製だからと言って品質が良くなるわけでも、外部ライターだからと言って悪くなるわけでもありません。
内製だから、外部だから、そういった考え方ではなく、目的を達成するためには、提供されるものの品質がどこまで高められているかが大事です。
事象:担当者の変更によって品質を落とす
「担当替えのご挨拶となります。」
「引継ぎを行いまして…。」
外注先の事情によって、今まで担当してくれた方が変わる場合もありますよね。
人事異動のため、別プロジェクトへのアサインのため、退職のためなど、様々な理由で人材の移動があります。
担当者が変わるから品質が落ちる?関係なくない?と思われるかもしれませんが、今まで品質を担保できていたのは、その人が周りと調整してくれたり、依頼側の意図をしっかり汲み取ってくれていたからこそ、提供品質が高くなっていた。
私が体験した内容だと、今まで担当してくれていた人が辞めてしまい、その後の連絡が途絶えやすくなって、結果的に契約を解除した経験があります…。
うまく引継ぎが出来たとしても、今までのような状態にはならない、またはさらに良くなる場合もありますが、何かしらの支障は必ずあります。
対策:仕組み化をしておく
ずっと同じ人が担当してくれる方が少ないと思うので、まずは人の入れ替わりは必ず発生するものだと認識しておき、人が変わったとしても同じ品質を維持し続けられるような仕組みを、依頼側と外注側で作っておくのがオススメです。
人に依存したやり方だと、その人がいなくなった途端、大きくぶれてしまうため、人に依存しない仕組みにしておく。
例えば、連絡フロー、品質チェック表など、一人だけが覚えている内容にするのではなく、関わる全ての人が同じ情報にアクセスできる状態にしておくだけで、ずいぶん変わります。
特に、属人的な情報管理が失敗する原因だったりするので、少し変えるだけで、環境は維持できると思います
事象:外注先の企業方針や体質が自社に合わない
「絶対にこれにすべきです!(決めつけ)」
「でも~、だから~、そのため~(言い訳)」
外注さんの選び方にもよりますが、選んだ企業の特徴によっては、目的達成が危ぶまれる場合もあります。
- 薄利多売
- 社員が頻繁に辞めていく
- 知識、スキル不足
- ミスが多い
- 固定概念が強い
- 考えの押し付け
- 言い訳が多い(できない理由ばかり)
オウンドメディアの運用をサポートしてくれたり、コンサルティングしてくれる企業はたくさん存在。
長期の経験がなくても、オウンドメディアのスキルは比較的取得しやすいため、一時成果を出せれば、それを元に売り込みもできるので、経験が浅い企業でも事業とすることができます。
また、フリーランスなど個人の方が、ブログなどのメディア運用に詳しい場合があるので、オウンドメディアの外注先はたくさん。
だからこそ、様々な考えをもった企業が存在しているので、上記の悪い傾向に当てはまる企業を選んでしまう場合もあります。
対策:きちんと比較をして決める
1社のみに見積もりをお願いして決めるのではなく、複数社に要件を伝えて相見積もりするのが一般的な流れだと思います。
相見積もりのメリットは比較ができることですが、デメリットは価格だけで選んでしまいがちなところ。
価格の安さは確かにメリットですが、安さにはそれなりの理由が必ずあるので、合わない外注先を選んでしまったら、あなたが目指す目標やゴールを遠回りする場合も。
価格以外の基準もしっかりとつくっておき、自社にとってどの外注先が一番いいのか慎重に選んで決めましょう。
契約内容に関する失敗事例
オウンドメディア運用の外注先を決めるにあたって、契約内容のトラブルもあります。
契約は約束事でもあるので、しっかりと取り決めを行った上で契約に臨んで頂くのがオススメです。
事象:当初の契約よりも依頼レベルが高くなってきた
「今度は、もっとこうしてほしい!」
「追加で、こういうのもできますか?」
最初に依頼を受けた際は、お互いどこまでやれるのか、様子見の部分もあると思います。
だんだんとお互いの事が分かってくるのと、依頼側として知識が増えてきて、さらにやりたい事も増えてくる。
その結果、最初の要望から大きく前進してしまって、対応可能なレベルを超えてくる場合があります。
一度契約した内容や金額からズレてしまうと、外注としても対応がしずらくなって、連絡が遅くなったり品質が逆に落ちてしまう場合も。
対策:対応可能レベルの認識合わせと調整
どんどん内容がモリモリになってくるのは、外注あるあるです。
そのため、最初の契約時にはきちっと「この対応内容だと、この金額です。」と線引きしておくことがオススメ。
本当はこれ以上のレベルだと追加料金が必要となるのに、依頼側と外注側でなにか覆せない関係性があると、なかなか言い出しずらい。
その状態で進めていくと、結果的に品質が落ちたり、現場が破綻して目的達成もできなくなる場合も。
外注だからといって「何でもしてもらえる感覚」を持つのではなく、仕事をしてもらうためには正当な対価が必要なことを認識して頂くと、お互いが幸せになれます。
事象:十分な対応ができないのに外注が引き受けている
「え、これできなかったの?」
「この内容だと、結構時間が掛かります…。」
外注側も案件を受注したいと思っているので、多少背伸びをして引き受けることもあると思います。
そこが大きく逸脱すると、求めているレベルに達せられず、どんどん作業も、あなたの目的達成も伸びていく。
対策:依頼内容に近しい実績や事例を確認する
外注先を選ぶとき、しっかりと比較をされていると思いますが、改めて今回依頼したい内容が受けられるのか、それに近しい実績や事例を見せてもらいましょう。
事象:制約が多すぎる
「この表現は使えません。」
「必ず、この言葉は入れてください。」
ブランドを崩さない、またはオウンドメディアの運用方針を持っているなら、外注として依頼する企業にはレギュレーション・ルールなど規則を伝えると思います。
しかし、それらの規則が多すぎて、外注として受けるには制約が多すぎて辛い場合も…。
制約があるからこそクリエイティブが光る、なんて言われることもありますが、できないことが多すぎると身動きがとれなくなり、外注先としてもやりずらさを覚えてしまう。
どんなに良い外注先だとしても、お金払いが良かったとしても、仕事がしずらかったり現場に相当な負担をかけるなら受けてもらえなくなる可能性もあります。
対策:本当に必要な制約なのか改めて確認する
一度決めたルールなどを、そのままずっと使い続けている場合もありますよね。
付け足し付け足しで進んでルールが多くなりすぎている場合もあれば、更新せず古いままで使って時代に合っていない場合もある。
外注先に伝える場合は、改めて精査して本当に必要なことだけを守ってもらう形にして頂くのがオススメです。
事象:途中で依頼内容をコロコロと変えていく
「やっぱり、このテーマにしていいですか?」
「んー、こっちに変更でお願いします!」
最初に決めた方針、またはコンテンツ作りのテーマなど、進めていく途中でコロコロ変えて現場が混乱する場合もあります。
何も分からない状態から外注し、進めるうちに知識が付いて、方針が変わることはよくありますが、そのケースが多いと、外注先としても受けられる範囲を超えてします。
例えば、最初に決めていたテーマで進むために、人員を確保・アサインしていただけど、コンテンツのテーマ自体を変更することになり、改めて人員を確保しなくてはいけなくなった。
私自身も経験があるのですが、最初にお願いしていた内容から途中でガラッと変えてしまった時、外注先からの連絡や対応が極端に落ちて、モチベーション低下にともないプロジェクトの進捗が遅くなったケースがあります。(今では反省してそんなことはもうしてません。)
どんなにコミュニケーションが取れていても、良い外注先でも、依頼内容の変更はそれなりのリスクを伴うので、気を付けましょう。
対策:ジャストアイデアを封印する
外注側としては、最初に決めた流れにそって進んでいきますが、あるタイミングで依頼側の誰かの中で突然アイデアが浮かび、それを試したくなることがあるかもしれません。
これをジャストアイデアと仮に命名しますが、すでに一度決めた中で進んでいることに対して、かなり大きな方向転換を行うと、色々なところに混乱を招きます。
また、一度決めたことの効果も検証しないまま、新しいことを始めても、何が良くて悪いのか分からないため、新しいアイデアなどは、次の機会にしてもらうのがオススメ。
まずは両社で一度決めた内容を実行し、検証しながら調整して進むのがいいと思います。
失敗に不安を感じているあなたへ
外注にお願いして、オウンドメディアの運用を行う場合の、失敗事例と対策を見て頂きありがとうございます。
これらの内容が必ず発生するわけではなく、あなたの会社の特性や、外注側のレベルによっても変わってきます。
どの外注先を選ぶかは条件次第だと思いますが、どこに頼んだとしても、何事もなく進められることはなく、大小何かしらの課題は出てくる。
課題が生まれることを前提に、一緒に解決していける外注先を探すことが、一番安全で成果がでると思っています。
外注選びは慎重に行いながら、末永く付き合っていけるパートナー探しを楽しんでもらえると嬉しいです。