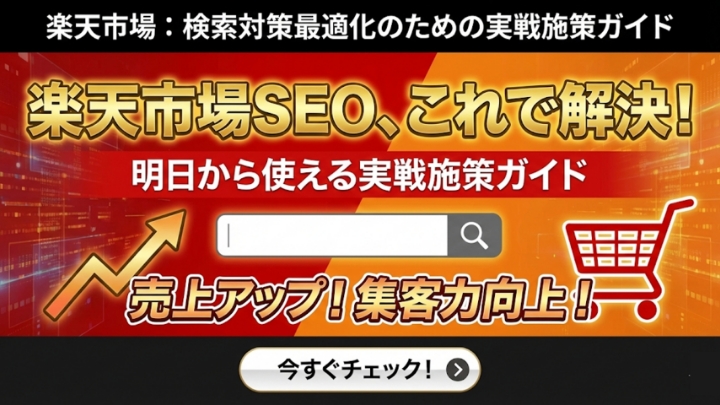いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:fukuyamaです。ダイバーシティ(多様性)そのものだけでなく、それを活かした「ダイバーシティ経営」にも注目です!
近年、ニュースやメディアなど社会のさまざまな場面で耳にする「ダイバーシティ(多様性)」ですが、その意味を知っていますか?
ダイバーシティは今や企業活動にとっても避けては通れない考え方です。
ここでは、ダイバーシティの意味や企業経営への効果、実践方法などを解説します。
- 目次
- ダイバーシティとは?意味をわかりやすく解説すると?
- なぜ、ダイバーシティが求められるのか?そのメリット
- ダイバーシティ経営がうまくいかない原因や課題・デメリット
- ダイバーシティの理想と悲惨な現実
- ダイバーシティを実現する方法
- ダイバーシティを取り入れ事業を発展させましょう
ダイバーシティとは?意味をわかりやすく解説すると?
ダイバーシティ(Diversity)を日本語に直訳すると「多様性」。
他にも、「相違点」や「多種多様性」といった意味もあります。
ダイバーシティの実現とは、「組織やグループ、企業などにおいて、さまざまな属性の人々が集まった状態」と表現できます。
ダイバーシティという言葉は、1950〜60年代の米国で始まった「マイノリティが差別を受けないこと」を目指した公民権運動がきっかけとなって広まりました。
以降、性別や人種といった特定の属性に対する差別について議論する際に使用されてきましたが、現代では「多様性=あらゆる属性」といった視点に発展して語られるようになりました。
ダイバーシティとインクルージョンの違い
近年は「ダイバーシティ&インクルージョン(Diversity & Inclusion)」、略して「D&I」という概念も企業経営における重要な項目として認知されています。
セットで語られますが、厳密にいうとそれぞれの単語の意味は異なります。
- ダイバーシティ(多様性)…人種や性別といった多様な属性を持つ人材の集まり
- インクルージョン(包括)…多様な人材が集まって互いに機能している状態
D&Iを企業経営の場面で例えると、多様な人材が共存し、互いに個々の機能を活かしながら能力を発揮できる職場環境といったところです。
つまり、ダイバーシティとインクルージョンは、意味は違いますが分離できる概念ではなく「ダイバーシティを前提にインクルージョンが成り立つ」と説明できます。
ダイバーシティ=多様性に該当する要素
多様性に当てはまる要素とは、外部から判断できる「表面的ダイバーシティ」と、一見して分かりにくい「深層的ダイバーシティ」に大別できます。
| 表面的ダイバーシティ | 深層的ダイバーシティ | |
|---|---|---|
| 定義 | 生まれ持った変えようのないことや、自分の意思で変えにくいこと | 見た目には大差がなくても、内面的に大きな違いがあること |
| 属性 | 年齢・性別・容姿・国籍・民族・人種・障害の有無・性的指向など | 第一言語、能力・スキル・キャリア・仕事観・価値観・宗教・ライフスタイルなど |
上記に挙げた例はごく一部で、実際にはもっと多くの属性が存在します。
また、思考や経験に基づく深層的ダイバーシティは、その人の生まれ育った時代や国の文化といった表面的ダイバーシティに大きく影響されることがあります。
例えば、
- 痩せている(表面的)から、美しい(深層的)
- 女性(表面的)だから、家事をする(深層的)
- 若い男性(表面的)は、外でがむしゃらに働くべき(深層的)
- 外国人(表面的)だから、就職が難しい(深層的)
これらの認識は、表面的な要素が深層的な要素に影響したごく一例です。
ひと昔前の日本では当たり前のように語られ、今でも世代によっては「常識」として根強く残っています。
無意識に差別・偏った考え方をしていることを「アンコンシャスバイアス」といい、本人に悪気はないので異論を向けられると「非常識だ」と捉える節も。
このように、2つの要素は絡み合って存在しているだけに、複雑な問題といえます。
ダイバーシティ経営(マネジメント)とは具体的に言うと?
ダイバーシティを企業マネジメントの骨格に取り入れることを「ダイバーシティ経営」と呼んでいます。
グローバル化による競争の激化、少子高齢化による労働者の減少…。
さまざまな環境が変化する中で、企業の競争力強化に欠かせない概念として注目されたのが「社員の多様性」です。
ダイバーシティ経営によって、女性・高齢者・障がい者・外国人をはじめとした多様な人材が能力を発揮する機会を作ることで、新たな価値の創造につなげます。
経済産業省では、ダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、日本企業にダイバーシティ経営の浸透を働きかけています。※出典:ダイバーシティ経営の推進 (METI/経済産業省)
なぜ、ダイバーシティが求められるのか?そのメリット
ここでは、企業経営の視点からダイバーシティが求められる背景やメリット、効果についてみていきましょう。
ステークホルダーから選ばれる会社となるため
企業は法令遵守や利益追求はもちろん、あらゆるステークホルダー(利害関係者)からの要求に対して適切な対応を行う社会的責任があります。
ステークホルダーとは、企業活動の結果が利害に直結する株主や顧客、共にビジネスを行う取引先や従業員、企業を取り巻く地域社会や環境といった立場のこと。
企業が多様性に配慮した活動を行うと、立場や役割の異なるあらゆるステークホルダーからの支持を集めることにつながります。
ダイバーシティの効果
「多様なステークホルダーから選ばれる」ということは、顧客は商品を買い、株主・投資家は投資額を増やし、従業員には働きがいが生まれ、採用希望者も増えるといった形として現れます。
その結果、企業は業績が上がり、さらなる発展を目指していく。こうした好循環が期待できるのです。
ジェンダー平等を実現するため
日本社会のダイバーシティにおいて象徴的な課題の一つといえば、女性活躍を主題としたジェンダー平等ではないでしょうか。
ジェンダー(gender)とは、社会的・文化的に作られてきた役割の違いによる性別のことを指します。
例えば、「男は外で稼ぎ、女性は家事などで家を守る」という論調は今だに語られますよね。
バリバリと稼ぐ女性や家事が得意な男性だってごまんと存在するのに、無意識に決めつけている男女の役割。
これが「ジェンダー不平等」「ジェンダー差別」と呼ばれる状態です。
SDGs(持続可能な開発目標)には、17の目標のうちの5番目に「ジェンダー平等を実現しよう」と掲げられています。
達成目標に「全ての女性と女の子にあらゆる差別をなくす」と示されているように、世界的に見ても女性の社会的立場の低さは課題となっています。
ビジネスシーンにおいても男女の分け隔てをなくすだけでなく、あらゆる固定観念を正すことも、企業が取り組むべき重要な課題と言えます。
ダイバーシティの効果
身体的な「性」に対する無意識な偏見を取り払うことは、まずはセクシャルハラスメントの防止につながります。
また、男女を問わず個人の能力を正しく評価し、ポテンシャルを引き出していく効果も期待できます。
優秀な人材を採用し競争力を高めるため
今やビジネスは特定のエリアにとどまらず、国境や地域を超えて取引されています。
日本企業が海外へ進出する、海外企業が日本で事業を行うことはごく一般的になりました。
そんなグローバル社会において、企業で働く個人の価値観が内向きでは国際競争に太刀打ちできません。
それなのに、多くの企業は採用の基準が「日本の四年制大学を出た新卒生」といったステレオタイプのままで良いのでしょうか。
島国である日本の企業が世界市場で勝つためには、日本人と文化・慣習の異なる人々がターゲットになります。
国籍や人種、仕事観などの属性を問わず「優秀な人材」を見極めて採用することが、世界からの期待に応える競争力につながります。
ダイバーシティの効果
例えば、さまざまな国籍の人材を採用すると、他国の人々の価値観や働き方といった幅広い視点を取り入れた事業活動が可能になります。
育休や介護休暇後の女性社員に活躍のチャンスを与えると、その経験が活かされることもあります。
また、社内に多様な人材が増えるほどお互いの立場や視点を理解しようとする動きも生まれ、さらに風通しが良くなり、ダイバーシティの機運も高まります。
様々な視点を活かし事業にイノベーションを起こすため
上司やチームリーダーを見まわしても、新卒から生え抜きの男性社員しかいない。
役員ともなれば、定年に近い中高年男性の揃い踏み。
時代の流れに合わせて、社外取締役だけ女性を採用している。
これらは、日本企業で未だ多く見られる姿です。
これでは、既定路線を抜け出すのは困難。
従来にない視点を取り入れて事業にイノベーションを起こすためにも、ダイバーシティの考え方が欠かせません。
ダイバーシティの効果
バックグラウンドや経験が異なる人材がそれぞれさまざまな視点を持ち寄れば、かつてないアイデアが生まれる可能性が広がります。
そして、これまでにない視点を持つ人材が経営に携われば、現場から上がってきた新たな発想にコストや人材をかける決断ができる可能性があります。
ダイバーシティ経営がうまくいかない原因や課題・デメリット
ダイバーシティ経営の重要性は理解できても、「思うように現場に受け入れられない」「効果を実感できない」といった課題を持つ企業もあります。
考えられる原因やデメリットについて把握しておきましょう。
トップのコミットメントが弱い
企業のダイバーシティを推進するにあたって、現場の自主性に依存するだけでは実現できません。
代々受け継がれてきた会社の風土を一個人が変えることは簡単ではなく、ましてや経営者やチームリーダーといった決裁権を持つトップが古い価値観で行動している限り、現場が変化するわけはありません。
「他社もやっているから」とトップがダイバーシティを宣言しても、現実を知る社員は見せかけのポーズかどうかを見抜いてしまいます。
ダイバーシティをトップが経営戦略の骨格に取り入れ、実践のロードマップを示す。
多様性を重んじることにコミットし、自ら行動に移す。
そのような姿を見せて、初めて現場の風潮も変わってくるのです。
トップにあたる人は、現場に浸透するまで多様性の重要さを、自らの言葉で説明する必要があります。
理解不足により女性社員を積極的に教育しなかった
「これまでの役職者は全員男性」「責任のあるポジションを任せられる女性がいない」という企業は、女性社員への教育を積極的にしてこなかったことが要因として考えられます。
見込みのある男性社員に研修やチャレンジの機会を与える一方で、女性社員はバックオフィスに配属していては、女性が成長のチャンスを掴むのは難しい。
重要なタスクを与えられない女性社員は仕事にやりがいを感じられず、辞めることへの抵抗感が低くなってしまうことも考えられます。
その結果、「やっぱり女性には無理だ」「思った通り女性は長く働かない」という偏見につながってしまうのです。
スキルや能力は個々に持つものであり、性別によってポテンシャルが決まるのではありません。
男女平等に学びのチャンスを与える必要があります。
女性は出産で辞めるなどのバイアス
ダイバーシティの第一歩として産休・育休制度の整備だけでは、多様性が認められたことにはなりません。
現場に「女性は出産で辞めるだろう」というバイアス(先入観)がある限り、出産を控えた女性が産休・育休制度を使いたいと思っても、現場が受け入れる空気になっておらず使いにくい・使えないケースもあります。
現実として、妊娠・出産は女性の心身に大きな負荷がかかるライフイベントです。
当初は辞めるつもりがなかったとしても、「どうせ辞める」という周囲の雰囲気を負い目に感じて退職してしまう人もいます。
その時に重要なのは、職場全体で理解して応援する姿勢です。
お客様先によって配置できる人材が限定される
いくら「多様な人材が活躍できる職場づくり」といっても、お客様先によっては配置できる人材を厳選しなくてはいけないこともあります。
外国人や高齢者では対処できない場合や、スキルや能力の不一致なども考えられるので、もちろん誰でもいいというわけではありません。
人材は企業経営の中でも非常にコストのかかるリソースのひとつ。
ただ多様性を優先するだけでは、活躍の場面がない場合もあることが悩ましいポイントでもあります。
理想の状態ではなく現在の自社の雰囲気に合う人を採用している
企業にとって離職者が増えることは、採用コストが上がるため避けたいところ。
ダイバーシティの効果を理解していても、離職を防ぐために「今の社風に馴染む人材」を優先して採用してしまっているケースもあります。
一見効率的な採用計画のように思えますが、これでは、結果として同じような属性の人の集合体となり、価値観はさらに固定化。
本来の目的である「多様な価値観によって企業が成長する」という理想から程遠い状態になってしまいます。
縦割り組織などが原因で意思決定は毎回同じ人
企業活動では日々さまざまな意思決定が行われています。
経営企画や人事、営業、販売といったように縦割りの部署では、何を決めるにしても決裁者が毎回同じという状況は珍しいことではありません。
偏った思考を持つ決裁者の元では、現場の人間は決裁者の顔を伺いがちです。
例えば、「やりたいことを提案しても、あの部長がGOサインを出すはずがない」と部下が諦めてしまうと、新しいプロジェクトや斬新なアイデアを生み出す気力も生まれません。
指摘ができない文化
その場の空気を読みすぎる「YESマン」しかいない状況も、組織の価値観を固定化してしまう原因です。
トップや役員、経営層や上長など権威者が高圧的な態度をとっていたり、事なかれ主義の同調圧力が強い環境だったりすると、「NO」と言いづらいもの。
上からの指令に黙って従い、人と違う意見は飲み込む方が楽といった感覚を持ってしまうのが人間の心理です。
ダイバーシティの理想と悲惨な現実
ここまで読んでみて、社会に属している人ならダイバーシティの「理想と現実のギャップ」に少なからず気づいていませんか?例えば、以下のようなこと。
- 「女性の役職登用」や「海外国籍の人材採用」などしても、現場では女性や外国人への偏見や差別といったハラスメントが起きている
- 考え方が異なる相手と衝突し、生産性が低下している
- これまでと比べてあまりにも異なる人事に、不平不満の声が起きている
また、ダイバーシティの悲惨な現実は、女性の社会進出に焦点を当てると統計上にも表れています。
労働政策研究・研修機構がまとめたデータブック国際労働⽐較2022によると、日本の就業者に占める女性の割合は44.5%であるのに対し、管理職に占める女性の割合は13.3%と世界において低い状態になっています。
もちろん、国としてもダイバーシティを実現するためにさまざまな取り組みをしていました。
内閣府の内閣府男女共同参画局は、社会のあらゆる分野で2020年までに女性の管理職を30%程度になるよう期待する目標を掲げ、経済産業省もダイバーシティ2.0を掲げ推進。
しかし、これが現実です。
ダイバーシティ経営は男性社会や年功序列といったかつての価値基準とは正反対で、年齢や性別、キャリアや考え方が異なる人々と平等に働くこと。
古い体質の現場なら「多様性」の考えを持ち込むだけではかえって混乱します。
広く周知し、個人が納得できるように、自社のペースで取り組むことが重要です。
※出典:データブック国際労働⽐較2022 3-3 就業者及び管理職に占める女性の割合※出典:内閣府男女共同参画局の30%目標※出典:ダイバーシティ2.0
ダイバーシティを実現する方法
ダイバーシティを実現する方法として、主なものを6つ解説していきます。
この中でいくつか取り組めばいいというわけではなく、これらを複合的に着手することで、より質の高い多様性が実現します。
個性を受け入れる文化・社風を作る
企業文化や社風は、一人ひとりの日々の発言や社内外のコミュニケーションによって、自然と浮き彫りになるものです。
スローガンを掲げるだけで、風通しの良い環境が出来上がるわけではありません。
トップによるダイバーシティへのコミットメントの発信や、推進体制の構築といった基盤づくりはもちろん、ダイバーシティについて意見交換するコミュニケーションの機会を取り入れたり、面談で個々の気持ちをヒアリングしたりなど、きめ細かい取り組みによって社内の風向きを変えていく必要があります。
このような機会を通じて多様性を自分事として意識できるようになれば、自然と行動も変化し、個性を受け入れる文化・社風が育まれるようになります。
評価システムと連動させる
「組織のダイバーシティのレベル」を一概に判断することは難しいですよね。
ダイバーシティはあくまで多様性という概念であり、何をもって多様性とするかという解釈の仕方は組織によって異なるからです。
一方で、組織のダイバーシティの進捗状況を定量化し、どれくらい浸透しているかを判断することはできます。
- 海外国籍の人材を、◯年度は◯%採用
- 女性役職者を、◯年までに◯%登用
といったように、企業の最終的な目標を数値として掲げ、途中経過として何%達成したかを測る方法です。
定期的に進捗状況を計測し、達成状況を評価。
この「評価システム」と連動して具体的なダイバーシティ施策を行うことが、着実な推進につながります。
個人を知る機会を増やす
「入社◯年目の△△さん」「30代の女性社員」という表面的な属性だけでなく、個人がどんな働き方を望んでいるか、実際にどれくらいの能力があるかといった深層的属性について、管理職や人事が知る機会を増やすことも有効です。
例えば、上司と部下が定期的に対話をする「1on1」や、「コーチング」のように相手の話に耳を傾け、自発的な行動を促す方法は、普段の業務上のやり取りでは表に出にくい胸の内を聞く機会になります。
また「OKR(Objectives and Key Results)」を実施して個人の達成すべき目標や成果を測ることも、能力の見える化につながります。
その上で、長所や考え方を発揮できそうな配置や育成を行えば、社員にとっても組織にとっても良い環境になると期待できます。
働きやすさよりも働きがいの創出
ダイバーシティの成果をより良いものにするためには、働きやすさよりも「働きがい」に比重を置くと事態が好転することがあります。
「個人の働きやすさ」は労働者として重視したい条件ですが、自己中心的な解釈が進むと「話の通じやすい価値観の人と働きたい」「自分は個性を尊重されるべきだから好き勝手にやる」といったように、マイナスのベクトルに向く可能性は否めません。
一方で、「個人の働きがい」ならどうでしょうか。「私は必要とされている」「今よりもっと良い仕事をしたい」と、能力を発揮するようになります。
人材の同質化を防ぐ
採用活動や社員教育を行う際にダイバーシティの視点を取り入れると、人材の同質化から脱却することができます。
例えば、毎年同じような属性の新卒生を採用したり、若手の男性社員にばかり教育を行っていると、同じような人材がキャリアを重ねることになります。
一見効率的な人材育成のように思えますが、組織の人材の同質化は、価値観が偏りがちになり企業成長の妨げになる恐れも。
一方で、外国人や女性、障がい者といった人たちへと採用ターゲットの裾野を広げ、分け隔てなく教育すると、多様な価値観や能力を持つ組織づくりが実現します。
さまざまなバックグラウンドを持つ人材が、社会のさまざまな人にとって価値ある発想をする。
ダイバーシティによって人材の同質化を防ぐことは、社会に新たなイノベーションを起こす可能性も高められるのです。
異能を認める
「ダイバーシティ(多様性)」は、女性や障がい者だけに向けられた言葉ではなく、異なる能力や価値観を持つ一人ひとりの才能を活かしていくということ。
日本人は同質性が強く何かと空気を読みがちなので、これまでにないタイプの人物には身構えてしまうこともあります。
日々の仕事の中で「自分と違うからこそ、自分より優れているところがある」と考えて行動し、一緒に働く人の能力を認められるようになると、個々の能力の相乗効果も期待できるようになります。
ダイバーシティを取り入れ事業を発展させましょう
男性だけ、管理職だけ、既存の既得権益を持っている人だけが会社を動かすといった状況と、一人ひとりが尊重しあって自分らしく働ける職場。
どちらで多くの人が働きたいと考えるでしょうか?
労働人口が減少する中、グローバル社会に対応し企業が存続していくためには、無意識の偏見や固定観念が蔓延したままの状態がどれだけ損失になっているのかを見つめる時期にきています。
日本ではダイバーシティ推進を積極的に取り組んでいる企業は未だ少ない状況です。
一早く取り組んで多様な人材に「機会の平等」を与え、競合との差別化を目指してみませんか。