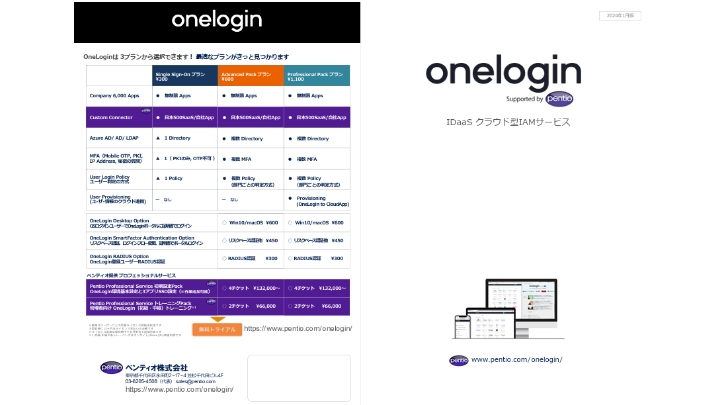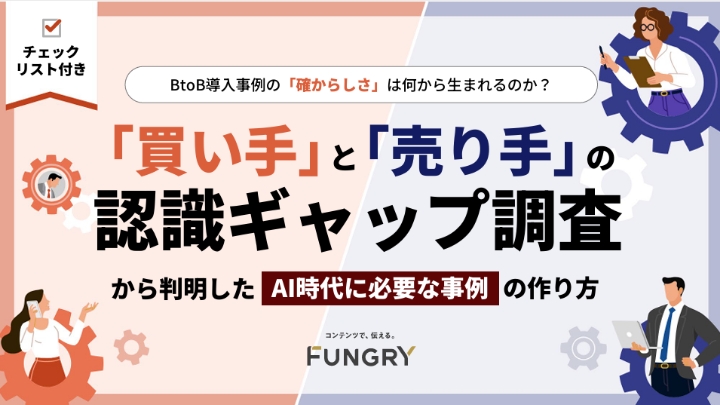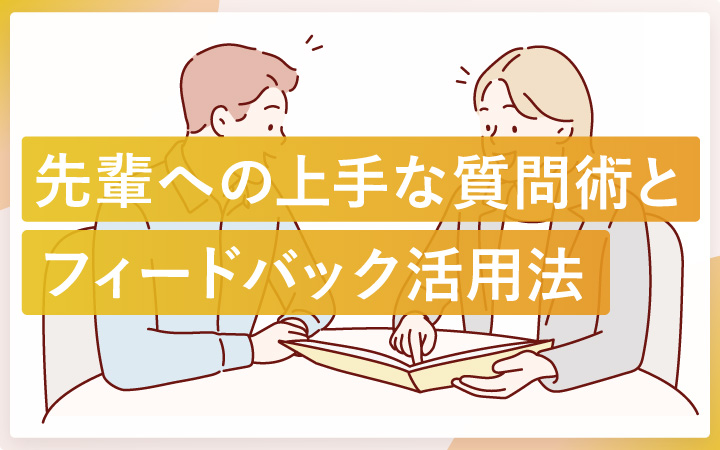
「エンプレス」の編集部:エンプレス編集部です。先輩への上手な質問術と、フィードバック活用法についてまとめました。質問するのが怖いと思っていたり、もっと成長したいと考えているなら必見です。
「先輩への質問の仕方が分からない」「フィードバックをもらうのが怖い」――新入社員や若手社員のあなたは、そんな悩みを抱えていませんか?
「初歩的なことを質問したら、先輩の時間を奪ってしまいそう」「どうせ言っても無駄かもしれない……」と、一歩踏み出せない気持ちもよく分かります。
しかし、質問とフィードバックのスキルを磨くだけで、あなたの成長スピードは飛躍的に向上するんです。
この記事では、明日からすぐに実践できる「質問術」と「フィードバック活用法」を解説していきます。
これらのスキルを身につければ、あなたは先輩や上司から信頼されるだけでなく、自分自身でキャリアを切り拓く力を手に入れられるので、私と一緒に見てもらえると嬉しいです。
- 目次
- 先輩を動かす「質問術」を知ろう!
- 成長のチャンスを逃さない!先輩からのフィードバックを120%活かす方法
- 質問とフィードバックがもたらすキャリアへの好循環
- 【まとめ】質問とフィードバックは成長への近道である
先輩を動かす「質問術」を知ろう!
先輩や上司から「良い質問をするね」と評価される社員は、なぜか成長が早いと思いませんか?
その理由は、彼らは単に答えをもらうだけでなく、質問を通じて先輩との信頼関係を築き、より多くのノウハウを引き出しているから。
ここでは、あなたの成長を力強く後押しする質問術を3つのステップで紹介します。
1. まずは自分で調べる意欲を持とう!
「これはどうすれば良いですか?」とすぐに質問する前に、自分で調べる習慣をつけましょう。
あなたが「まったく調べていない状態」で質問すると、先輩に良くない印象を与えかねません。
それは先輩の時間を一方的に奪うだけでなく、あなたの「考える力」を奪ってしまうことにつながるからです。
やみくもに質問するのではなく、Google検索や社内マニュアル、過去の資料で何を調べたかを明確に!
「ここまで調べましたが、分からない部分があるので教えてください」と伝えることで、先輩はあなたの「自分で解決しようとした意欲」を評価し、的確なアドバイスをしてくれます。
「ここまで調べました」と前置きするだけで、先輩はあなたを「成長意欲がある人」と認識してくれる可能性が、ぐっと高まるんです。
2. 先輩の時間を無駄にしない「効率的な質問」を
先輩はあなたの指導以外にさまざまな業務を抱えています。
貴重な時間を奪わないためにも、質問は「結論」から話すのが鉄則です。
質問の意図を素早く理解してもらうことは、スムーズな回答と、先輩からの信頼を得るために欠かせません。
3.質問を簡潔にまとめるコツを知ろう
先輩とのコミュニケーションを円滑にする上で重要なのは、質問を簡潔にまとめるコツを知ることです。
結論から先に話す
ビジネスの現場では、「結論から先に話す」ことが基本です。
質問が回りくどいと「結局何が聞きたいの?」と先輩をイライラさせてしまうリスクもあります。
本題にたどり着くまでに時間がかかると先輩の集中力も奪ってしまうため、質問する際は「結論から先に話す」ようにしましょう。
悪い質問例(前置きが長く、結論を先に言わない)
「すみません、実は昨日からこの資料を作っていて……このデータって先輩がまだ作成中ですか? そのデータがどこにあるか分からなくて、自分なりに社内のフォルダをいろいろ探したんですが、見つからないんです……」
良い質問例(結論を先に言う)
「〇〇の資料について質問です。 ××のデータがどこにあるか教えていただけますか? 共有フォルダの確認は済んでいます」
結論から話すことは先輩の思考整理にも役立ちます。
話が脱線しにくくなるため、「分かりやすい伝達」につながるのもメリット。
上司や同僚から「話が簡潔で理解しやすい社員」と評価を受けることも期待できます。
状況を簡潔に伝える
質問時に、結論から話すことが鉄則なのは前述の通り。
納得できる回答を先輩から得るためには「状況を簡潔に伝えること」も不可欠です。
というのも、結論だけだと「その質問が生じた背景」が分からず、先輩が的外れな回答をしてしまうリスクがあるからです。
状況を共有すれば、あなたのやり方がそもそも間違っているリスクにも、先輩は気づきやすくなります。
悪い質問例(背景がなく、的外れな答えになるリスクがある)
「この資料の作成方法を教えてくれませんか?」
良い質問例(背景と、聞きたい内容を簡潔に伝える)
「一週間後に提出する会議資料について質問があります。グラフの作り方を教えていただけませんか?」
悪い質問例の場合、先輩は「分からないのはどの部分?」「そもそも何用の資料なの?」と質問を追加しなければなりません。
一方、良い例なら「一週間後ならまだ余裕があるね。グラフを作りたいなら、共有フォルダから過去の資料を探して、それを参考に作ったらどうかな」と解決策を示しやすくなるんです。
話を簡潔にまとめるためには、結論と背景の関連性を意識し、要点を3つ程度に絞る工夫も効果的です。
疑問点をピンポイントで絞る
先輩があなたの質問に対し「どこから説明すれば良いか」がしっかり分かるよう、質問時は疑問点を絞るようにしましょう。
悪い質問例(漠然とし過ぎている)
「企画書って、どう書けば良いですか?」
良い質問例(疑問点がピンポイント)
「この企画書で、スケジュールの書き方が分かりません。どのような粒度で記載すれば良いですか?」
悪い質問例の場合、先輩はあなたがどこでつまずいているのか把握できません。
良い質問例のようにピンポイントでの問いかけができれば、あなたが「全体像を理解していること」「ある一点でのみ悩んでいること」がクリアに。
これにより、「自分で考えている」「あと一歩で解決できる」姿勢を先輩にアピールしやすくなりますよね。
3. あなたへの期待を高める「+αの質問」を
質問をする際は、単に答えを聞くだけでなく、一歩踏み込んだ「+αの質問」を。
先輩にあなたの成長意欲をアピールできます。
「なぜこのタスクが必要なのですか?」と本質を問う
行動科学では、人は目的を理解するとモチベーション・パフォーマンスが向上すると言われています。
そのため、「なぜこのタスクが必要なのですか?」と質問することは、あなたの仕事への主体性と、深い理解を求める姿勢を先輩に示す上で非常に重要。
目的を理解することで、「このタスクをより効果的にするにはどうすれば良いか?」とあなた自身で考えて工夫することも可能になります。
単に「言われたからやる」受け身の姿勢から一歩踏み出し、タスクの背景にある目的や意図を理解することで、仕事の質も向上するんです。
悪い質問例(指示通りの作業にしか言及していない)
「この資料の構成はAパターンで作れば良いですか?」
良い質問例(背景を理解しようとする姿勢をアピールできる)
「この資料のターゲットは中途入社社員向けとのことですが、なぜこの構成にする必要があるのでしょうか? 過去の資料の傾向も踏まえ、意図があれば教えていただきたいです」
「次からどうすれば良いですか?」と改善策を聞くことで成長意欲をアピール
「次からどうすれば良いですか?」と質問することで、失敗を恐れない強い意志を先輩に示せます。
組織や人材育成の分野では、フィードバックを受けた後に改善策を確認し、実行へとつなげることがパフォーマンス向上に不可欠と言われているんです。
悪い質問例(成長を期待できない聞き方)
「分かりました。修正を進めます」
良い質問例(改善策を聞くことで、成長意欲をアピールできる)
「ご指摘ありがとうございます。次からはどの点に注意すれば良いでしょうか?」
良い質問例では、あなたが短期的なタスクの完了だけでなく、長期的なスキルアップを見据えていることも分かります。
こうした質問をすることで、先輩はあなたを単なる「作業者」ではなく、「将来の戦力」と認識してくれるかもしれません。
成長のチャンスを逃さない!先輩からのフィードバックを120%活かす方法
フィードバックは「弱点の指摘」ではなく、あなたを「成長させるもの」です。
マネジメント研究の一部では、質の高いフィードバックは社員のエンゲージメントとパフォーマンスを高めるとされています。
フィードバックを味方につけ、成長のチャンスを逃さない方法を学びましょう。
「フィードバック=人格否定」ではない
フィードバックをされて、「自分の気持ややる気を否定された」と考えてしまった経験はありませんか?
厳しい指摘を受け、ショックを受けたこともあるはず。
しかし、フィードバックは人格否定ではありません。
両者は、その「対象」と「目的」がまったく異なるからです。
例えば、フィードバックの対象は、「資料の見出し」「スケジュール管理」「プレゼンの仕方」など、あなたの行動やスキル、成果物です。
その目的は、あなたの改善と成長を促し、「次は資料の見出しをもっと簡潔にしよう」「スケジュール管理をしっかり行おう」と心がけを持つことにあります。
一方、人格否定の対象はあなたの存在そのものであり、目的はあなたを傷つけること。
自分の仕事と自分自身を同一視する必要はありません。
フィードバックで厳しいことを言われても、感情的に受け止めないことが重要です。
フィードバックを記録・可視化する習慣を
「もらったフィードバックを、確実に自分の成長につなげる」ためには、もらったフィードバックを、必ずメモに残し記録・可視化する習慣をつけましょう。
具体的なメリットは以下の通りです。
1.フィードバックの抜け漏れを防ぐ
人は時間が経つと、もらったフィードバックを忘れてしまったり、内容が曖昧になったりします。
メモに残し、いつでも見返せるようにすることで、フィードバックの抜け漏れを防ぎ、確実に実践することが可能に。
これにより、同じミスを繰り返すリスクを防げるんです。
2.具体的な行動計画を立てやすくなる
もらったフィードバックをそのままにしておくのではなく、メモから「次は何をするべきか」と具体的な行動計画(ToDoリスト)に落とし込むことで、「何をすれば良いか」が明確に!
例えば、「資料のデザインが少し分かりにくい」とフィードバックを受けた場合、「資料デザインの参考サイトを3つ探す」「次回の資料は色使いを3色に抑える」と具体的な行動につなげやすくなりますね。
3.自分の成長を実感できる
記録したフィードバックを定期的に見返すことで、「昔はこんなことで悩んでいたけど、今はできるようになった」と、あなた自身の成長を客観的に実感できます。
仕事へのモチベーションが高まり、新しい挑戦の原動力にもつながりますよね。
実行した結果を共有する「報連相」
フィードバックを受けた後、実行した結果を先輩に共有する「報連相」は、あなたの成長をアピールし、より質の高いサポートを得る上で役立ちます。
以下で紹介するのは「報連相」の主なメリットです。
1.あなたの成長を可視化する
結果を伝えることで、「言われたことをちゃんと実行している」あなたの真摯な姿勢が、先輩の目に見える形で伝わります。
これには、あなたの成長と努力を可視化し、信頼度を大きく高める効果があるんです。
2.より質の高いフィードバックにつながる
先輩は、あなたがどのようにフィードバックを活かしたのか知ることで、あなたの理解度や次の課題を正確に把握できるように。
「前回はこうアドバイスしたが、次はここを改善しよう」と、より具体的で的確なアドバイスをもらいやすくなります。
3.先輩との信頼関係を深める
「報連相」は、単なる業務報告ではありません。
先輩は、あなたが自分のアドバイスを真剣に受け止めてくれたことに喜び、あなたへの関心と期待はさらにアップ!
このようなやり取りを繰り返すことで、先輩との間に強固な信頼関係が築かれ、質問や相談がしやすくなる好循環が生まれます。
実践的!フィードバックをもらったときの正しい反応チェックリスト
ここでは、ビジネス現場の調査や専門記事、多くの組織開発研修で推奨されている「フィードバックをもらったときの正しい反応」をリストにまとめました。
「フィードバック=自分の価値を高めるチャンス」と認識すると、上司・先輩からの信頼も獲得しやすくなります。
【実践チェックリスト】
| ひと呼吸置く | すぐ反論したり、動揺したりしない。まずは深呼吸し冷静に聞くこと。 |
|---|---|
| 最後まで注意深く耳を傾ける | 感情に任せて相手の話を遮ることはせず、全体を最後まで聞く。 |
| 相手の目を見て、あいづちやうなずきを入れる | 非言語コミュニケーションで「聞いていますよ」と示す。 |
| 内容が分からないときは積極的に質問する | 理解できなかったポイント、言葉の定義、不明な点はその場で確認する。 |
| 受け止めた内容をメモする | 抜け漏れ防止、振り返り・行動計画の基礎としてその場または直後に記録する。 |
| 具体的な行動計画に落とし込む | 指摘された事項を「次回からどう改善するか(ToDo)」にして整理する。 |
| 実行結果や改善策を報告する | 「前回いただいたアドバイスをもとにこう改善しました」と伝えることで信頼度もアップ。 |
| 感謝を伝える | 「ご指摘ありがとうございます」「貴重なアドバイスで助かります」と素直に伝える。 |
| 必要以上に落ち込まない、言い訳をしない | 否定的な意見にも感情的にならず、冷静でオープンな姿勢を保つ。 |
| ポジティブに捉え、自分の成長材料として活用する | フィードバックは「能力の伸ばしどころ」と考え、前向きに活かすマインドセットを持つ。 |
質問とフィードバックがもたらすキャリアへの好循環
良い質問とフィードバックは、個人の成長と組織の活性化につながります。
あなたの成長意欲がチーム全体に良い影響を与え、知識の共有や助け合いの精神が職場に生まれるからです。
ここでは、好循環の具体例を見ていきます。
「情報」と「信頼」は良い質問から生まれる
良い質問をすれば、先輩は「あなたへの情報提供が有益である」と感じてくれます。
同時にあなたの「考える力」も示せるように。
これにより、「情報」と「信頼」の両方を生み出せるんです。
1. より質の高い「情報」が集まる理由
良い質問は、先輩の知識を効率的に引き出すことができます。
「どこまで調べたのか」「どのポイントでつまずいているのか」「何を知りたいのか」を明確にすることで、先輩はあなたの知識レベルを正確に把握でき、「この部分だけ教えればいいんだな」と効率的に回答できるようになるからです。
その結果、あなたは表面的な情報ではなく、仕事の背景にある本質的なノウハウやコツなど、より深い情報を先輩のアドバイスから引き出せるようになります。
2. 強固な「信頼」が生まれる理由
良い質問により、あなたが「自分で考え、試行錯誤した」プロセスを先輩に伝えられるので、先輩はあなたを単なる「指示待ち」の人間ではなく、自律的に動ける「戦力」として信頼するように。
「結論から簡潔に話す」「状況を短く伝える」「疑問点を絞る」効率重視の質問スタイルは、先輩の時間を尊重している思いやりの表れでもあります。
タイムマネジメントやコミュニケーション戦略の観点からもこの姿勢は高く評価してもらいやすいです。
フィードバックを求める姿勢があなたの期待値を上げる
フィードバックを求める姿勢があなたの期待値を上げるのは、その行為自体が「成長したい」強い意欲と、仕事への真摯な姿勢を明確に示すからです。
組織心理学研究の分野でも、このような自己成長志向の姿勢を示す部下は、上司から「ポテンシャルがある」と認識されやすいとされています。
以下は、先輩や上司に与えられる印象の一例です。
1.成長意欲の高さを示す
多くの人は、失敗を指摘されることが怖くてフィードバックをためらいがちです。
しかし、あなたが「もっと改善したい」「次は成功させたい」と思い自らフィードバックを求めれば、指導や投資をする価値のある若手社員として評価されやすくなります。
2.自己認識の高さを示す
フィードバックを求めることは、「自分一人では気づけない課題がある」ことを素直に認める行為です。
これは、あなたの自己認識の高さや、謙虚に学ぶ姿勢だけでなく、自己理解力の高さも示すことに。
こうした能力の高さは、成長の土台として非常に重要であり、先輩からの信頼を得ることにつながります。
3.信頼関係を構築する
あなたがフィードバックを真剣に受け止め、実行しようとする姿勢を見せれば、先輩は「自分のアドバイスが役に立っている」と感じ、あなたへの信頼度もアップ。
この信頼関係が築かれると、先輩はより深く、そして積極的にあなたをサポートしてくれるようになります。
心理的安全性の高いチームがあなたの挑戦を後押し
心理的安全性の高いチームは、あなたの成長だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを向上させる上で重要な基盤となります。
心理的安全性とは
「心理的安全性(Psychological Safety)」は、ハーバード大学の組織行動学者エイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念。
「チーム内でメンバーが自分の意見や疑問を安心して表明でき、拒絶や批判を受けることなく交流できる状態」を指し、この状態が築かれると、メンバーは発言や行動がしやすくなります。
その結果、チームの創造性やパフォーマンス、問題解決能力が向上することは、多くの研究で明らかになりました。
あなたの質問が心理的安全性の高いチームを生む
心理的安全性の高いチームとは、メンバーが「間違いや疑問を素直に表現しても否定や非難を受けない」安心感を共有している環境を指します。
こうした環境では、率直な質問や意見交換が活発に行われ、チーム全体の問題解決力や創造性が高まることが、多くの研究で示されています。
例えば、あなたは積極的に質問をすることで、ほかのメンバーは「質問しても大丈夫なんだ」と安心し、互いに意見を交わしやすい雰囲気を作り出せます。
逆に、誰も質問をしないのは心理的安全性が低いチームで、新しいアイデアや改善点が生まれにくくなってしまうんです。
小さな成功体験が仕事へのやりがいを生む
小さな成功体験が仕事へのやりがいを生むのは、それが自己効力感と成長の実感を育む、非常に重要なプロセスだからです。
質問やフィードバックで得た学びを実践し、小さな成功を経験すると、あなたの自己効力感が高まります。
自己効力感は、新しい仕事やより難しい課題にも積極的に挑戦する意欲を生み出す原動力です。
さらに、小さな成功を積み重ねることは、あなたの成長を客観的に「見える化」。
「昔は先輩に聞いていたことを自力で解決できた」「フィードバックされた部分が一発でOKになった」具体的な事実は、あなたの成長を証明してくれます。
成長が実感できると、仕事へのモチベーションがさらに高まり、「やらされている」受け身の姿勢からも脱却しやすいです。
自ら考えて行動する主体性が仕事への深い「やりがい」を生み出し、さらなる挑戦の原動力となります。
【まとめ】質問とフィードバックは成長への近道である
この記事では、若手社員の成長を加速させる「質問の仕方」「フィードバック活用法」2つのスキルについて詳しく解説しました。
質問は、ただ答えをもらうための手段ではありません。
まずは自分で調べる姿勢を見せ、結論から簡潔に伝え、そして「なぜ?」と本質を問いてみて。
こうした一歩踏み込んだ質問は、先輩からの信頼と、仕事の本質を理解するための深い情報を引き出します。
また、フィードバックはあなたの行動をより良くするための「ヒント」や「道しるべ」です。
フィードバックを素直に受け止め、具体的な行動につなげる習慣を身につけることで、あなたの成長を、目に見える形で先輩にアピールできます。
「質問」と「フィードバック」のスキルを磨き、社内で信頼されるだけでなく、自分自身でキャリアを切り拓く力を手に入れましょう。